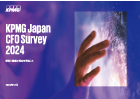KPMGジャパン CFOサーベイ2024は、2019年の調査開始から今年で5回目となります。今回は「変革と信頼の両立を目指して」をテーマに、CFOの役割や機能に加え、CFOに求められる先端的なテクノロジーへの取組みに関する調査も実施しました。
今回の調査によれば、事業の選択と集中について果断な経営判断に対するCFOの役割の重要性が増していることがわかりました。
持続的な企業価値向上のために、さまざまなしがらみや利害関係、バイアスを乗り越えて、経営資源配分の最適化のための果断な意思決定を推進すること。これがCFOが担うべき最も重要な役割と考えられます。
一方で、CFOの責任や管掌範囲はますます広がりを見せ、経営や人事、IR、サステナビリティなどに及び、経理財務部門の責任者としての役割から、経営チームの一員としてコーポレート全般をリードすることまでが、現在のCFOには求められています。
すなわち、事業に係る計数に基づく合理的な根拠と、企業価値に影響する重要な非財務要素データを提供することで、戦略的な意思決定をサポートし、ロジカルにステークホルダーと対話すること。これを通じて、企業価値の向上に寄与することがCFOに求められています。
本調査結果の主なポイントはニュースリリースにて紹介しています。