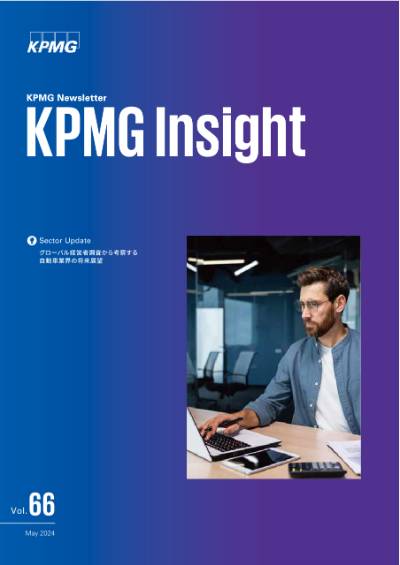2024年1月に発表した「第24回KPMGグローバル自動車業界調査」では、30ヵ国1,000人以上の自動車業界の経営者への調査を通して、自動車業界の現状と将来の展望に関する興味深いデータを得ることができました。本稿では同調査、およびKPMGジャパンで行った、日本消費者調査の結果も合わせて分析することによって、グローバル、日本の自動車業界の将来を展望します。
調査では、今後5年間で自動車業界の利益増を「強く確信している」割合が、前年の「第23回KPMGグローバル自動車業界調査」の41%から34%へ減少しました。なぜ、経営者は自信を弱めているのでしょうか?今までの最大の関心事であったBEV普及の見通しに加え、生成AIにより注目が高まった先端デジタル技術への対応の観点からも検証していきます。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることを、あらかじめお断りいたします。
POINT1:なぜ、経営者は長期的な成長への自信を弱めているのか グローバル経営者はどこに不安を感じているのか。BEV化が長らく経営者の課題の中心であったが、巨額投資に対するリスク対応への焦りと、新たに先端デジタル技術への警戒感を強めている。 POINT2:不透明なBEV普及の見通しとリスクへの備え 引き続きグローバル経営者はBEV普及を楽観視せず、現実的な視点で捉えている。しかし、取り巻く環境の不透明さが増しているなか、リスクへの備えの必要性は増しており、投資の最適化が求められている。 POINT3:先端デジタル技術が起こすイノベーション 2023年の生成AIの急速な普及以降、注目を集めている先端デジタル技術は、販売プロセスやシェアリングにおいても変革をもたらす。 |
I なぜ、経営者は長期的な成長への自信を弱めているのか
今後5年間での自動車業界の利益増を「確信している」グローバル経営者の割合は81%で、前年の83%からほぼ変化はありませんでした。しかし、「強く確信している」と回答した割合は41%から34%へ大きく低下しました。米国(同48%→43%)、西欧(同31%→24%)でも「強く確信している」経営者の割合が減少しましたが、日本の減少(同32%→10%)が特に顕著でした。これらの変化の要因として以下3点が推定されます。
| (1)揺れ動く外部環境の影響を受け、将来に向けた戦略が計画どおりに機能していない。 (2)巨額投資を行っているBEVの普及・コストダウンが想定どおりに進まない場合に、他パワーユニットの生産・販売へ柔軟に切り替えられるようにするための、ヒト・モノ・カネにおけるリスク対策が十分でない。 (3)自動車ビジネスのあらゆる箇所にAIなどの先端技術を組み込むための、人的リソースの確保や外部提携の準備が不足している。 |
ただし、違う視点で今回の結果を捉えると、これらの課題が解決されれば将来の見通しに対する自信が強まり、長期的な成長への期待が高まっていくと考えることができます。
2.短期的な懸念とその要因
今後1年間のビジネスにおいて金利、エネルギー価格、インフレレートの急激な上昇を「強く懸念している」グローバル経営者の割合は、前年の28%から23%へ減少しました。地域別だと、米国(同35%→27%)、インド&アセアン(同64%→34%)で懸念が弱まったものの、中国(同10%→14%)、南米(同17%→31%)で懸念が強まり、地域間の差が明確に出ました。
一方、今後1年間の車両価格の変動予測について、13%のグローバル経営者が10%以上の上昇、64%の経営者が5%~10%の上昇を予想しました。中古車価格の下落や供給不足の改善が進んでいる状況において、車両価格の大幅な上昇は顧客流出などのリスクに繋がる可能性があります。とはいえ、コスト上昇をできる限り価格転嫁したい、というグローバル経営者の思惑が今回の予想からうかがえます。
3.先端技術への対応
「AI/先進ロボなど最先端の生産技術に対する備えができているか」という質問に対し、「非常にできている」、「十分できている」と回答したグローバル経営者は前年の63%から40%へ大きく下落しました(図表1参照)。
【図表1:<グローバル経営者>自社において最先端の生産技術への対応に備えはできていますか(例:AI、Machine Learning、Digital Twins、先進ロボ)?】

出所:KPMG作成
この変化は、2023年の生成AIの急速な普及により、経営者が先端技術の備えへの不足を感じたことが主因だと考えられます。地域別に見ると、備えが「非常にできている」、「十分できている」と答えた比率はインド60%、米国47%、中国46%、西欧34%、日本7%でした。
さらに、「今後数年間で最も重要になるスキルは」という質問において、グローバル経営者のなかでは「AI」が前年の3位から1位に順位をあげました。この質問においても地域差は出ており、たとえば日本は「AI」が4位で、「ハードウェア電動化技術」や「高度な製造スキル」が「AI」を上回りました。
前年まではBEV化への対応に課題感が集中していましたが、生成AIの革新を経て、先端技術への対応がBEV化への対応に並んで経営上の最重要課題として捉えられるようになったと考えられます。
II 不透明なBEV普及の見通しとリスクへの備え
別の調査項目では、BEVへの補助金制度に「賛成する」グローバル経営者が増え(前年75%→84%)、特に「$30,000未満の低価格BEVも補助金制度の対象に含める必要がある」と考える割合が大きく増加しました(前年21%→30%)。
各国の補助金制度の行方が不透明ななか、原材料のCO2排出やリサイクルに対する規制の広がりなどBEVを取り巻くグローバル環境は複雑化しており、BEV普及を楽観視することはリスクとなり始めています。
2.パワートレイン将来投資の見通し
グローバル経営者の70%(前年72%)はBEVへの投資を増やす計画を立てており、引き続きBEVを中心に投資計画を考えていることが分かります。しかし、グローバル経営者の53%(前年51%)はハイブリッドへ、36%(同39%)は燃料電池へ、21%(同38%)はガソリン/ディーゼルへの投資増も計画しています。不透明なBEV普及のリスクヘッジとしてハイブリッドへの投資を計画している経営者が増えている傾向は、この結果からも裏付けられています(図表2参照)。
【図表2:<グローバル経営者>あなたの会社における各領域での設備やR&Dに対する将来投資の見通しを教えてください。】

出所:KPMG作成
3.日本の消費者のニーズ
日本の消費者が今後5年以内に車を購入する場合に選ぶ車両は、第1位がエンジン車で64%(前年52%)、第2位がHEVで36%(同33%)、第3位がPHEVで13%(同10%)、第4位がBEVで13%(同12%)という調査結果でした。
年齢別で見ると、60代でエンジン車を選択した比率が対前年で8ポイント(39%→47%)増加し、他年齢層とエンジン車を選択する割合がほぼ等しくなりました(図表3参照)。
【図表3:<日本の消費者>今後5年以内に車を購入するとしたら、どのクルマを選びますか?(年齢別)】

出所:KPMG作成
また、現在のBEV/PHEVユーザーの44%はエンジン車、26%はHEVを選択すると回答し、PHEV、BEVを再購入する考えを持っているユーザーは、それぞれ11%、13%と限定的でした。
BEVを選択しない理由は前々年、前年から変わらず「充電インフラの問題」、「購入価格の問題」が最大で、消費者の視点ではいまだそれらの課題は解決されないままです。その状況も要因となり、日本の消費者のBEV購入意向は、グローバル経営者のBEV普及予測から引き続き乖離しています。
日本のBEVは軽自動車・高級車が主流となり独自の市場を形成しつつありますが、これからのBEV投資をどの市場・ターゲット層に向けていくべきか、各国の充電インフラ拡充に対する取組みやユーザーの車の使い方を踏まえて、注意深く検討していくことが求められています。
III 先端デジタル技術が起こすイノベーション
【図表4:<グローバル経営者>あなたの国では2030年に、何%の新車が各チャネルを通して販売されると思いますか?】

出所:KPMG作成
自動車業界では、先端デジタル技術の活用により、ディーラーの提供する試乗や実車展示をリアルからバーチャルへ、アフターサービスを実車整備からリモート整備へ、消費者とのコミュニケーション相手を人からAIへと代替させていく検討が進んでいます。
ただし、オンラインで車を購入したいと考える日本の消費者が引き続き限定的なように(前々年22%→前年25%→今年23%)、必ずしもデジタルテクノロジーの進化が消費者ニーズの変化につながるとは言えません。そのため、これらの施策についても消費者の受容性を確認しながら進めていくことが重要になります。
2.シェアリングビジネス
日本の消費者でカーシェアリング/MaaS(携帯などで予約できる配車サービス)を利用したいと回答した比率は前々年、前年の調査結果からほぼ変わらず37%と限定的でした。ただし、利用しない理由は変わってきており、「シェアリング自体への抵抗」は低下し、「自由に利用できない可能性がある」が上昇しています。
日本では、カーシェアリングの会員数・車両数が共に右肩上がりで伸びているものの、ステーション数の伸びは鈍化しているため、消費者が利用したい場所にカーシェアリング車両が無い可能性があります。
解決策の1つとして、「消費者が安心して自宅の空きパーキングをステーションとして貸し出せるようにする」対策が考えられますが、その実現にはAIを活用した監視機能が有効だと考えられています。ただし、消費者を納得させるには、同時にサイバーセキュリティやプライバシー保護の対応が必須であることは明らかであり、包括的なAI戦略の下、対策を進めることが求められています。
Ⅳ さいごに
今回の調査を通して、グローバル経営者は将来戦略、リスクへの備え、先端技術への対応の再確認が必要だと考えていることがうかがえました。それはグローバル経営者が悲観的になっているということではなく、外部環境やテクノロジーの変化に対応しようという意志の表れであり、明確化した課題への対応が進めば力強い成長を自動車業界へもたらしてくれると期待できます。
特に注目すべきは、先端デジタル技術への対応がBEV化と並ぶ自動車会社のトップ課題として認識され始めた点です。経営者からすると、最重要課題が1つから2つに増え、警戒すべき領域がまた広がった状況ではありますが、別の見方をすれば、どこの強みを目指して長期的な成長を進めるのか、戦略の選択肢が膨らんだと考えることができます。
別の調査項目では、車のソフトウエア化が創出する新ビジネスの恩恵を最も受けるのは「自動車会社」だと見通している結果も出ており、自動車会社にとってプラスの選択肢が多いことは歓迎すべき状況だと言えます。戦略を明確に持ち、外部環境の変化に対応できるリスク管理と新たな機会の獲得を進めていければ、競争力のあるビジネスモデルが構築できるはずです。
執筆者
KPMGコンサルティング
パートナー 犬飼 仁
アソシエイトパートナー 轟木 光
マネジャー 大熊 恒平
マネジャー 小谷野 幸恵