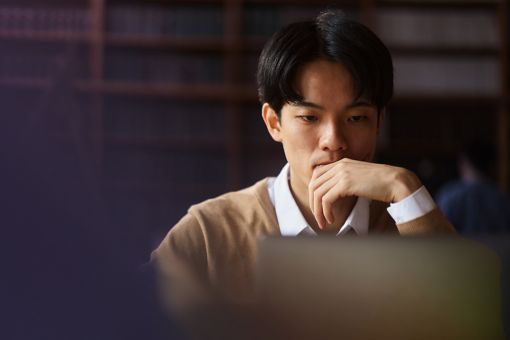連載特別対談第2弾。今回は、次々と新しい試みを実践し、世界中から学生を惹きつける経営手腕に注目が集まるテンプル大学日本校(以下、TUJ)のウィルソン学長にお話しを伺いました。過去には挫折も経て到達した大学経営への思いとは…。
マシュー・J・ウィルソン(Matthew J. Wilson)氏
プロフィール
テンプル大学日本校学長。
テンプル大学ビーズリー・スクール・オブ・ロー法務博士。法曹界、国際ビジネス界での豊富な経験を持つ。TUJ副学長・顧問弁護士、アクロン大学学長、ミズーリ・ウェスタン州立大学学長等を経て、2020年より現職。
学生の成功を重視する姿勢や革新的な経営戦略を打ち出し、日本各地の大学・地域との連携も積極的に進めている。


テンプル大学日本校学長 ウィルソン氏
テンプル大学・TUJ概要
|
テンプル大学日本校の教育
―まずはTUJ京都キャンパスの開校おめでとうございます。
ウィルソン氏:ありがとうございます。新しいキャンパスは大きな挑戦ですが、今秋には学生数が両キャンパス合わせて3,500人に達しました。メインキャンパスでのガイダンスも一度では収まらないから3回に分けて実施しています。人数が増えると運営は大変になりますが、それだけ大学への期待が広がっていると受け止めています。夏休みには小・中・高校生向けのサマースクールも開いているから、キャンパスがいつもにぎわっていますよ。
―はじめにTUJの教育について教えてください。大学全体の教育力を、どのように高めていらっしゃるのでしょうか。
ウィルソン氏:TUJは「学生ファースト」をはっきりと掲げています。アメリカの大学らしくリベラルアーツ教育を基盤にして、幅広い分野を学びながら問題解決力やコミュニケーション力を鍛えていく。AI時代に必要な判断力も含めて、どこへ行っても通用する力をつけてもらいたいと思っています。
そのために優れた教員の採用には力を入れていて、今は教員が約270人。京都と東京を合わせて教職員は約500人います。常に学生とのコミュニケーションを大事にしながら教育の質を維持する制度づくりに力を入れています。
教育検討委員会では授業内容をかなり吟味していて、「化学」の授業でワインをテーマにしたり「会計」で家計簿を扱ったり、身近な題材で学びを実感できる工夫をしています。
教員の研修も徹底していますよ。フィラデルフィア本校の教育センターの研修を受けてもらい、TUJ独自でも教育専門家を置いています。コロナ禍でオンライン授業にシフトしたことが教員の意識を大きく変えました。それをきっかけに、専門副学長や教育デザインの専門家を採用してより実践的な教育体制を作ってきました。
教育業績の評価とインセンティブ
―日本の大学にも研修制度はありますが、教育活動へのインセンティブが弱い面もあります。TUJではどのように評価と動機付けを行っていますか。
ウィルソン氏:TUJは「学生ファースト」を掲げて教育を重視しているから、それを仕組みとしてはっきりさせています。評価は「研究・教育・大学運営(サービス)」の三本柱で行い、それぞれが給与や昇進に直結します。だから教員も教育改善への意識が高まるし、研修に参加したり新しいプログラムに取り組んだりすることが大学への貢献としてしっかり評価されています。
授業の評価も多面的です。ポートフォリオや評価者による授業観察、それに学生アンケートも重視します。これもただのアンケートではなく学部や教授間で比較できるようにしているので、自分の強みや改善点がよくわかります。優れた授業には表彰制度もあって、受賞者はフィラデルフィア本校の式典に招待しています。
教育を頑張れば報われるといつも伝えているのも教員のモチベーションにつながっていると思いますね。
教育力の可視化と学生の声
―なるほど。教育やサービスにも明確なインセンティブがあるのですね。大学の実態を社会が知る機会は少ないですが、教育力をもっと可視化することはできるのでしょうか。
ウィルソン氏:公式な仕組みとしては、アメリカでも「認証評価(accreditation)」が義務化されています。テンプル大学も7年ごとに全学的・部門別の審査を受けて、その時には学生の声も必ず反映されます。ただ、結果を公表する大学は少ないし、仮にいい結果が出たからといって公開しても読む人はほとんどいないので、認証の内容に社会的なインパクトはあまりないですね。
―大学ランキングや格付け(rating)も、実際の教育内容は見えませんね。
ウィルソン氏:そのとおりです。格付け会社の人と話しても、授業の中身や教員の工夫までは把握できていません。学長同士で話をしても、実際にどう教えているかまでは共有されないから、結局、自分の目で確かめにいかないと本当のところはわからない。教育の可視化は難しい問題ですよね。
ただ、社会に一番影響力があるのはやっぱり学生の声だと思います。
TUJの場合、学生がStudent Workerとして大学運営に関わっています。たとえば広報は、FacebookやInstagram、TikTokのSNSチームに学生が入ってコンテンツ制作を担当しています。学生は友人同士や家族とはSNSでいつもつながっていますよね。そこでの体験談や感想はリアリティがあって、結果的に大学の評価につながっていきます。これは自然で効果的な可視化じゃないでしょうか。
大学経営に必要な視点と実務理解
―学生のリアルな声は同世代にも共感されやすいですよね。次に、こういった方針を決める大学経営についてお聞きします。TUJはどのように方針を決めていますか。
ウィルソン氏:私が学長になった時、TUJを「学生ファーストの大学」とはっきり打ち出しました。TUJの収入の大半は授業料で、学費は年間約170万円です。フィラデルフィア本校や米国連邦政府、日本の文部科学省から補助金を受けていないので、その分自由度は高いです。もちろん役員会を通しますが、最終的には学長のリーダーシップで決めていきます。


テンプル大学日本校学長 ウィルソン氏
―日本でも学長のリーダーシップは重視されています。ただ、多くの場合、学長は教授から選ばれるのですが、経営者としての教員のキャリア形成についてはどうお考えですか。
ウィルソン氏:教授にいきなり経営感覚を持てと言われても難しいですよね。どうしても教授としての価値観に判断が引っ張られてしまいます。私の場合は、日本企業で働き、国際弁護士を経て大学顧問をやり、それから教育の世界に入りました。アメリカでいくつかの大学の学長を経験して、ようやく教育と経営の両方を理解できるようになったと思います。
多くの学長から「なぜそんなに早く改革を進められるのか」と聞かれることがあります。リスクは当然ありますが、リスクを取らなければ前に進めない。このバランス感覚も、ビジネスと大学の両方を経験したからこそ身に付いたと思いますね。
―経営と大学、両方の経験ですね。日本では大学教員が外の世界と行き来することは少ないですが、大学経営の視点を育てるにはどうすればいいでしょうか。
ウィルソン氏:やっぱり「外を知る」ことです。ビジネスの現場でもいいし、他大学の動向を知るのも大切です。内部に閉じているとどうしても変化に対応できなくなります。
私の体験談になりますが、2005年にTUJの副学長をしていた頃、学長公募に立候補しました。世界から100人以上の応募があって、最終的に他の大学の学長に負けてすごく悔しかった。でもそのことがアメリカでの複数の大学の学長を務めるきっかけになったのです。
リベラルアーツ教育の責任を負う学長になると、自分の専門(法学)だけでなくアートやサイエンス、心理学やコミュニケーションまで幅広い理解が求められます。私は副学長時代に挫折したことで、かえって幅広く学び直すことができました。今振り返れば、あの時学長になれなくてよかったとつくづく思います。
若いうちからの経営感覚の醸成
ウィルソン氏:もう1つ大事なのは年齢ですね。日本では学長就任が遅いケースが多いですよね。60歳を過ぎてからだと任期中にできることが限られてしまいます。次の学長になれば別の計画を立てるとわかっているから、部下の教員や職員も意見が合わない時はとりあえず時間をかせいでおこう、となりがちです。
私が初めに学長になったのは40代後半で元気いっぱい。何かを成し遂げようという意欲も強かったし、将来を長く見据えて計画を立てられるからできることがたくさんありました。
―なるほど。大学人も、若いうちから経営視点を持つことが重要ですね。
ウィルソン氏:そう思います。日本では最高裁の判事でも60歳前後に就任して70歳で引退です。数年かけて仕事を理解しても、改革に使える時間は限られてしまう。
私もTUJで副学長になった時は、最初から学長になりたいとは考えていませんでした。でも、学長選に挑戦したことで大学経営を考えるようになり、その後のキャリアにつながりました。3つの大学でトップを経験するうちに、どうやって大学の課題を解決するかということに強い関心を持つようになったのです。日本の大学では学長を最後の花道のように考えることもありますが、気づきが実践される前に終わってしまうのは本当にもったいないと思います。

テンプル大学日本校学長 ウィルソン氏
―大学に問題意識を持っている先生は多いと思います。そうした教員が大学経営へのキャリアを積むにはどのような姿勢が必要でしょうか。
ウィルソン氏:まずは幅広い興味を持つことですよね。自分の専門にとどまらないで、できるだけ多くの学科や同僚と協働してみること。研究から大学教育の課題を探ることもできるし、実践的な活動につなげることもできます。たとえボランティア的な取組みだとしても挑戦してみたらいい。
確かに日本の大学は変革が難しい環境かもしれません。それでも大切なのは関心を持ち続けることです。その姿勢が将来の大きなチャンスを引き寄せるはずです。
日本の社会慣習に対して思うこと
ウィルソン氏:私は日本が大好きですよ。人は優しくて安全だし、街はきれいでごみも落ちていない。貧しい人をあまり見かけないし、交通機関は便利です。物価も安いし文化は豊かでどこへ行っても時間やルールが守られている。とても住みやすい、いい国です。
―それは規制や仕組みの強みですね。そのかわり課題もありますよね。
ウィルソン氏:そうですね。規制には良い面がありますが、時にものごとを停滞させてしまいます。文科省の管理も同じで、整える力はあるけれど抜本的な改革にはつながりにくい。創造的な人がいないのではなくて、成功しにくい環境になっているように感じることがあります。
日本に戻ってきて驚いたのは、10年前とほとんど変わっていないように思えたこと。新しいビルは建っているし、見た目は変わったけれど、銀行ではいまだに対面でハンコが必要で、テレビも以前と同じような番組をやっている。世界が動き続けているのに、日本は変わらない。良い意味でも悪い意味でも安定を守っているのです。
一人ひとりが「必要性」を感じるエネルギーを持つ
―何が問題なのか、一人ひとりが自覚できるかどうかですね。日本の大学も変われると思いますか。
ウィルソン氏:もちろんです。どんな組織でも本気で変わろうと思えば変われます。ただ、そのためには変わりたいという意志と、どう変えるかを考える力が必要です。
日本では、よく「仕方がない(It can’t be helped)」と言いますが、私はこの言葉が嫌いです。だって「仕方はある(It can be helped)」んですよ。方法は必ずある。大学だって改善の道を探せば変われるはずです。日本は十分な能力を持っているのに、現状維持の方が楽だからそちらを選んでしまうのかもしれません。留学も同じで挑戦するより楽な道にいってしまう。でも、本心から必要性を感じたら、人はエネルギーを出せるのです。
日本は少子化が進んで、大学は差別化しなければ生き残れません。今こそ進化の時だと思います。実際、TUJの取組みに関心を持ってくれる大学関係者はたくさんいますし、あとはそれを実践につなげられるかどうかです。
TUJにも課題はあります。三軒茶屋のキャンパスは学生数の増加で物理的に限界に近づいているし、拡大には教員や職員の質の維持も必須です。それでも国内外からTUJに学びたいと思ってくれる学生に、どうしたら質を落とさず学習環境を広げられるか。私自身、いつも「必要性」を感じながら経営に取り組んでいます。だからこそ、ここTUJで挑戦を続け、日本の教育に新しい選択肢を示していきたいと思っています。
インタビュー実施日:2025年8月27日
聞き手:KPMGコンサルティング スペシャリスト(リードスペシャリスト) 田中 智麻