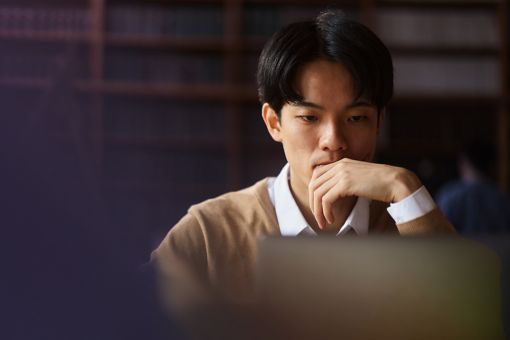1.はじめに
昨今、「連携」や「協働」という言葉を耳にしない日はありません。
こうした言葉が日常的に使われるようになったのは、1995年の阪神・淡路大震災以降です。まちづくりにおいて住民と行政の共助の関係を築くことへの認識が高まり、2011年の東日本大震災はその経験も活かして、より高度な協働の減災活動が行われました。持続可能な社会の実現にとっての協働の効果が広く認識され、公共性の高い領域を中心に連携・協働の取組みが定着しつつあります。
そして、大学もまた、地域社会の一員として、研究の拠点であると同時に社会に資する人材育成の場であることが求められるようになりました。本連載第2回で見たように、大学教育において汎用的能力の涵養が求められるようになっており、実社会との関係性をきっかけに新たな教育方法を模索する試みも生まれてきました。そこで取り組まれたのが「地域連携」です。
一方、資金や経済的成果が伴う点で注目されやすいのが「産学連携」です。○○大学と△△企業の共同開発や、大学発スタートアップへのファンド出資といった動きがメディアを賑わせ、研究資金や事業出資など資本が動くのは主としてこちら側です。
一見すると両者は「大学の社会連携」という同じ枠組みに見えますが、実際には目的も性質も大きく異なっているのです。
2.大学の社会連携
大学の社会連携のなかでも、地域との連携は全国の国公私立大学で広く取り組まれています。たとえば、文部科学省が主導した「地(知)の拠点事業」では、自治体、大学、地域企業などが連携し、全国約200の大学が参画しました。商業や工業、交通、防災、観光、異文化交流など、地域に根ざしたテーマを扱いながら、地域振興やまちづくりに関するPBL(Project-Based Learning)型の授業やプロジェクトが展開されています。学生にとっては、自ら考え、協働し、実行するプロセスを体験できる貴重な学びの機会となり、新聞等で取り上げられることも多く、教室とは異なる楽しさややりがいを感じられるため、好まれる傾向もあります。
こうした地域連携の取組みは、学生の「考える力」や「協働する力」などの汎用的能力の向上にも一定の効果があることから、単発ではなく、年次の進行に応じた段階的なカリキュラムとして整備する大学も増えています。
一方で、その成果の可視化は容易ではありません。定量的な成果としては、参加学生数や連携団体数、共同事業数などが挙げられますが、教育的な効果は関係者への聞き取りなど定性的な評価にとどまり、明確な指標化が困難です。また、実践的教育の多くは教員の裁量に依存しており知見の蓄積が難しいという課題もあります。
多くの大学は、地域連携を推進するため、自治体・大学・地域企業を主たる構成メンバーとして連携プラットフォームを設置します。これが共同事業を生み出す場となりますが、プラットフォーム設置が国の補助事業の要件である場合も多く、事業終了後も推進母体として継続できるかどうかが課題です。このような事情から、大学教育が地域社会の将来像に対してどれだけ構造的な変化をもたらしているかといった本質的な議論にはなかなか至らず、大学による地域連携の意義や教育的成果が社会にとって見えにくい状況となっています。
研究開発を主眼とした産学連携
それに対して、企業との連携は、研究者と企業が協働して研究開発を進める産学連携が長く行われてきました。政策的にも、産学連携による技術革新を長期スパンで後押しする比較的大規模な支援策がとられ、2020年前後からは、経済産業省や内閣府が大学を起点としたイノベーション創出やスタートアップ支援を加速させています。企業が人材コーディネイトやマッチングプラットフォームを担うケースもあります。
こういった産学連携は、大学は研究力の世界的地位や資金獲得、企業は技術革新や研究成果の事業化というように、双方に明確な目的があります。そこで顕在化したニーズが起業家精神の育成であり、学生を対象にしたアントレプレナーシップ教育が行われるようになりました。主に、マーケティング、財務、事業戦略といった文理横断型の知識を授ける授業が行われています。起業に必要な企画力や協働力を養うことを目的にしたPBL型授業が設けられることもあります。また、企業や業界団体が主催するピッチコンテストも開催され、意欲のある学生にとっては起業機会や支援策が充実しつつあります。
とはいえ、産学連携はあくまで研究開発が主たる目的で、学生が研究開発の現場に触れる機会があることは非常に有意義ですが、教育としての位置付けは確固たるものがありません。アントレプレナーシップ教育としてのPBL授業も、地域連携を通した教育と同様に教員や外部講師による個別プロジェクトが多く、大学全体の教育力としての蓄積が課題です。
さらに、産学連携の研究開発を後押しする施策として、経済産業省と文部科学省が推進する「クロスアポイントメント制度」があります。研究者を大学と企業の双方に所属させて研究開発を加速する制度ですが、産業界での認知は十分ではなく、経団連も2025年の提言で活用の促進を呼びかけています。主に研究目的の制度ですが、今後は教育的観点からの活用も検討の余地があります。
連携の担い手
大学と社会をつなぐ連携を担う人材も多様化しています。
たとえば、研究開発の推進役として、URA(University Research Administrator)が登用されるようになりました。URAは、大学の研究シーズと企業のニーズをつなぎ、研究と経営を橋渡しする専門人材です。研究知識、資金調達、事業推進といった専門的知見から経営的スキルまで幅広い能力が求められるため、役割をわけてURAを置く大学もあります。
地域連携においては、連携の形態によって担い手が異なります。教員自身が担当する場合もあれば、大学の社会連携部門の職員、あるいは専任の連携コーディネーターが任用される場合もあります。URAや連携コーディネーターは連携の推進役ですが、一般的には教育者ではありません。また、その人件費は補助金で賄われることも多く、事業終了とともに雇用契約も終了するため、ノウハウの継承が課題です。
また、実践的な研究や教育を担う存在として近年増えているのが実務家教員です。企業や行政などの実務経験を持ち、大学での研究や教育に携わる教員ですが、その役割や制度設計は曖昧で大学によってさまざまです。実務家教員はその専門に基づき授業も担当しますが、実務経験があることすなわち教育即戦力ではなく、研究者と同じように教育者としての心構えや手法の習得が必要となります。
社会連携の教育的側面の見えにくさ
研究開発を軸とした産学連携は、主に研究大学や研究者を中心に広がっており、国による資金的な支援も豊富です。産学連携に力を入れる大学は研究志向が強く、社会連携も研究との結びつきが中心で、教育が主目的にはなりにくい傾向があります。一方で、広範な大学が取り組む地域連携は、大学と地域社会との関係性を基盤とし、プラットフォームの形成を通じて取り組まれる事業は学生の教育プログラムとして結実したケースも多々あります(下図参照)。
つまり、汎用的能力を育むような実践型教育は、地域連携に意欲的な大学が、地域との関係構築を通して教育方法を試行錯誤してきたと言えます。こうした大学に通う学生にとっては、4年間の学生生活を通じて多くの実践的な学びの機会が提供されており、実際にそうした彼らに対しては、企業や地域社会からも総じて高評価です。
しかしながら、こうした学びが育まれる教育体系は明確ではなく、その成果の可視化も難しく、社会に向けて発信する手段は限られています。結果として、就職活動などの場面では、学生自身のアピール力に委ねられ、大学名や肩書といったわかりやすいバッジが勝ってしまう現実もあります。
【大学の社会連携マトリックス】

出所:KPMG作成
執筆者
KPMGコンサルティング
スペシャリスト(リードスペシャリスト) 田中 智麻