ドナルド・トランプ氏が2025年1月20日、第47代アメリカ大統領に就任し、第二次トランプ政権が幕を開けました。アメリカ・ファーストを掲げるトランプ氏の政策が世界にどのような影響を及ぼすのか注目が集まっています。
今回は、アメリカの現代政治が専門の前嶋和弘氏(上智大学総合グローバル学部教授)をお迎えし、アメリカの政権交代に関連したビジネスへの影響について議論しました。
前編である本稿では、まず2024年大統領選の概要やアメリカの現状、第二次トランプ政権が目指す方向性を振り返りながら、日本企業に求められるリスク点検について確認します。
※本稿はトランプ氏のアメリカ大統領就任前の2024年12月11日に実施した座談会を編集したものです。記載している内容は、KPMGコンサルティングの意見を代表するものではないことをあらかじめお断りします。
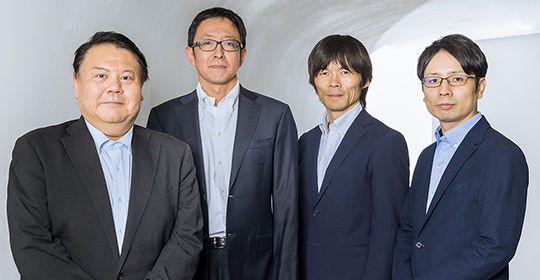 左から 上智大学 前嶋氏、KPMG 足立、白石、新堀
左から 上智大学 前嶋氏、KPMG 足立、白石、新堀
【インタビュイー】
上智大学 総合グローバル学部教授 前嶋 和弘 氏
KPMGコンサルティング
執行役員 パートナー 足立 桂輔
アソシエイトパートナー 新堀 光城
マネジャー 白石 透冴
2024年大統領選が映し出したアメリカの今
足立:2024年11月のアメリカ大統領選挙ですが、ビジネス界でこれほど注目を集めた選挙はこれまでなかったのではないでしょうか。実際、多くの企業経営者が「これからビジネスにはどんな影響が出てくるか」と気にされています。トランプ氏の勝利を、前嶋先生はどのようにご覧になりましたか。
前嶋氏:ビジネス界の方々が関心を持たれているのは、2017年からの第一次トランプ政権の時と同じく、状況が「大きく変わる」ことがわかっているからだと思います。
アメリカは今、未曾有の分断が起きている状態です。「トランプ氏の圧勝」と報じる日本のメディアもありましたが、実際にはトランプ氏と民主党候補カマラ・ハリス氏の得票率の差はたった1.5ポイントです。前回の大統領選では、ジョー・バイデン氏が4.5ポイント差で勝利していますから、その3分の1の差、ということになります。
大統領選挙と同時に実施された議会選挙の結果、上院と下院も共和党が押さえましたが、内実を見てみると過半数をわずかに上回る議席数を確保しているだけで「多数派」と言い切るにはかなり弱い。和製英語で「トリプルレッド」とも言われますが、薄い薄いレッドであると言わざるをえません。
今回の結果で、民主党サイドはかなりのショックを受けていますが、共和党と民主党の勢力が拮抗する状態は今後も続いていくでしょう。トランプ政権がいくら「気候変動対策は敵だ」「ウォークネス(社会の持続性や差別撤廃に高い意識を持つこと)を潰す」と主張したところで、アメリカ国民の半数近くはそうした主張を批判的に見ているということです。
 KPMG 足立
KPMG 足立
 上智大学 前嶋氏
上智大学 前嶋氏
新政権の顔ぶれからわかること
足立:トランプ新政権の人事を見ると第一次政権の時とは変わって、トランプ氏と思想を同じくする人々で固めています。政策の実行力が高いイメージです。
前嶋氏:トランプ氏のドリームチームになっていますね。吹けば飛ぶような僅差で勝ったからこそ、自分の主張を推し進めるために足元を強固にしたいという意図が見て取れます。就任してから最初の100日で急いで種を植え、後から不満が出てきたら調整をする、という進め方になるのではないでしょうか。
トランプ氏が掲げる減税や規制緩和ですが、これは結局、富裕層のための政策です。最終的には貧しい層が喜ぶものにはならないでしょう。目玉の公約である関税引き上げについても、貧しい層にとっては購入品の値上がりにつながるとの指摘がある消費税のようなものであり、いずれ不満も出てくるのではないでしょうか。
エネルギー政策では「掘って掘って掘りまくれ」というトランプ氏の言葉が有名ですが、そもそも利益がないと民間企業は掘りません。エネルギーが安くなればなるほど、事業者にとっての掘削のためのインセンティブ(動機付け)も減ってしまう。採掘にもかなりの時間がかかります。
トランプ氏の打ち出している政策はどれも派手ですが、よく考えてみると実現性が不透明なものは多々あります。
政権の目玉「関税政策」を読み解く
新堀:トランプ氏は自身を「タリフマン」と称するほど、関税政策について繰り返し発信してきました。今回の大統領選挙でトランプ氏の支持率を押し上げた要因として、インフレに直面する有権者の苦しみもあったと聞きますが、関税はインフレを助長する側面もあります。
化石燃料回帰を軸とするエネルギーコストの削減によるインフレ対策を進める旨を掲げていますが、日本の企業としては、どこまでトランプ氏が公約どおりの関税政策を実行していくのかを慎重に見極めながら対応する必要があると思います。前嶋先生はトランプ氏の関税政策についてはどのようにご覧になっていますか。
前嶋氏:わからない部分が多分にあります。関税について、すでに発表されているのは、メキシコとカナダからの輸入に25%、中国に10%の追加関税を課すというものです。メキシコとカナダについては「犯罪者の薬物の流入が止まるまで」という説明を、中国については「もし台湾に攻め入ったら150%~200%」と発言したこともあります。
ただ、どれだけトランプ氏が本気で発言しているかを見定める必要があり、数字自体に意味があるかどうかは懐疑的です。たしかに、関税がインフレを助長する可能性はあるので、そうならないように調整をしていくのではないでしょうか。
 KPMG 新堀
KPMG 新堀
新堀:関税を上げるタイミングも、先ほど前嶋先生からお話のあったエネルギーコストとのバランスで見ていくのかもしれません。
関税のほかに、安全保障貿易管理の観点も重要かと思います。従前の「スモールヤード・ハイフェンス(輸出管理の対象を絞って厳重に管理する)」の方針が、実質的に「ミドルヤード・ハイフェンス」に変化していくのかについても関心が高いです。
第一次トランプ政権、バイデン政権ともに、対中輸出規制を強化してきました。トランプ氏の発信や主要閣僚候補の顔ぶれを見ても、その傾向は変わらないか、一層強化されるようにも思われますが、どのような点に着目されていますでしょうか。
前嶋氏:第一次トランプ政権時の流れを受けて、デカップリングのさらなる細分化が進行すると見ています。たとえば大豆の輸出であれば、政権としてはどんどんと拡大していきたいわけですが、安全保障関係のものはきっちり切って規制していく、という動きが拡大していくと思います。
現在、共和党のなかで中国への好感度は非常に低い状態です。中国という国へのリアリティが薄く、台湾侵攻が「今にも起きる」と考えている議員もいます。また、不法移民は共和党が支持基盤とする地方よりも民主党の支持基盤の都市部に多いわけですが、不法移民への嫌悪感は共和党支持者の方が強い。つまり、中国への嫌悪感も、不法移民への嫌悪感も、「見たことがない」ということに起因していて、これはトランプ氏にとっては安全保障の口実として使いやすいカードとなります。対米外国投資委員会(CFIUS)が今後、政治的な動きを受けてより厳しい対応に出ることも想定されます。
新堀:今のお話だと、アメリカとしては中国にモノを売りたい。一方で、安全保障の観点で中国を利するところは制限をし、バランスを取っていくということでしょうか。
前嶋氏:そうですね。トランプ氏にとっては、中国の習近平国家主席と話し合いたくさん米国製品を買ってもらった、となるのが最良です。唐突にトランプ氏と習氏がディールを進めてしまうことが考えられ、アメリカの同盟国である日本の立場からすると、台湾や安全保障の話はどこにいったの、と感じる展開になるかもしれません。
新堀:一方で、中国は2024年にガリウム、ゲルマニウム、黒鉛など重要鉱物の輸出規制を強化してきましたが、アメリカに対する中国の対抗措置として、日本企業が留意すべきポイントはどのあたりになるでしょうか。
前嶋氏:アメリカと中国のデカップリングについて、当初は不可能だという見方が大勢を占めていたと思います。中国が世界の工場となり、アメリカの工場となり、貴重な鉱物などの原産物をアメリカに提供してきました。切り離すことは不可能だと思われてきたけれど、現状はどんどん切り離しているという状況だと思います。
中国の対抗措置としては、アメリカで必要とされているものを切り離していくことが考えられます。たとえば太陽光パネルで用いられるような鉱物です。また、中国はアメリカとその同盟国に、中国にしかないものを売らない、という出方をする可能性もあります。それがレアアースだったりすると、アメリカ以上に日本企業や日本政府が困ったことになります。このあたりの動きは注視しないといけません。
サステナビリティめぐる動向に注視を
新堀:安全保障貿易に関する政策が、気候変動対策にも影響するという点も見逃せないかと思います。また、気候変動対策自体の変化の可能性も重要な論点です。トランプ氏は選挙戦の公約で地球温暖化対策の枠組みであるパリ協定離脱、化石燃料回帰を謳っていました。同時に、サステナビリティをリードしてきたはずの欧州でも、エネルギーコストの高騰、極右政党の台頭など、サステナビリティ政策について反発する動きが出てきています。2024年9月に公表された元イタリア首相のマリオ・ドラギ氏による報告書「ドラギレポート」でも、野心的な脱炭素目標が産業界の負担になっている、との指摘がなされました。
ダイバーシティ政策についても、米国では反発する動きが活発化し、ダイバーシティ方針の撤回やダイバーシティ推進部署を解体するケースも出てきています。さらに、ESG投資に関しても、そのパフォーマンスへの疑念も広がるなか、気候変動に対する投資家イニシアティブなどから大手金融機関が相次ぎ脱退していますが、トランプ氏もESG投資を制限する政策を公約に掲げています。このような「サステナ疲れ」や「反ESG」をめぐる動きも念頭に、トランプ政権の動向を注視する必要があると考えています。
前嶋氏:トランプ氏の考え方は、わかりやすく言えば「反ウォークネス」ですよね。「ウォーク(英:Woke)」はもともと、気候変動や人権、ジェンダー平等、ダイバーシティを推し進めようと社会の問題に対して「目を覚ました」人たちという意味で使われている言葉です。トランプ氏はこれに対して「戦っていく」という姿勢なわけです。日本企業も、アメリカで展開するCMやキャンペーンには慎重になる必要があるかと思います。ただ、そのまったく逆の動きもアメリカ国内にはあるわけで、アメリカが必ずしも反ウォークネスだけに向かっているわけではない、ということは頭に置いておく必要があります。
インフレ削減法はどうなるか
新堀:バイデン政権の目玉だった「インフレ削減法(IRA)」は今後どうなるでしょうか。 IRAは、クリーンエネルギー投資やEV(電気自動車)製造への税額控除、補助金などサステナビリティ的な側面を持ちながら、保護主義的であるとの批判も欧州からありました。IRAから恩恵を受けている共和党支持層もいます。トランプ氏にとっては、今後進めたい政策の方向性と合致する部分と、そうでない部分の両面があるように見えます。
前嶋氏:IRAはトランプ氏による撤廃も囁かれていますが、アメリカの現状を見ていると「衣替え」といった程度の改定にとどまるのではと思います。たとえば、今まではクリーン水素を製造すると受けられた税額控除がありました。この対象をあまり環境には良くない、化石資源から抽出される「グレー水素」にまで広げることが考えられます。
ほかに、EVを購入した際に最大7,500ドルの税額控除を付与するとした決定を残すかどうか。自動車工場が多い南部の共和党支持者には、CO2を排出するかしないかには関心の薄い人も多いですが、税額控除はありがたいという本音もあります。
アメリカと中国の距離感
足立:アメリカがEVや再生可能エネルギーの分野で消極的になれば、中国が存在感を増し、アメリカに代わってリーダーシップを発揮する、とも言われています。総じてアメリカが自国ファースト、内向きとなれば、中国が各国と関係を強化する可能性も高まるように思います。今後、世界におけるアメリカと中国の距離感はどうなるでしょうか。
前嶋氏:距離感がどうなるのか、微妙なところです。中国は「新しい国際秩序」の構築に意欲的でしたが、経済成長は鈍化しており、存在感を発揮するのは難しくなっていくのではないかと思います。
中国にとって、EVが欧州やアフリカ、ブラジルでどんどんと売れるのは嬉しい話であり、この分野では中国が天下を取るかもしれません。アメリカとしては、EVに注力するのではなく圧倒的な化石燃料で対応しようという算段かもしれませんが、どうなるか先行きは見通せません。
足立:ありがとうございます。前編では、第二次トランプ政権の概要や、対中国を意識した関税政策を中心にお話をうかがいました。後編では、欧州、東アジアにも視野を広げていきたいと思います。
<話者紹介>
上智大学 総合グローバル学部教授 前嶋 和弘 氏
1990年上智大学外国語学部卒業、2001年米メリーランド大学大学院博士号取得。敬和学園大学、文教大学勤務を経て2014年4月より現職。専門は現代アメリカ政治・外交。アメリカ学会会長も歴任。
KPMGコンサルティング
執行役員 パートナー 足立 桂輔
2003年よりKPMGに勤務。その間、KPMG中国での勤務を経験。現在、ガバナンス、サステナビリティ、リスクマネジメント等のサービスをリード。
アソシエイトパートナー 新堀 光城
弁護士。経済安全保障・地政学サービスチームリーダー。
国内外のリスク管理・規制対応・サステナビリティ施策のほか、中長期戦略策定に向けたビジネス環境分析支援等に従事。
マネジャー 白石 透冴
元日本経済新聞社パリ ジュネーブ支局長、エネルギー報道チームリーダー。
KPMGでは企業の経済安全保障リスク対応、有事コミュニケーションなどの危機対応支援を担当。





