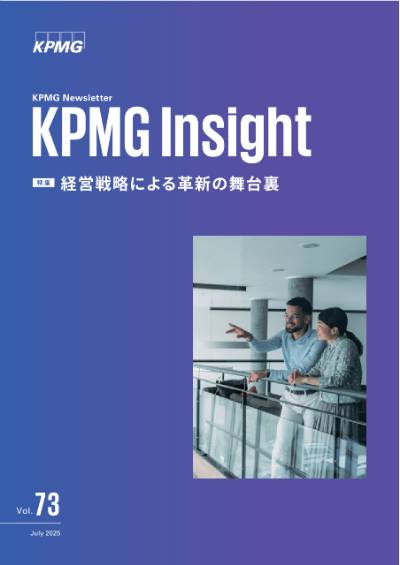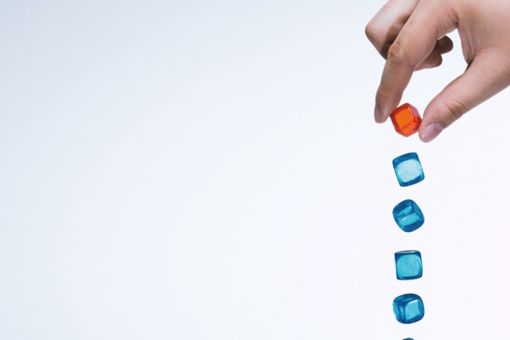経営戦略のためのコーポレートブランディング~INPEX 新ブランディング戦略の舞台裏~
本稿では、このプロジェクトを主導した同社取締役専務執行役員経営企画本部長の滝本 俊明氏に、伴走したKPMG FASの古谷 公と佐伯 尚子が、ブランド刷新の舞台裏についてお話を伺いました。
本稿では、このプロジェクトを主導した同社取締役専務執行役員経営企画本部長の滝本 俊明氏に、ブランド刷新の舞台裏についてお話を伺いました。
従来、広告や販促プロモーションの延長として捉えられがちだったブランディングは、今や経営戦略と一体となり、将来ビジョンの実現に向けてその方向性を社内外のステークホルダーに示すものとして再認識されています。その背景には、事業価値を超えた「大義」や「意味」に社会の関心が向かい、企業が明確な価値観を体現することが求められるようになったことがあります。
こうしたなか、株式会社INPEXは新ビジョンと共にブランド指針を策定し、世界各拠点の従業員とともにアイデンティティーを再定義しました。本稿では、このプロジェクトを主導した同社取締役専務執行役員 経営企画本部長の滝本俊明氏に、伴走したKPMG FASの古谷 公と佐伯 尚子が、コーポレートブランディング策定の舞台裏についてお話を伺いました。
新ビジョンの策定とコーポレートブランディングを一体的に推進
古谷
INPEX は2025年2月に「INPEX Vision 2035」および「2025-2027中期経営計画」を発表されましたが、その策定段階からブランディングの策定も意識されていました。まず、ビジョン策定と同時にブランディングに力を入れられた背景を教えてください。

滝本 俊明 氏 株式会社INPEX 取締役専務執行役員 経営企画本部長 入社後、執行役員アメリカ・アフリカ事業本部長、常務執行役員上流事業開発本部長、取締役常務執行役員水素・CCUS 事業開発本部長、取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当、ネットゼロ事業統括などを経て、2025 年4月より、取締役専務執行役員 経営企画本部長、法務担当、コンプライアンス担当、低炭素事業統括を担当。 |
滝本氏
今回ブランディングの策定を行ったタイミングには明確な理由があります。2025 年2 月に、「INPEX Vision2035」という新しい長期ビジョンを発表し、新しいビジョンで10年後の会社の方向性を示すのであれば、それを社内外に強く印象付けるために、ブランディングも同時に策定する絶好の機会だと考えたためです。
さらに、ビジョンの実現に向けて、当社ホームページの刷新と、4月1日付で大規模な組織改編も実施することにしました。このように、当社としての大きな変革を一体的に進めるなかで、コーポレートブランディングも連動させ、会社全体の変化と成長へのコミットメントを社内外に強く示せると判断したのです。
従来使用していたキャッチコピーは広告代理店が広告用に作ったものでしたが、今回は当社の方向性や社員の想いを真に反映したブランドメッセージを作り上げたいと考えました。この重要な変革期に、INPEXの本質を表す長期的なブランディングを構築することが必要だったのです。
古谷
技術系のバックグラウンドをお持ちの滝本さんから見て、ブランディングとはどういうもので、なぜ経営にとって重要だとお考えですか。
滝本氏
本来、経営企画本部長は事務系の役員が担当することが多いのですが、私は技術系出身です。ただ、会社名やロゴ、最近で言えばパーパス(存在意義)といったものをきちんと定め、社員と共有することが、社内のエンゲージメントを高めるために必要だと以前から考えていました。
当社は2021年に「国際石油開発帝石」から「INPEX」へと社名変更しました。「名は体を表す」ように、社名は会社の戦略や目標に影響します。会社名やブランドステートメント、ブランドメッセージは、技術系・事務系といったバックグラウンドに関係なく社員にとって重要なものではないでしょうか。
また、当社は帝国石油と国際石油開発の合併会社ですが、ジャパン石油開発や旧石油公団出身者、最近ではキャリア採用者も増えており、さまざまな背景の社員がいるなかで、社内の一体感醸成のためにも統一したブランディングが必要でした。今回はビジョン策定というタイミングで、社内外へのアピールを兼ねたブランディングを策定し、企業価値向上と社員エンゲージメント醸成を狙いました。

古谷 公 KPMG FAS マネージングディレクター/ CBMA 統括リーダー 2015年にKPMG に参画。通算25年以上にわたり戦略系コンサルティングに従事し、消費財、流通、自動車関連、機械、化学、商社などの業界に対して、戦略策定、営業・マーケティング改革、ブランディング強化、プライシング/ ROI マーケティング実行、組織オペレーション改革、等に関する幅広いプロジェクトに携わる。 |
佐伯
今回、経営幹部自らが旗振り役を担われた理由はどこにあるのでしょうか?

佐伯 尚子 KPMG FAS シニアマネージャー 自動車会社のグローバルマーケティングを経て、大手広告代理店にてストラテジックプランナーとして国内外グローバル企業の事業戦略、ブランド戦略、マーケティング戦略の策定や商品開発に参画後、国内最大手化粧品会社の経営戦略にて新規事業開発を経験し、KPMG FAS に入社。 |
滝本氏
個人的にも、コーポレートブランドの統一、特にロゴは会社の看板として重要だと考えていました。ですので、海外事務所や子会社で異なるロゴを使用していたり、その使用にやや統一感を欠いていた部分については完全統一が必要だと感じていました。
海外のメジャー石油会社や国内のユーティリティー企業は、ブランディングを非常に重視しています。我々も経営の視点からブランディングに本格的に取り組む必要があると感じたことが大きな理由です。
グローバル拠点を巻き込んだワークショップを展開
古谷
今回のブランディング策定プロセスでは、オーストラリア、インドネシア、アブダビ、日本国内各地など、さまざまな拠点で社員の方に集まっていただき、インテンシブなワークショップを実施しました。INPEX にとって、何か新たな発見はありましたか?
滝本氏
日本では東京と新潟、海外では3ヵ国の事務所でワークショップを実施し、「INPEX とはどんな会社か」「何を大切にしている会社か」「これからどう変わっていくべきか」などについて議論しました。社員からは「会社のあり方について改めて考える良い機会になった」という声が多く聞かれ、大きな成果があったと思っています。ワークショップには長い時間をかけましたが、コーポレートブランディングやブランドステートメント策定の目的である「社員のエンゲージメント向上」という点でも、非常に効果がありました。
古谷
海外の事業会社や日本の各事業部にまたがっての想いの共有が進んだということでしょうか。
滝本氏
まさにそのとおりです。「INPEXVision2035」を発表するにあたり、10年後を見据えた時、社内の一体感醸成と社外の認知度向上のためには目標や想いの共有が必要で、そのためにはコーポレートブランディングの策定が不可欠だと考えました。BtoB 企業でもBtoC 企業のように、こうした取組みが求められる時代になっています。企業の成長には、社員を含むステークホルダーが1つの方向を向いて事業を進めることが重要であり、INPEX の次なる成長への基盤になると考えたのです。
古谷
合併会社の企業文化の複雑さによって、意思疎通や方向性の共有などの面で難しさを感じる場面もあったのではないでしょうか。
滝本氏
そうですね。2006年のホールディング会社設立、2008年の実質的な合併に伴う赤坂オフィスでの合同勤務開始から17年が経ちますが、当初は各社のカラーが強く出ていました。1つの方向を向くためには、コーポレートブランディング、特にビジョンやロゴ、ブランドステートメントの統一と共有が不可欠でした。
また、従来、一般消費者に対する認知活動は限定的でしたが、昨今、特に株主、社員、リクルート層、取引先、政府関係者や自治体など、それぞれに当社の事業や方向性を理解してもらう必要性が高まっています。社内の一体感醸成と、ステークホルダーへの業務理解促進は、企業の成長にとって重要となってきているのです。

「挑む」に込めた信念と覚悟
佐伯
最終的にブランドメッセージは「地球の力で未来へ挑む」に決まりました。ブランドメッセージ策定にあたってのこだわりについて教えていただけますか。
滝本氏
ブランドメッセージは親しみやすく、社員のモチベーションを高められるものが理想です。すべてを語らなくても企業の特色を表し、短くて覚えやすいものを目指しました。
「エネルギー」「石油」「天然ガス」といった具体的な言葉を使わずに、エネルギー会社であることが想像できる言葉を用い、すべてを語らないからこそ、その先を想像させるブランドメッセージが良いと考えていました。そうしたことを踏まえて、広報グループがKPMGと協力しながら、社内の意見も取り入れて「地球の力で未来へ挑む」(英語のブランドメッセージは「Energy for a brighter future」)というブランドメッセージとブランドステートメントを策定しました。個人的には「未来へ何をするのか」と想像力をかき立て、短くて覚えやすいという利点がありましたので「地球の力で未来へ」で止めたかったのです。
しかし、ワークショップで抽出された「INPEXらしさ」のなかに「追求心」や「耐久心」、「挑戦と解決を目指す風土」などがあり、「挑む」という動詞を入れようと提案があり、決定しました。社内の人間が会社のことを最もよく知っているるという信念のもと、策定過程で多くの社員の意見を取り込み、納得のいくものができたと思っています。
佐伯
ワークショップでは、INPEX は地球規模の課題にかかわり、インフラを支える使命があるゆえ、もっとチャレンジしていきたいという社員の方々の声が聞こえてきました。また、INPEXの事業の特徴として、地球が対象という規模の大きさ、原油価格などコントロールできない要素に業績が左右される点、そして1人ではなくチームでの取組みが必須である点などがあげられました。そこでKPMGでは一人ひとりが能力を発揮するには「挑戦心」がキーになると考え、タグラインのキーワードの1つとして「挑む」を提案させていただきました。
滝本氏
当社の事業は、何年もかけて調査・物理探査を行い、検討を経て100億、200億円をかけて井戸を掘っても、何も出ないことがあります。たとえば建設会社の場合、橋を作ったけれど失敗して200億円損失というのは考えにくい話ですが、われわれの事業ではあり得ることです。大きな成果があれば10倍、100倍の喜びがありますが、外れた時の落胆も大きい。3~4年の検討期間、投資、多くの社員の労力、厳しい契約交渉など、すべてが水泡に帰すこともあります。こうした業界特性を踏まえ、「挑む」という言葉には良い面も厳しい面も含めた挑戦心が込められていると思っています。
古谷
「挑む」には特別な想いが込められているのですね。
滝本氏
はい、「挑む」には、エネルギー業界特有のリスクと挑戦が集約されています。当社の事業は大きな投資を伴い、チームで取り組むプロジェクトが中心です。地下3,000mから5,000mという人間の知を超えた深さに挑戦しても空振りの時もあります。そうした厳しい現実のなかでの「挑戦」は重要な要素です。加えて、探究心や好奇心も欠かせません。エネルギーは人間の生活に永続的に必要なものであり、それを支える使命感も込められています。また、エネルギーの安定供給を最大のミッションとしながらも、脱炭素化や新技術開発、地域貢献などにもチャレンジしていくという想いも込めています。
古谷
「地球の力で」という発想はユニークですね。普通なら「人間の力で地球を何とかしよう」という環境問題的な発想になりがちですが、ワークショップを通じて違う視点から言葉が生まれました。
滝本氏
そのとおりです。当社のフィールドは地球であり、地球の力をお借りして地下から資源を取り出して供給するという点を強調したかったのです。当社の社員たちは、まさに地球を相手に仕事をしています。最初は「ミッション:地球」という案もありましたが、さまざまな議論やワークショップを通じて現在の形に落ち着きました。また、当社は現場を大切にする会社です。最先端のIT も活用しますが、どちらかというと「職人技」的な側面が強い。そうしたさまざまな要素を凝縮したのが「地球の力で未来へ挑む」というブランドメッセージです。「未来へ」か「未来に」かという助詞の選択も議論になりましたが、能動的に未来に向かうという想いを込めて「へ」を選びました。デザイン面でもINPEX のロゴと同じ地球の傾き23度を表現したり、エネルギーや向上心、安全を象徴するオレンジ色をワンポイントで入れたりなど、細部にもこだわりました。こうした工夫も社員のエンゲージメント向上に貢献すると考えています。
古谷
ブランドステートメントの策定でも、ブランドメッセージと同様に細かなこだわりがあったのでしょうか。特に印象に残っている部分があれば教えてください。
滝本氏
個人的に気に入っているのは、ブランドステートメントの「私たちはエネルギーを探し、届け続ける。今日も明日もこれからも、ずっと」という部分です。当社は単にエネルギーを売るだけでなく、探鉱から始める点が他のエネルギー企業と異なります。探鉱には多大な苦労があり、何百億円使っても成功しないリスクもありますが、それに懸命に取り組んでいます。
また、探して生産するだけでなく、必要とする人々に継続的に届けることも重要です。「今日も明日もこれからも、ずっと」には、永続的にエネルギーセキュリティーに責任を持つという決意を込めています。ステートメントは読点や句点の位置、ビジョンとの整合性、ワークショップから抽出したキーワードのちりばめ方など、細部まで工夫し、さまざまなこだわりをもって作成しました。
「INPEX Vision2035」の目標を達成するために
佐伯
最近のブランド活動は言葉だけでなく、実際の企業活動を伴う「言行一致」が求められる傾向にあります。INPEXは新ブランド指針に合わせて組織も変革されましたが、このことは社内への強いメッセージになったと思います。組織改革とブランディングの関係について教えてください。
滝本氏
経営企画本部として2024~2025年の最大ミッションは、「INPEX Vision 2035」および「2025-2027中期経営計画」の策定と社内外への浸透でした。ビジョンを新たに作成し、投資家などステークホルダーに訴求するには、「変化」を感じてもらうことが重要です。このビジョンの目標を実現していくことが重要なことで、コーポレートブランディング策定、ホームページ刷新、組織改編はその一環です。
10年後のINPEX に向けた本気度を社員にも認識してもらい、社外からも成長投資への真剣な取組みを見て取れるメッセージにしたかったため、その1つとしてコーポレートブランディングが役立つと考えました。
最近制作をした動画広告でも、最後に「地球の力で未来へ挑むINPEX」というメッセージを発信しています。従来の広告よりもカジュアルな雰囲気で、社名認知と、事業理解に焦点を当てた構成にしました。ブランディングとコミュニケーション戦略を連動させることで、変革への一貫したメッセージを発信できたと思います。
古谷
社内へのブランド浸透策については社風も考慮する必要があると思いますが、INPEXの社風はトップダウンとボトムアップ、どちらが強いですか?
滝本氏
難しい質問ですね。以前はトップダウン的な「これをやれ」「この成果を出せ」という指示が多かったと思いますが、規模拡大に伴い、トップが直接指示できる範囲も限定的になってきました。トップの決定も必要ですが、草の根から湧き上がる提案や要望も大切です。たとえば、石油・天然ガス探鉱を継続したいという声もあれば、水素事業に挑戦したいという社員もいます。こうしたボトムアップの提案も尊重していきたいと考えています。
古谷
戦略や方向性を作っても現場が動かないために機能しないことはありがちですよね。今回のブランドメッセージも現場にしっかり浸透させることで企業風土が変わっていくと考えますが、その点で意識的に取り組んでいらっしゃることはありますか?
滝本氏
一番重視するのは「INPEX Vision2035」の実現です。取締役会でも議論しましたが、ビジョンを作ることが目的ではなく、それを実行して2035年の目標を達成することが目的です。たとえば「60- 60」(事業規模60% 拡大・GHG 排出原単位60%削減)といった目標を達成していかなければなりません。
そこで今年に入って国内拠点を回り、目標を共有し、10年後のあるべき姿に向けて次の3年間で何をすべきかという「バックキャスト型」の目標を説明しています。同時に「こんな想いでブランディングを作りました」とメッセージを伝え、ビジョンとブランディングが一貫して伝わるよう努めています。
地域の意識差を乗り越え、エネ ルギー企業としての責任を表明
古谷
ワークショップでは地域によって異なる見方も出てきましたね。
滝本氏
そうですね。地域によって状況は全く異なりますので、一体感やエンゲージメント向上につながるブランドメッセージを作り、会社の方向性を凝縮するのは非常に難しい作業でした。
中東では油田・ガス田が当たる確率は高いものの、地政学的なリスクに加えて、商業化後の税率も高い。日本はカントリーリスクが低く比較的自由に事業展開できますが、国土が狭く資源ポテンシャルも低い。それでも日本でのガスや石油の発見はニュースになり認知度向上にも貢献するので、国内での挑戦にも大きな意義があります。
佐伯
地域によって従業員の方々の意識も異なっていると実感しました。アブダビではオイル&ガスカンパニーであることに誇りを持つ一方、オーストラリアでは環境意識の高まりから「自分たちはオイル&ガスカンパニーではない」という声もありました。振り返ってみると、グローバル展開されているINPEXを1つのタグラインに集約すること自体が、難しい挑戦でした。
滝本氏
そうした多様性のなかで、共通の方向性を示すことが重要ですね。今回のビジョンでは「責任あるエネルギートランジションの実現」というサブタイトルを掲げていますが、これには深い意味があります。
4~5年前は脱炭素化が最優先され、再生可能エネルギーは善、石油・天然ガスは悪者という極端な見方が主流でした。しかし、ウクライナ侵攻後はエネルギー安定供給の重要性が再認識されています。「責任ある」と強調するのは、石油・天然ガスから水素へ、ガソリン車から電気自動車への移行は一夜にして実現できないからです。気候変動対策と温室効果ガス削減のために、現実的なアプローチが必要です。
たとえば石炭火力発電の燃料を天然ガスに替えるだけでもGHG 排出量を45% 削減できます。これは現行システムで実行可能ですが、100%水素燃料への切り替えは短期的には難しいと考えます。こうしたエネルギー転換には20~30年かかるかもしれませんが、その間にも気候変動は進行します。できることから責任をもって取り組む姿勢を、今回のビジョンとブランドメッセージに込めています。
佐伯
「言行一致」が重要になっていますね。「責任ある」というキーワードが象徴するように、実現可能なことを約束し、できないことは言わない姿勢が求められます。欧米企業のなかには達成困難な目標を掲げ、未達でも「仕方ない」で終わらせるケースもあります。経営とブランドメッセージの一貫性については、どうお考えですか?
滝本氏
今回のビジョンでは、「60-60」やCCS(二酸化炭素回収・貯留技術)、ブルー水素による脱炭素貢献、電力関連分野への事業拡大を掲げています。これは2035年以降は石油・天然ガスだけでは十分でないという認識からです。
これらの約束が達成できなかった時には「申し訳ありません」では済まされないと考えています。エネルギー事業環境は変動し、米国のトランプ政権もエネルギー環境に影響する可能性がありますが、そうした変化を踏まえたうえで、チャレンジングでありながら手が届く範囲の目標を設定しています。
企業の信頼性は重要です。たとえば株主総会で約束した累進配当を下げることは、信頼性を損なう可能性があります。ビジョンについても達成可能な目標を掲げ、全力を尽くす。そのためにブランドメッセージを通じて、ステークホルダーの理解を促進することが大切だと考えています。
ブランドを浸透させ、 想いを込めた取組みを推進する
佐伯
ブランディングの主なターゲットをどのようにお考えですか。多くの企業ではCMや外部発信が中心になりがちですが。
滝本氏
メインターゲットは投資家の皆さまですが、取引先を含むステークホルダーの皆さま、個人的には社員や役員の一体感醸成、ブランド認知度向上も重視しています。社外発信も重要ですが、社内のエンゲージメントやモチベーション向上につながることが理想です。
古谷
BtoB企業のなかではテレビCMも積極的に活用されていますね。外部発信が内部の帰属意識を高める効果もあると思われますか?
滝本氏
はい、BtoB 企業は一般消費者の目に触れる機会が少なく、認知度の向上は課題です。広告出稿は特に採用面での効果が大きいと考えています。今の新卒学生は多くの企業に応募し、複数の内定を得ますが、最終選考で「親確(親に確認)」する際、BtoC で名前が通った企業が選ばれやすい傾向があるとも聞いています。
優秀な人材確保のためにも、親世代やリクルート層への認知度向上は重要で、ブランドメッセージや広告はそれに貢献すると考えます。最近は他のBtoB 企業もCMを行うようになり、ブランディングの重要性は共通認識になってきています。
佐伯
ブランド浸透のための活動は、今後はどのように進められる予定ですか?
滝本氏
「地球の力で未来へ挑む」というブランドメッセージはすべてを語っていない表現です。これを社内はもちろん社外の関係先にも浸透させ、込めた想いを理解してもらう取組みを進めます。社外的には、今年2月に新聞広告でお披露目し、社内に対しては国内拠点を巡回してビジョンの説明とともにブランディングの想いも伝えています。半年をかけて作り上げたブランドメッセージとブランドステートメントは、社員やステークホルダーにも内容を深く理解してほしいと思っています。
今後は広告や株主総会、個人株主向け説明会などでも積極的に使用し、ステークホルダーや取引先に広く認知されることを目指しています。
古谷
ブランドメッセージの社内浸透はいかがですか。
滝本氏
現場の反応はさまざまですが、おおむね好意的ですね。ビジョン全体についての理解は得られていますし、ブランドメッセージやコーポレートブランディングについても、社外役員からは「見ているうちに良さが分かってきた」という評価もいただいています。会社の目指す方向を的確に表現しているという評価も多いです。
古谷
そうした一貫性を実現できたのは、経営企画本部長でありコーポレートブランディングに熱い想いを持つ滝本さんが旗振り役を担われたからこそだと思います。ブランディング策定の要所要所で関わっていただいたことが、成功の大きな鍵だったと思います。
滝本氏
そう言っていただけるとうれしいですね。多くの社員の協力を得、半年以上かけて作り上げた成果ですから、今後も大切にしていきたいと思います。ビジョン策定を機に、コーポレートブランディング、ブランドメッセージ策定、組織改編を同時に進められたのは非常に良かったと思います。これからも、ブランドメッセージやブランドステートメントに込めた想いを、社内外に広く伝えていきたいと考えています。