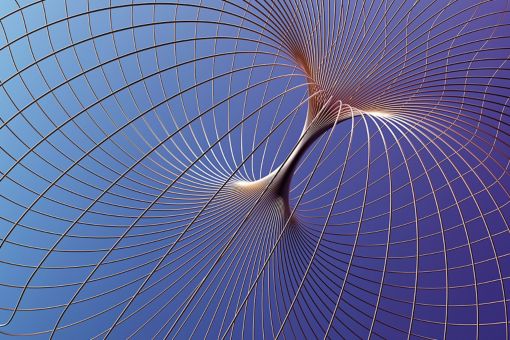慶應義塾大学寄附講座、ディープテック・スタートアップ動向
有限責任 あずさ監査法人インキュベーション部の阿部 博が慶應義塾大学生向けに講義をしました。本稿では、講義内容のエッセンスをお届けします。
有限責任 あずさ監査法人インキュベーション部の阿部 博が慶應義塾大学生向けに講義をしました。本稿では、講義内容のエッセンスをお届けします。
KPMGジャパンでは、最新のテクノロジーの動向からアカウンティングやファイナンス、関連法規など、“起業”に必要な知識を体系的に学ぶ寄附講座「スタートアップとビジネスイノベーション」を慶應義塾大学経済学部に提供しています。そのなかの1つとして、「ディープテック・スタートアップ動向」をテーマに、有限責任 あずさ監査法人インキュベーション部の阿部 博が慶應義塾大学生向けに講義をしました。本稿では、講義内容のエッセンスをお届けします。
Ⅰ.スタートアップの世界動向と日本の現状と課題
「スタートアップ」という言葉をニュースなどでよく聞くようになりました。なぜスタートアップが昨今日本で注目されているのか、それはスタートアップが経済成長のドライバーで雇用を創出するのも大きな役割を果たし、新たな社会課題を解決する主体としても重要だからです。今回は、スタートアップ特にディープテック領域について講義をしました。
1.日本を取り巻くスタートアップ市場
KPMGでは各国・地域で勝ち抜いたスタートアップ企業を世界中から集め、ポルトガルのリスボンでピッチコンテスト「KPMG Global Tech Innovator Competition」を開催しています。2024年で11回目の開催となりましたが、初めてアジア、しかも日本から出場した企業が優勝しました。これは非常に画期的なことで、日本のディープテックのレベルが非常に高いことを、多くの人が実感していますし、実際に私もそう感じていますし、日本にはもともと高い技術力があり、医学やヘルステック分野でも強みを持っています。それにもかかわらず、なぜ日本では同様の成功例が生まれにくいのか。ここに、現在の日本が抱える大きな課題があると感じています。

KPMG Global Tech Innovator Competition in Japan 2024
日本を取り巻くスタートアップ市場について説明します。日本のスタートアップ数は約2万5000社に(「スタートアップ政策について」 出典:経済産業省)達しており、数としては大きな成長を見せています。IPO市場では、グロース、スタンダード、プライムを合わせた上場件数も増えています。大学発スタートアップも活発で、毎年5〜6社、多い年には8社がIPOを果たしており、これも国を挙げたスタートアップ支援政策の成果だと思います。宇宙分野やAI技術など、時価総額の大きなスタートアップも出てきています。ただし、日本ではグロース市場において比較的小規模な段階で上場するケースが多く、5年後には時価総額100億円を超える規模に育てることが求められています。
2.スタートアップにおけるIPOとM&A
次に、M&Aの増加と資金循環についても見ていきましょう。日本ではこれまでIPOがスタートアップの主な出口戦略でしたが、近年はM&A(企業買収)も増加しています。その例として、ある化粧品素材メーカーが10年越しにM&Aにより成長したり、大学発ベンチャーが米国企業にスピーディーに買収されたケースもあります。米国のM&Aは、デュー・デリジェンスも迅速で、すぐに買収に至るケースが多いですが、日本では半年〜1年かかるのが一般的です。しかし今後は、資金循環を早めるためにも、M&Aがもっと普及していく必要があると考えています。では、IPOとM&Aの違いと意義とはなんなのでしょうか。IPOの特徴としては、会社として独立し、産業を牽引できる素晴らしい成果と言われていますし、IPOが最初の目標と言われる起業家もいます。ただし、資金の循環が遅くなりやすく、経営者が長期にわたり同じ会社に留まる傾向にあります。M&Aの特徴として、買収後、1〜2年の拘束期間を経たのち、起業家が新たなスタートアップを立ち上げることがあります。資金循環が速く、人材やノウハウが社会に再分配されるというメリットがあります。このため、今後の日本ではM&Aの活用が、スタートアップエコシステムを活性化させる重要な鍵になると考えています。
最近は、何社もスタートアップを創業する起業家が増えてきており、それゆえ人材が循環し、同時に資金も循環するようになっています。たとえばIPOの場合、上場に向けた準備だけでも5年近くかかるケースが一般的です。なかには、上場まで60年かかると言われるくらいでした。しかし、M&Aであれば、海外では1ヵ月程度で買収が決まることもあり、資金循環が非常に速いです。こうした特徴から、今後日本でもM&Aがますます増えていくだろうと予想しています。

あずさ監査法人 阿部 博
Ⅱ.日本の概況とディープテック領域に注目が集まる理由
阿部:
私が大学を卒業した1990年頃、世界の企業ランキングの上位は銀行が占めていました。大蔵省(現在の財務省)が中心となって金融機関を守っていた時代です。また、当時海外の方は、京セラ、村田製作所といった日本企業の技術力を高く評価し、「日本はイノベーションが自然発生する国だ」とさえ思われていました。しかし、現在は大きく様変わりしています。
直近のランキングでは、ほとんどの上位企業は米国などが占めています。この30年間で、国力が急速に低下した現実を強く感じます。これに歯止めをかけなければ、若く優秀な人材の活躍の場がますます減少してしまいます。そういったなかで、ディープテック・スタートアップに注目が集まっています。ディープテック・スタートアップとは、特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術で、その事業化・社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社会課題の解決など社会にインパクトを与えられるような潜在力のある技術を有するスタートアップを指しています。いま注目されるディープテック分野としては、AI、量子コンピュータ、エネルギー、ヘルステック、宇宙・ロボティクスが挙げられます。
こういった分野にて、日本発ディープテック・スタートアップの一部をご紹介します。
- Heartseed株式会社
iPS細胞由来の再生心筋により心不全感謝の治療を目指す。 - リージョナルフィッシュ株式会社
ゲノム編集技術で水産物を品種改良。 - Blue Laser Fusion,inc
高出力で連続照射できるレーザー技術を米国で研究中。
このような企業がありますが、日本において実はスタートアップを支える「人材」が圧倒的に不足しています。日本では、スタートアップに挑戦する人材がまだ少ないのが現状です。これまで優秀な人材は大企業に進むケースが多かったため、スタートアップには人材が集まりにくいという課題があります。これを何とか改善しなければなりません。この点については、慶應義塾大学でも人材育成に取り組んでいるようです。たとえば、大学のEIR(Entrepreneur in Residence)制度の活用や、事業会社から人材をスタートアップに送り込む取り組みも進んでいます。とはいえ、人材育成には時間がかかります。もっと多くの人にスタートアップへの関心を持ってもらい、何度も起業や挑戦を経験する人材を増やす必要があると考えています。
これらを意識して、社会全体でスタートアップエコシステムを育てていく必要があります。
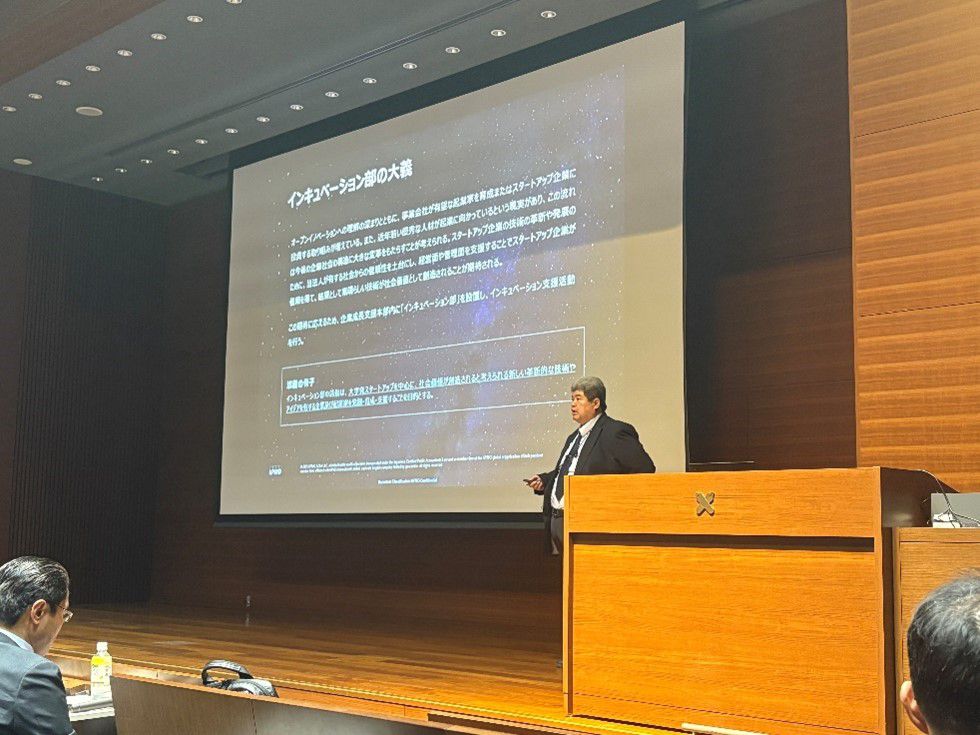
あずさ監査法人 阿部 博
Ⅲ.最後に若い世代へのメッセージ
慶應義塾大学の学生・卒業生は非常に優秀で、スタートアップに飛び込む人も増えています。ただ、一度大企業で経験を積み、その後スタートアップに挑戦するケースが多いのが実態です。
たとえば、ある起業家(30代)は、「スタートアップを始めるのに早すぎるとか遅すぎるとかはない。思い立った時が適齢」と話していました。また、60歳を超えてスタートアップを立ち上げた方もいますが、できれば若いうちに挑戦するほうがいい、という意見もありました。
皆さんには、今はまだ直接スタートアップに飛び込まなくても、頭の片隅にスタートアップへの関心を置いておいてほしいと思います。チャンスが来たときに躊躇せず飛び込めるよう、日々好奇心を持ち続けてください。私たちも、慶應出身のスタートアップ起業家たちを引き続き応援していきます。