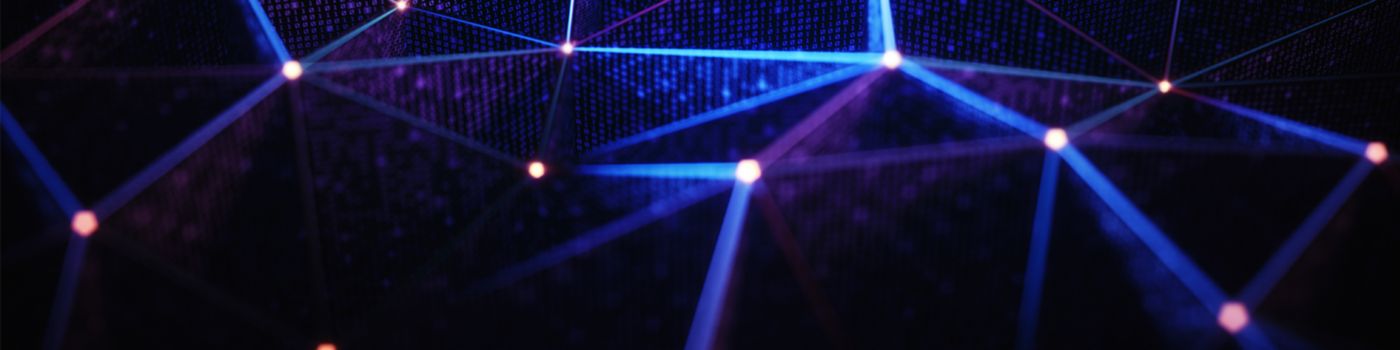日本社会は今、労働人口の減少による産業力低下の危機に直面し、あらゆる場面でDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、テクノロジーの力で課題を解消する必要に迫られています。そうした中で、コロナ禍は、DXを後押しする大きな力になっている、との見方もあります。
実際に、リモートワークやオンライン会議など、テクノロジーを用いる場面は“珍しいこと”ではなくなりました。しかし、こうした業務風景は未だ「以前のやり方を忘れるほど自然なこととして受け入れられてはいない」との指摘も少なくありません。
では、デジタルやテクノロジーは今後、どのようにして社会に“慣れ親しんだ”存在になっていくのでしょうか? 本稿では、KPMG Ignition Tokyoの茶谷公之が、東京大学大学院工学系研究科 森川博之教授と対談した内容をお伝えします。
テクノロジーがどう普及するかは過去の出来事が教えてくれる

(株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(左)、東京大学大学院工学系研究科教授 森川博之氏(右))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。
茶谷: こうしてお話ししていると、時間はかかるもののテクノロジーは社会生活に取り込まれていくものだ、と改めて気付かされます。
森川: そういう点で言うと、5Gもそうなるのでしょう。
もうすでに忘れてしまっているかもしれませんが、10年前を振り返ってみると、4Gが出てきた頃、エンジニア達は「4Gという新しい周波数帯は難しくて使えない」と言っていました。しかし、今はご承知の通りですよね。頭の中では、「パイプが太くなれば、動画広告もできる」と分かってはいましたが、「貴重な帯域を広告のために使うなんてもったいないこと、あり得ない!」という声もあったものです。
このように、時間が経つにつれて感覚はものすごく大きく変わりますし、「無理だ」ということはだいたい解決できるのだ、と思います。このようなことに注意しつつ、昔どんなことを考えていたのか、振り返ってみると面白いかもしれません。
茶谷: iPhoneもそうですね。2007年に登場しましたが、今ではiPhone前の生活が思い出せないほどです。
森川: おっしゃる通りです。だからこそ、それを振り返ってみると結構面白いのですよ。
先日、ポケットベルを思い出してみましたが、当時の高校生は休憩時間に公衆電話までダッシュしてメッセージを打っていましたよね。今では公衆電話を見つけることすら難しくなっています。
「基準」や「当たり前」は実は様々に変化していて、変化後には何が「基準」や「当たり前」だったか、分からなくなることが往々にしてあります。これは非常に興味深いことですし、いろんな方々がいろんな事を考えるような場を作る必要があります。
茶谷: 「基準」や「当たり前」の先を見ることができたら、そこにチャンスがあるかもしれませんしね。
森川: その象徴的な話として、「洗濯機の自由」というのがあります。
洗濯機の登場は、洗濯という家事の負担を減らし、社会に大きな影響を与えました。しかし、実は、洗濯機が社会に与えた影響はそれだけではありません。洗濯機がきっかけで、衣類の市場も拡大したと言われているのです。これはつまり、洗濯機を使うことによって衛生管理が徹底され、我々はみんな綺麗好きになって毎日服を洗濯するようになり、衣類の買い替えサイクルが早くなったので、その市場が一気に拡大した、ということです。
言われてみれば「なるほど!」と思えるのですが、言われるまでなかなか気付けないものです。洗濯機が発売されたのと同時に、「これからみんなが綺麗好きになるから衣類市場はチャンスだ!」なんて言った人はきっといないはずです。
茶谷: 今はリモートワークが導入されて、ズボンやスーツが売れなくなったとのことです。画面の上だけキチンとしていればいいから、上半身の服だけですむ、と。
森川: そうですよね。では、この先どんな市場が生まれていくのか? 将来は分からないし、「言われてみれば当たり前のこと」というものは実は私達は気付かないことの方が多いのでしょう。それは、悩ましくもあり面白いことだとも思います。
日本の凄さはどこにある?
茶谷: 変化の真っ只中にいるわけですが、森川先生が今一番興味を持たれているテーマやトピックは何でしょうか?
森川: まず、日本の産業がやはり元気になってほしいですね。10年先、20年先の日本が元気になるためには何をしていけばいいのか、考えていきたいテーマです。
茶谷: 何をやればいいと思われますか?
森川: 具体的な戦略というよりも、それに先立って、従来の固定概念や既成概念は取り払っていく、とにかく様々なことをやっていきながら「何がうまくいくのか」と探り試していくことが重要なのだと思います。
テクノロジーの分野でいうと、やっぱり研究開発と知財標準化と事業開発がキーになるでしょう。ここをしっかりと横通しさせないといけません。現状はまだバラバラである、という感じがあります。そう言えば、この領域はソニーではしっかりとされているのではないでしょうか?

茶谷: 今のソニーは1兆円くらいの利益を出していますが、利益が出ている源泉はプレイステーションとCMOSイメージセンサーと、ファイナンスです。もう25年以上前に作ったビジネスがようやく収穫期に来た、というイメージですね。
森川: 25年前に作り始めた時、研究開発と知財標準化についてどのように捉えていたのか、気になります。
茶谷: 知財については、昔からその重要性を非常に強く認識していたと考えます。もともとソニーがトランジスタラジオを作っていた頃、トランジスタに関する特許料の支払いがラジオの売り上げ比のかなりを占めていたこともあり、トランジスタの特許を買い取った、という歴史があります。
当時はまだトランジスタ技術を民生品に使うという概念はなかったらしいのですが、ソニーとしては「トランジスタは重要だ」と判断したのでしょう。特許を売却した相手もトランジスタを民生品に使うとは思っていなかったらしく、「買いたいなら売るよ」というスタンスだったと伝わっています。
このような経験から、「特許は自分達の成功ストーリーの一要因だ」と感じているのでしょう。だからこそソニーは知財を非常に重要視していますし、紛争も当然あったはずです。
知財に関する紛争という意味では、家庭向けビデオテープレコーダー「βマックス」が米国で訴えられた件が特徴的ですね。「TV番組を録画するのは著作権に抵触する、著作者の権利の侵害にあたる」ということで、米国で裁判になった事例です。
この時、当時のソニー法務部の総力と有力な弁護士の力をもって最終的には勝訴したのですが、その力の原動力には、「生活者、とりわけソニー製品を使ってくれるファンにとって有意義なことである」という信念があったのでしょう。
ちなみに、米国ニューヨーク証券取引所に日本企業が上場したのもソニーが初です(1970年)。グローバルに名前を知られるためのアクションだったと言えるでしょう。そうやって、前例や慣習にとらわれずに自分たちが正しいと思っていることをやっていく、というのがソニーのDNAでしょうし、そういうDNAは強いと思います。
森川: そうですね。日本企業は、「技術で勝って、ビジネスで負ける」と言われてきましたが、最近ではその技術も弱くなってきている、との見方も出てきています。これをどうしたらいいのか、考えていかなければならないでしょう。
ただ、何だかんだと言っても、日本はすごい部分もあります。
例えば、地方の県内総生産を見てみると、最も低い鳥取県でも天然資源に恵まれたブルネイと同等のレベルです。これだけでもものすごい経済規模だ、ということが分かるでしょう。市区町村でも同じで、岩手県の大槌町も南太平洋のトンガ王国のGDPと同程度です。こうして見ると、日本は今でもものすごい経済規模を誇っており、捨てたものではありません。
一方で、やはり人口減少は問題です。特に労働力人口が減っているため、一人当たりの生産性を上げざるを得ない、ということになります。ですから、デジタルやテクノロジーの力で生産性を維持向上させることができれば我々は幸せになるのではないか、そんなことができたらいい、と思っています。
イノベーションは“気味が悪い”から始まる

茶谷: 様々な切り口からデジタルやテクノロジーが社会にどう浸透し、受け入れられていくのかについて話してきました。
最後に、これからの社会がどう変わっていくのか? この先30年後、50年後の社会でテクノロジーはどう活用されるのか? その時に活用されるイノベーションはどう生み出されていくのか? といったテーマで話していきたいと思います。
森川: キーワードを挙げるなら、「Just in timeからJust in caseへ」あるいは「冗長性」でしょうか。もしものために誰と誰がどう繋がっているのか、すべてデータとして把握しておくことは非常に重要で、将来的にはデジタルツインも活用されていくのでしょう。
そうした情報を元にデジタルツインの中でシミュレーションをしてからリアルで行なう、という世界がやってくるかもしれません。様々なものが繋がる社会になっていることを踏まえても、方向としてはそれがメインシナリオになるでしょう。
茶谷: 確かにそうした社会になっていくのかもしれませんが、「そのような社会は面白いのか?」という声も聞かれますね。
森川: そうした視点はとても大切ですね。茶谷さんはどう思われますか?
茶谷: 私は面白いかな、と思っています。実はすでに自分のデジタルツインを作っているんですよ。
これはカメラ150台くらいで自分をキャプチャーして、声も自分の声をサンプリングしてシンセサイザーにしてもらって喋っています。日本語版と英語版があり、英語は本人よりも上手いかもしれません。(笑)
ゴールは私の代わりにこのデジタルツインが仕事をしてくれる、という状態です。もちろん、まだそこまでになるには時間がかかるでしょうが、枠組みだけはでき、次は頭脳を作れば…と思っています。面白くなっていくかどうか自体も楽しみです。
森川: すごいですね!そんな突拍子もないことをやっているんですね!(笑)
成功するイノベーションというものは、始めた時には7〜8割くらいの人が「こんなのはいらないよ」と言うようなものだと思います。10人が10人とも「欲しい!」と言うようなものはイノベーションでも何でもないでしょう。むしろ1人か2人が、「あってもいいんじゃない」と言ってくれるようなものが実は“良いもの”になっていくのかもしれません。
そういうイノベーションの“芽”みたいなものは世の中にたくさんあるけれど、ほとんどがなくなっていくものでもあります。茶谷さんのデジタルツインも10年後に当たり前な存在になるかもしれませんし、やっぱ駄目だったとなるかもしれません。
一般的には、茶谷さんのデジタルツインはまだ「不気味」という反応になるかと思いますが、その「気味が悪い」という反応がポイントかも知れないと感じています。
イノベーターはマリーン(海兵隊)のようなもの
茶谷: イノベーションが「イノベーティブなものだったんだ!」と理解されるには時間がかかるものです。それでもイノベーションが生まれるのを後押しするために、社会として何が必要なのでしょうか?
森川: 私達はどうすればいいのかというと、「絶対にこれがいいです! 素晴らしいものなのです!」という強い想いを持った人を応援することに尽きます。強い想いを持った人が100人いるなら、彼らを全力で応援する、というわけです。
しかし、おそらく80人ぐらいが道半ばで力尽きるとも想像します。それでも10人が残るかもしれない、と。それがエコシステムというものなのだと考えています。
茶谷: そうした挑戦を許す風潮も不可欠ですね。
森川: 私は、イノベーターはマリーン(海兵隊員)のようなものだと常々言ってきました。マリーンという言葉を選んだ理由には2つの意味があります。

まず一つ目の理由は、マリーンの機能的な側面からきています。マリーン達は陸海空軍の機能がコンパクトにまとまっているため、最初に敵陣に向かっていきますよね。非常にフットワーク軽く進み、失敗したらすぐに撤退もしますし、上手くいったらもちろん本体の部隊が出ていくことになります。「初めにやる」という意味では、マリーンとイノベーターは同じだと言えるでしょう。
2つ目の理由でありマリーンのすごいところは、“死亡率”や“作戦失敗率”が圧倒的に高い点です。最初に出陣するのでそれは当然のことですし、それでも向かっていくことのすごさを認めなければいけません。
イノベーターにしてもそうですが、誰もが「無理だ」と言ったとしても、その存在価値を認めて「頑張っていけ!」と力強く後押しすることが重要です。
対談者プロフィール

森川 博之
東京大学大学院工学系研究科教授
1987年東京大学工学部電子工学科卒業。1992年同大学院博士課程修了。博士(工学)。
2006年東京大学大学院教授。2002~2007年NICTモバイルネットワークグループリーダ兼務。
モノのインターネット/M2M/ビッグデータ、センサネットワーク、無線通信システム、情報社会デザインなどの研究に従事。電子情報通信学会論文賞(3回)、情報処理学会論文賞、情報通信学会論文賞、ドコモモバイルサイエンス賞、総務大臣表彰、志田林三郎賞、情報通信功績賞、大川出版賞など受賞。OECDデジタル経済政策委員会(CDEP)副議長、Beyond 5G新経営戦略センター長、新世代IoT/M2Mコンソーシアム会長、5G利活用型社会デザイン推進コンソーシアム座長、スマートレジリエンスネットワーク代表幹事、情報社会
デザイン協会代表幹事、総務省情報通信審議会部会長等。著書に「データ・ドリブン・エコノミー(ダイヤモンド社)」「5G 次世代移動通信規格の可能性(岩波新書)」など。
KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。