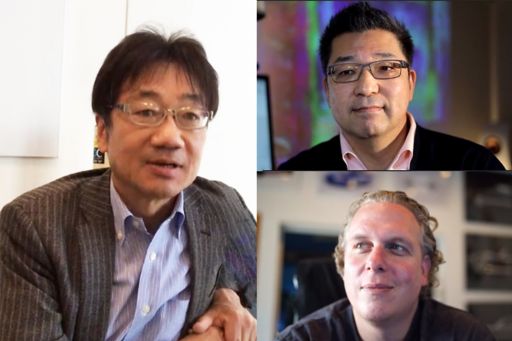企業にとって既存ビジネスを維持しつつ、社会の流れを見極めながら新たな挑戦をしていくことは容易ではありません。特に、既存ビジネスが“うまくいっている状態”であればなおさらです。自社のビジネスの本質を追求し、会社のあり方そのものを刷新するにはどのような思考や要素が必要でしょうか?
この課題について、KPMG Ignition Tokyoの茶谷公之が、寺田倉庫株式会社 代表取締役社長CEO 寺田 航平氏と対談した内容をお伝えします。
寺田倉庫がニッチトップな事業に転換するまで

(寺田倉庫株式会社 代表取締役社長CEO 寺田航平氏(左)、株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(左))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。
茶谷 :東品川の臨海部で倉庫業を展開されている寺田倉庫と、私の前職であるソニーとは、海外向けの部品管理や物流拠点として強いつながりがありました。ですが、今や寺田倉庫はいわゆる倉庫業とは思えないほど幅広いビジネスを展開されています。
例えば1本から預かってもらえるワインの保管サービスや個人所蔵のアートの保管、ミュージアム、カフェといった他業種への挑戦は非常に注目されています。そうした最近の動きを見ていると、言語で表しにくいものを積極的に扱おうとしている、という印象を受けます。そうした動きのきっかけは何だったのでしょうか?
寺田 :私は寺田倉庫の3代目になります。創業から最初の30年くらいは、いわゆる物流を中心とした倉庫業を営んでいました。しかし、昭和30年代の終わりから40年代の頭にかけて、徐々に街の姿形が進化し、物流もどんどん量が増える中で、やはり系列の強さといった規模の経済の側面が色濃くなっていきました。
その時にはすでに2代目である父に代替わりしていたのですが、変化を見極め、「大規模な物流というところに大きく攻めていくのではなく、違うビジネスモデルで進化を遂げたい」と考え、リテール領域に踏み込んでいこう、という流れになっていきました。ちょうどトランクルームが出始めてきた頃のことです。
一般的に、トランクルームとは、個人の家財道具を片付けるための部屋というイメージがあるかもしれませんが、倉庫業の立場からすると少し定義が異なります。商品を扱うのが倉庫業務で、いわゆる非製品を扱う場合はトランクルーム、といった区分けです。その中でもBtoB事業として、文書を預かったり、テレビ業界が残してきた映像系のフィルムを預かったり、というビジネスにシフトしていったのが父の時代からでした。
お預かりするモノの一点一点は極めて小さいのですが、それが集合体として積み重なると非常に大きくなります。今ではそのようなモノを扱う業界において、寺田倉庫が主要シェアの半数以上を占めるようになりました。ただ、このようなニッチトップを目指すビジネスモデルに事業転換できるまでには15年から20年程かかっており、それまでは以前の物流事業が収益を支えていました。
茶谷さんがおっしゃる通り、アートやワイン、貴重品、それに映像メディアといったものを預かるビジネスはここ5〜6年くらいで非常に注目されるようになりました。しかし、実は最近始めたことではなく、1970年代半ばくらいから始めて、結果的には非常に大きな収益の母体になった、というわけです。
デジタル投資の前に「何を預かっているのか?」を議論した
茶谷 :あるタイミングで事業転換したことが今に生きている、といった感じですね。では、預かっている荷物の管理をしていくにあたって、デジタル投資をし、既存ビジネスをデジタル化させた経緯はどのようなものだったのでしょうか?
寺田 :デジタル化もこの5〜6年くらいの潮流ですね。今、世の中ではSDGs的な考え方や、真に顧客の益になることを追求する流れが起きていますが、寺田倉庫では10年ぐらい前から、「私たちはお客様の何を預かっているのか?」という議論を続けてきました。
もちろん、預かっているのはワインであり、アートであり、貴重品ではあるのですが、一方でそれらは時間の経過と共に価値を高めていくものでもあります。だからこそ最適な環境下で預ける価値がある、とお客様は考えているわけです。そうしてお金を出してまで預けているものが“死蔵”されている、つまり、日の目を見ないまま眠っているということは、価値が埋もれてしまうことにもなりかねません。

そこで、「お客様にとって価値があるものなのであれば、その価値が最大になることを目指すべきである」と、私たちは考えました。だから、必要であればそれを見せる場も作る、といった発想になったのです。
したがって、アートでもワインでもそうですが、まず一点ずつ写真撮影してデジタル化し、お客様がスマートフォン、タブレッド、PC上で見える状態にします。そうすることで最適な保管環境にありながら、価値が上がっていくタイミングや売るタイミング、あとはコレクションとしての価値を楽しんでいただくというサービス、付加価値をご提供できるようにしました。
こうした流れがあり、この数年は「お預かりしたものをデジタル化する」という動きが社内のメインストリームになっています。
デジタル化は「距離の壁」を越えられる

茶谷 :デジタル化すると、お客様に提供するサービスが「預かる」から、まさに非言語的な部分に深まっていくように感じますね。
寺田 :そういう意味では、昔はワインをお預かりするというより単純に空間を提供してお客様が温度や湿度を自由に設定して、その中で時を刻んでいるだけでした。
それが今ではお預かりしたワインを1本1本、写真を撮ることでお客様が自分のコレクションがきちんとデジタル整理でき、今の相場価格も分かるようにまでなっています。これはアートについても同様です。
いつかは、所有者同士がコレクションを売買できるサービスも展開したいと考えていますし、コレクションを見せるミュージアムを作ることも考えています。そうやってアナログとデジタルの垣根がない世界観を作っていくことが、私たちのお客様にとって一番嬉しいソリューションになると考えています。
茶谷 :なるほど。お話をお伺いしまして御社の、だれもが箱単位で倉庫を持てるクラウドストレージサービス「minikura(ミニクラ)」のコンセプトにつながるのかなと思いましたが。
寺田 :ありがとうございます。まさに、このような方向性に舵を切ったのは私たちが提供している「minikura」というサービスがきっかけでした。
個人の方々の家財を預かるトランクルームを展開し、その市場について改めて調べていたとき、「都心の自宅から1〜2キロ圏内にトランクルームを借りると意外にコストが高い」という事実に気がつきました。
都心の自宅近くでトランクルームを借りたい場合、自分が住んでいるマンションの坪単価より高い金額で借りざるを得ないという“謎の現象”が起こってしまうのですが、それは小さなトランクルームをたくさん作ると廊下のようなファシリティのスペースが多く必要になるためです。
「じゃあ、広い家を借りたらいいじゃないか」という話も出てくるかもしれませんが、不動産を所有している人も賃貸住宅に暮らす人も、そう簡単に住み替えられないですよね。そうしたことから、「多少高くても借りざるを得ない」という状況を捉えて世の中で伸びているのがトランクルームというビジネスです。
ところが海外では様子が全く異なります。例えばアメリカであれば、トランクルームの市場は3兆5000億〜6000億円の規模に成長しています。日本とは比べものにならないほど市場差が生じているのはなぜか? この理由をいろいろと研究していたところ、非常にシンプルなことが分かりました。
アメリカは首都圏が分散化されていて、首都のど真ん中の家賃相場に対して車で15分〜20分走ったあたりの土地は一気に地価が下がるのです。日本のように、東京からなだらかに郊外に向けて地価が下がっていくような富士山のような姿ではなく、剣山のように山の頂点が50ヶ所も60ヶ所もあるという状況で、剣山の谷の部分では、頂点に比べて場所によって地価が1/5にも下がるほどです。これならトランクルームを借りる意味が出てきますよね。
ところが日本はそうはなっていません。コストを抑えようとすると、モノは遠くで預かった方が良いけれど、遠くだと結局のところ運ぶコストもかかるし、段ボールで簡単に預けられるとしても何を預けているのかわからなくなってしまう。では、段ボールの中身をあらかじめ写真に撮ってから送ろうと考えても、その手間はかかってしまう…。
茶谷 :たしかに日本とアメリカのアーバンランドスケープは全く異なる様相を呈していますね。私もアメリカに住んでいましたので日米の都市の違いは実感として理解できます。
寺田 :そうした中で、私たちが一箱330円でお預かりして写真も撮影する、ということでサービスを始めたのが「minikura」です。私たちとしても、預かるコストが安ければそのコストは吸収できますからね。
このように、今の寺田倉庫の原点には「minikura」があって、デジタル化することによって“距離の壁をなくす”という発想からプロジェクトがスタートしました。
サービスとして預かったものを死蔵させないという考え方を使ってサービスモデルをどんどん展開し、「ただ預ける」ということ以外のニーズを満たしていく、という掛け算のビジネスをしてきたというのがこの10年間です。
サービスを知ってもらうために「free to play」方式にも挑戦
茶谷 :私は日本ソムリエ協会のワインエキスパート資格を持っているので、ワイン保管サービスは非常に興味深く見ていました。最近は安価でちょっといい銘醸ワインが当たるキャンペーンも展開されていますね。キャンペーンに応募して当選したとして、その賞品のワインは動かさずにそのまま寺田倉庫に預けておくこともできる、という流れになっているようですね。自宅に置いておくのではなく倉庫で保管してもらえる、という体験までを賞品にしている取り組みは非常におもしろいと思います。
これはゲームでいう「free to play」と非常に似ていて、まずは楽しんでもらい、気に入ったら課金してくれるだろう、という考え方のビジネスモデルだな、と感じました。
寺田 :あのキャンペーンも実は“変化球”みたいなものなのです。それというのも、私たちが最初に考えていたのは、ワインの物々交換でした。およそ35万本のワインをお預かりしているので、所有者同士で欲しいワインを売り買いするプラットフォームができたり、また、リバースオークション的に「このワインほしいです」と呼びかけられたりする場を作りたい、というのが始まりです。

しかし、そのプロジェクトを進めていく過程で「酒販免許を取得しなければならない」という壁にぶつかりました。免許の取得には半年ほど時間がかかるのですが、それを全員に取得していただくのは大変なコストで、難しいと判断しました。法律の壁を崩すことは別途きちんと働きかけていくにしても、すぐにはできません。
そこで、まずは自分たちがワインを取り扱ってみようか、と少し方向転換しました。ただ、実は私はそんなに売れないと思っていたのです(笑)。
しかし、2020年にサービスを開始してみると、あれよあれよという間に数億円売れたのです。新しくワインを購入されるお客様に新たな体験を、ということで、先ほどのようなキャンペーンをしてみた、というわけです。
茶谷 :アメリカでもコレクターの方がもう飲めなくなった3,000本や4,000本のワインのコレクションを別のコレクターに売るケースがよくあるのですが、それを「権利だけ移す」というやり方でトランザクションができるのが寺田倉庫の提案ということですね。
寺田 :まさにそんなところです。ワインにも20〜50年という賞味期限がありますので、その中でどう価値を最大化するか、というのがコレクターの関心事のひとつだと思います。そこに、ただ預かるだけでなく、最大限の意味合いを付加するという取り組みは、新しい市場ができるチャンスになるのかな、と思います。
<後編に続く>
対談者プロフィール

寺田航平
寺田倉庫株式会社代表取締役社長CEO
慶応義塾大学法学部法律学科を卒業後、1993年に三菱商事株式会社に入社。2000年にデータセンター事業の株式会社ビットアイルを設立し、代表取締役に就任。
2006年大阪証券取引所ヘラクレス市場(現JASDAQスタンダード市場)上場、2013年7月東京証券取引所第一部上場を果たす。2015年に同事業世界最大手である米Equinix Inc.のTOBを受け上場を廃止し、
エクイニクス・ジャパン株式会社取締役COOに就任。2018年6月には家業である寺田倉庫株式会社取締役社長に、翌年6月には代表取締役社長に就任し、現在に至る。その他、経済同友会幹事、ベトナムオフショア事業大手の株式会社コウェルの代表取締役会長、株式会社イーブックイニシアティブジャパン及び株式会社マーケットエンタープライズの社外取締役、個人投資先として株式会社モブキャストホールディングス、アライドアーキテクツ株式会社など、多数のベンチャー企業にてアドバイザーを兼任。
KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。