「日本では海外のスタートアップのようなスケールの企業が育たない」とよく言われます。しかし、過去を振り返れば、多くの日本発スタートアップがスケールアップし、今日の大企業となって、各業界における世界的リーダーとして認知されていることは周知の通りです。
では、以前のように競争力を持った企業を育てるために、スタートアップを取り巻くステークホルダーはどのような支援ができるのでしょうか。
KPMG Ignition Tokyo(KIT)の茶谷公之とティム・デンリ、そして、あずさ監査法人常務執行理事であり、企業成長支援本部長でもある伊藤俊哉が対談をしました。
スタートアップも老舗企業も、成長支援を必要としている
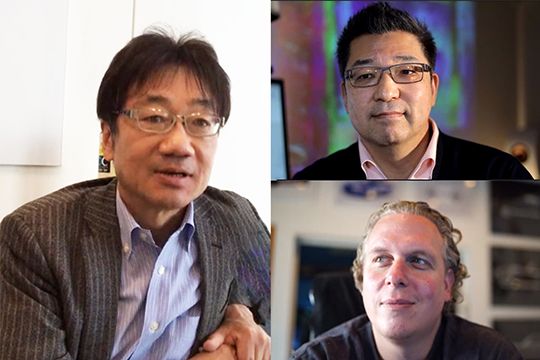
(あずさ監査法人 常務執行理事、企業成長支援本部長/パートナー/公認会計士 伊藤俊哉 (左)、株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(左上)、同社取締役 パートナー ティム・デンリ(左下))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。
茶谷: 伊藤さんの部署は、スタートアップの成長支援をされているとのこと。立ち上げすぐの会社との接点もたくさんお持ちだと思います。具体的にどのような支援をされているのでしょうか?
伊藤: スタートアップのIPO支援の実際の業務範囲は多岐にわたります。例えば、上場を検討中のスタートアップ経営者らの「これから上場した方がいいのか? それが本当にベストの戦略なのか?」という悩みに寄り添ったアドバイザリーを行うこともありますし、上場ではなく海外進出やIT導入など企業の成長ステージに合ったサポートを提供することもあります。
また、意外に思われるかもしれませんが、50年以上の歴史を誇る老舗オーナー企業から後継者問題やビジネスに関する相談を受けることもあります。
茶谷: 対応範囲が幅広いですね。確かに少し前から事業承継は注目のテーマになっていますね。
伊藤: グローバルに展開するKPMGではファミリービジネスというくくりで主に富裕層向けの税務調査を行なっていますが、日本の場合は節税のアドバイスというよりも、後継者問題や老舗企業のIPOなど「会社を何とかしたい」という想いに応えるというケースが多くなっています。そういった日本ならではのファミリービジネスの支援を通じて、日本各地のより良い企業とネットワークを構築できれば面白いことができるのではないかと個人的には考えています。
テクノロジーに強い経営者に必要なのは、同じ想いを持つCFOやCTO
デンリ: 成長企業という意味では、海外では成長過程にある企業の経営者は技術者である傾向が強くなって久しいのですが、日本でもそうした傾向はあるのでしょうか?
伊藤: 最近はテック系と呼ぶ範囲が広がっているわけですが、とにかく技術にこだわりある人の割合が増えているのは確かです。
ただ技術者やその思考を持っている方と話をしていると、「技術を認められてもその後の拡大が難しい」との悩みが挙がってきます。例えるなら、「おいしい料理までは作れるけれど、繁盛店にするのは難しい」という課題にぶつかっている、というわけです。
茶谷: 確かに、最近お会いするスタートアップの経営者たちは、有名大学で研究していて、研究所がそのままスピンアウトした、というような流れが多いように思います。

「美味しい料理は作れるけど、繁盛店にするのは難しい」という話ですが、Hondaの本田宗一郎氏は名参謀である藤澤武夫氏と、ソニーであれば盛田昭夫氏と井深大氏とがタッグを組んでいたことを思い出します。技術に徹する本田氏や盛田氏と、渉外やマーケティングなどを担う藤澤氏や井深氏というように、テクノロジー側の人と経営側の人が組み合わさって発展するのが日本らしいように感じます。
伊藤: そうした意味では、今は技術側の人を支える人が見当たらないケースが多いように思います。「ベンチャーキャピタルでいろんなことを支援していました」という人はいますが、ある会社の経営に5〜10年携わって上場まで経営者と一緒になってやっていた、という人とはやはり感性や温度感が違っているものです。そうした理由からか、CFOが途中で変わってしまうというケースは少なくありません。また、経営者と想いを同じくできるCFOはいないかと、我々に相談してくる経営者もいます。
茶谷: 私もスタートアップを支援する人たちから、優秀なCTOやCFOが“枯渇している”という話はよく聞きますし、それがスタートアップの新たな課題になっていると耳にしました。
デンリ: スタートアップは技術を注目されがちですが、企業成長させるためのチームづくりをする際に一番に見るべきなのは「同じ船に乗って一緒にできそうか?」という人間性の部分だと思います。これはM&Aや事業譲渡の案件でも同じことが言えると思います。
海外のスタートアップを見ると、テスラ社のイーロン・マスク氏やApple社のスティーブ・ジョブス氏のように技術はもちろん、高い経営センスも兼ね備えているケースがありますが、それは稀なことです。HondaやSonyのようにいい人材の組み合わせで成長していくということは重要だと感じます。
プロフェッショナル人材の流動性はスタートアップの成長を左右する

茶谷: 私はシリコンバレーに5年ぐらいいましたが、あの場所の良さは、スタートアップをサポートするリーガルやファイナンスなどのプロフェッショナル人材の流動性が非常に高いことだと見ています。
日本の場合、どうしても転職すると給料が下がるリスクがあり、面白いプロジェクトがあっても、素早く参加してIPOした後は次のジェネレーションに移る、というサイクルがまだできていないのかもしれません。そこが早く変わるといいですね。
また、VCについても、日本の場合はテクノロジーを熟知した人材が少なく、海外のように自分でテクノロジー系の会社を立ち上げた人がVCに携わる、というケースがほとんどないことも違いとして挙げられます。
伊藤: 私もこの10年以上、「日本ではなぜアメリカのように大きなスタートアップが育たないのか?」という“古くて新しいテーマ”について考えてきました。その中で大企業とスタートアップの連携が上手くいかない根本的な理由として感じたのは、日本の「縦割り組織の意識」や「自分の範囲や組織に対してある意味で固執してしまうこと」です。江戸時代の藩制度の意識がまだ残っている、と感じてしまうくらいです。
そうしたメンタリティであるがゆえに心の流動性が低くなり、大企業側はスタートアップに対して口では「応援します」と言いながら、実際は3年程経って成長していなければすぐに手を引くこともあるし、スタートアップ側もそれをなんとなく想像して振る舞う、というわけです。このような状態では、双方の信頼関係は育ちません。
抽象論になりますが、“藩意識”のようなものがあるから、大企業は自社の利益を最優先に考えて「スタートアップと一緒に成長する」という本気さが出てこないのではないでしょうか? 大企業とスタートアップがもう少し心を通わせることができるように考える必要があります。
デンリ: そうですね。やはり日本と海外ではエコシステムとしてのあり方が違うことに目を向けなければなりません。アメリカでは、「このスタートアップは今のところ足りない部分は多々あるけれど、ひとつ光るものがある」という点にフォーカスして大企業が一緒に光る部分を育てよう、という気持ちがあります。これが結果的に双方にインセンティブが生まれる元になっていると見られます。日本にも、ここにしかない独自的なやり方がたくさんあると思います。
伊藤: そうした場面で、我々のような監査法人は、公平で中立な立場に裏打ちされた信頼感をベースに、もっとサポートできる分野があるのではないか、と感じます。
茶谷: 私たちもスタートアップと大企業やCFOなどの人材が集まるプラットフォームを作って新しいチャレンジをサポートするようにし、「日本でしか生き延びられないような会社」から「海外にチャレンジする企業」への変換を後押ししていきたいと思います。
特に、技術系のスタートアップは同じ年代や同じ研究室のメンバーがそのまま外に出た、というケースが多く、イベントリスクを潜在的に抱えているように感じます。そうしたところで必要とされるベテランの知恵や経験は今後大きな価値を持つと考えます。
伊藤: 他方、私たち監査法人も十分な専門性のある人材の不足、という問題に向き合う必要があります。スタートアップも大企業も同じように監査できるだけの能力を兼ね備えた人材を育成するまでには、相当の時間が必要です。求められる質を担保しながら依頼をすべて受けるには、やはり限界が来ているのではないかと感じています。
茶谷: なるほど。最近のスタートアップは使っているテクノロジーがエッジコンピューティングやブロックチェーン、暗号など、高度な専門性に基づいているものが多く、さらにビジネスモデルもこれまでの製造業などとは異なっているため、監査に必要な知識も大きく変わっているのではないか、と想像します。
伊藤: 技術面の理解もさることながら、企業そのものの理解という面でも課題はあります。実際のところ、過去に経験したことがあるビジネスモデルの企業ならば、どんなところに監査リスクが発生しやすいか、ある程度予測することができます。
しかし、スタートアップの場合はお互いが初めてのお付き合いになることが多く、職業的猜疑心をもって監査をし、かつ経営者に納得してもらうのは難易度が高いものです。それにもかかわらず、「とりあえず依頼を受けて監査する」というスタンスでお付き合いしてしまうと、結果的に経営者からの信頼をなくしたり、マーケットに不信感を与えることになりかねません。
そうした理由で、我々の一番の問題は人材を育てていくことだと考えています。それなしでは早晩、経営者と議論を交わすことすら難しくなるでしょう。KPMG Ignition Tokyoのみなさんには、ぜひテクノロジー学習を通じて、我々のリテラシーを上げるお手伝いをしていただきたいです。
次世代のアドバイザリーサービスではAIをどう活用するのか?
茶谷: ここまで企業成長支援に欠かせない人材論やメンタリティの話をしてきましたが、テクノロジーやソリューションが支援を後押しすることもできると考えています。現場では実際にどのような場面で「テクノロジーを活用できる」と思われるか、非常に興味があります。
伊藤: 我々に対する依頼には、「ワンストップで最初から終わりまで面倒を見てもらいたい」というものが多くあります。そうした企業に対して、スタートアップから始めてその先のゴールを2つぐらい設定し、それを見据えた上でどうしていくのか、支援するツールがないか、と想像しています。
茶谷: なるほど。今、KITでは、「次世代のアドバイザリーを定義したとき、どういうことができるとそれが果たせるのか?」という発想から、あるファンクションをAIで作ろうと考えています。
これは、今までのアドバイザリーが「一緒に走って励ます存在」だったとしたら、次世代のアドバイザリーは「マラソンの先導車のように『こっちに行くべきですよ』と誘導する存在」ではないか、という考え方を元にしたものです。

企業の成長エンジンが戦略と戦術、運用によって構成されているとするなら、戦略については企業の経営者の発言や社内のニュースレターなどで分析が可能ですし、そこから戦略や存在意義を見出すこともできるでしょう。その戦略に対して外部環境の要素を加えると、戦術も見えてくると思います。それが分かればどういった体制や組織で運用していくか、モデルが出てくるでしょう。そういったことをAIで明らかにしていくことはできないか、と議論しているところです。
伊藤: それは興味深いですね。私たちはこれまで会計監査に特化してきましたが、役割としては医者のようなものだと考えています。そう考えた時、世の中が急速に変化している、ということは「医者として診る体が変わっている」ということだと言えます。
そうであるなら、私たちは、新しい“体”のことを知らなければなりません。しかし現状はどういう切り口で理解したらいいのか、まだ正確に把握し切れていないのではないかと危惧しています。そこを改善するためにも、KITからテクノロジーの現在地や可能性について共有してもらうことは非常に有益だと考えています。
企業の全身をCTスキャンするように調べる

茶谷: 企業そのものをヒトの体ととらえ、監査法人の役割を医師として考える、というアプローチは私たちも多用するものです。そうした役割を果たすには、先ほどの構想以外にもできることがあるかもしれません。
伊藤: 企業側はよく「今、会社全体を見た時に一番ダメな部分はどこか?」という問いかけをしてくることが多いのですが、現状では感覚的にしか問題点を指摘できない、という課題があります。これに対し、「よく成長する企業の内幕はこうです。貴社とはここが異なっています」と客観的なデータで見せられたなら、と考えることはあります。
見た事柄に対して、「うちは大企業とは違いますから」と言われたとしても、データや予測を元にきちんとした助言ができるなら、それは大いに意味のあることだと思います。
茶谷: 今KITでは「マイクロサービス」というソリューションを製作しているのですが、これはそうしたことを可能にするものになるかもしれません。
老舗企業を社会全体で承継していくという考え方
デンリ: 最後に、今後5年後から30年後の話をしておきましょう。私はやはり、人と人との関わり合いの進化に注目しています。例えば、瞬間的に流行した「クラブハウス」のようなソーシャルメディアに代表されるデジタルやテクノロジーの要素は、コミュニケーションのあり方を急速に進化させています。
茶谷: 確かに、そうしたソーシャルメディアに対して24時間365日存在感を示せるようにアバターと音声技術を組み合わせて活用する、というやり方も現実味を帯びています。私も近いうちにアバター化して、私自身は出社しない、というようにできないか模索しているところです。
一方、おそらく今の日本の現場では、技術やスキルが非常に属人的になってしまっているがゆえに「その人がいなければならない」状態にあり、技術の承継が困難になっているのだと思います。これを解消する方法の一端はテクノロジーによって見出されると思います。
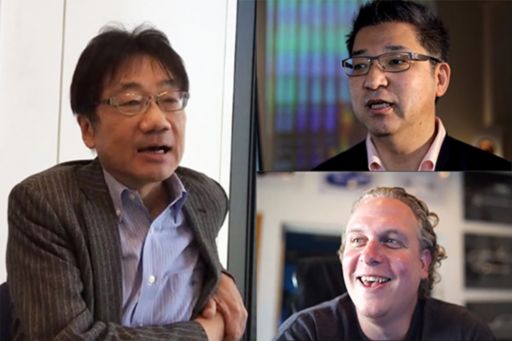
ただ、その技術やスキルを持つ企業を存続させ、再び盛り立てていくにあたっては、大企業の人材の流動性の向上が求められると考えます。日本型のキャリア形成として、同じ会社で様々な部署を経験する、というものがありますが、これによって広い意味での経営を経験的に勉強してきた人材が事業承継に困っている会社を受け継ぐことによって、未来を繋いでいく、という姿もあるだろうと想像します。
伊藤: 今日のスタートアップは「社会課題を解決したい」という思いがきっかけで誕生することが多いと感じます。しかし、社会課題は時代とともに違っていて、いま老舗企業とされている企業も当時の社会課題に対して「世の中に役立つ仕事をしたい」と誕生したものがほとんどだと考えます。そうしたこともあり、最近は今の生活様式に求められる安全や安心を社会に提供しようと努力する老舗企業が増えてきました。
両者は対比されがちですが、想いは同じだと私は感じています。そうであるなら、両者が新しい形で融合して、1+1が5にも6にもなるように道筋を作ることが大切ではないでしょうか?
もはや「どこの会社が事業を承継する」といった話ではなく、日本全体が老舗の優れたコアの部分を引き継ぎながら新しい技術と掛け合わせていく必要があり、会社という“小さな枠”にこだわらなくても良いとすら考えています。こういった今までとは違う発想を、社会が大きく変わりつつあるコロナ禍だからこそ、想像してみるチャンスだと思います。
私たちも監査法人として「不正を早く発見する」ということではなく、「不正が起こらないような企業をどうやって作っていったらいいのか?」ということも含めて、固定観念にとらわれず、若い人たちにとって夢のあるイノベーションを起こしていきたいと思っています。
KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。





