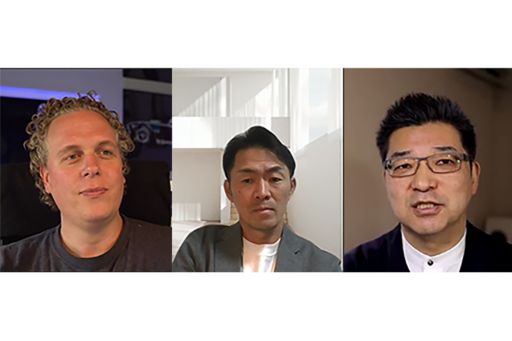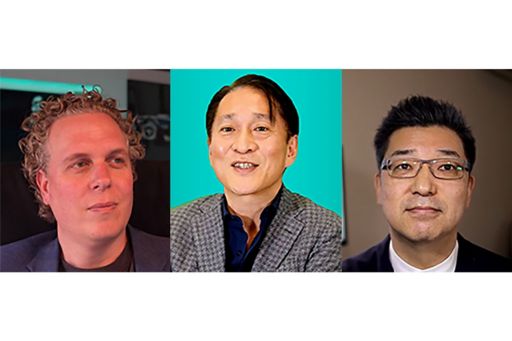IoTやAI、クラウドや5Gといったテクノロジーが私たちの生活の一部となり、社会に普及しつつあります。そして今や、リアル空間に存在する情報をデジタル空間で再現することで、リアル空間を“鏡”のように再現する「デジタルツイン」までもが現実的な未来と感じられるようになってきました。
そのようなデジタルとリアルの境界線が限りなく曖昧な世界において、私たちはどのような問題に向き合い、どこに解決の端緒を見出すことになるでしょうか?
本稿では、KPMG Ignition Tokyo(KIT)の茶谷公之が、ドライビング&カーライフシミュレーター「グランツーリスモ」を世に送り出した株式会社ポリフォニー・デジタルの山内一典代表取締役と対談した内容をお伝えします。
デジタルツインの先駆けとしての「グランツーリスモ」
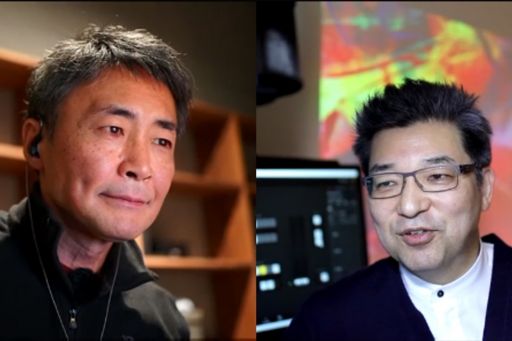
(株式会社ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデント山内一典氏(左)、株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(右))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。
茶谷 :「プレイステーション®️1」を発売して間もない頃、ソニー社内では「山内さんのところで凄いのができつつある!」という噂で持ちきりでした。当時からすでに夢のような発想だったわけですが、最近「デジタルツイン」という言葉を聞くと、「グランツーリスモ」はまさにその先駆けだったのではないか、とつくづく思います。
最初から「レースゲームではなく、シミュレーター」を狙っておられたのでしょうか? また、デジタルツインが注目される昨今、思うところはありますか?
山内 :そもそも多くのビデオゲームは、リアルの世界をそのまま再現するのではなく、むしろ「ここではないどこかの世界」の中でその世界の物理をエンジンで表現する、というものだったと思います。例えばマリオ・ブラザースには、マリオ・ブラザースの物理があります。しかし、私たちが相手にしてきたクルマやコースは現実の世界に存在するものだったため、結果的にデジタルツインの一例になったのだという印象です。
茶谷 :そういう意味では凄い先見の明ですよね。そして、今はもう一歩踏み込んで、シミュレーターで練習してレーシングのプロを育成するという「GTアカデミー(「GTアカデミー by 日産×プレイステーション®」日産、プレイステーション、ポリフォニー・デジタルの3社が2008年に始めたバーチャルとリアルを繋ぐ国際的なコンテスト)」を展開されています。
GTアカデミーの取り組みは、KPMGのようなプロフェッショナルファームで例えると、実際の業務の中で体験を積んで経験値を上げることで重責を担うプロフェッショナルになる、という過程をシミュレーションで達成しようということだと感じました。このことは教育に大きなインパクトを及ぼすと思うのですが、どのような意図で始められたのでしょうか?
山内 :GTアカデミーのプロジェクトは2008年に始まりました。最初のグランツーリスモが登場したのが1997年なので、約10年後です。
2008年当時、私は「グランツーリスモがきちんとしたシミュレーターであることを証明したい」という強い気持ちを持っていました。それというのも、「グランツーリスモはドライビングスキルの習得と向上に確実に寄与する」、「実際の自動車のシミュレーターとして使える」と考えていたものの、やはり世の中の評価としては、「ビデオゲームでしょ?」という雰囲気が強かったからです。ですので、私の考えを実証したいと思ったわけです。
茶谷 :結果としてたくさんのGTアカデミー出身者が様々なレースで高成績をおさめているわけですが、彼らはどのくらい練習しているのでしょうか?
山内 :例えば、FIA(国際自動車連盟)とのパートナーシップのもとで現在開催されている「FIAグランツーリスモ選手権」というeスポーツの選手権で勝ち上がってくる世界中のトッププレイヤーたちは、3〜4歳のうちから毎日4〜5時間は走り込んでいるようですね。
現実世界ならば、レーシングカー、あるいは、レーシングサーキットで走れる時間はほんの少ししか確保できません。リアルなモータースポーツは、とにかくお金がかかりますから。それに比べると、低コストで圧倒的な経験値と練習量を得ることができます。
茶谷 :ボリューム勝負というか、経験値勝負というところがデータAI時代っぽいアプローチに感じます。データをたくさん投入し、そこから最適なアルゴリズムを見つける、という感じですね。
ところで、レースでも日常の運転でも、リアルであれば天候や道路のコンディションなどによって求められるドライビングテクニックなどが変わってくると思うのですが、そうしたことまでシミュレーションできるのでしょうか? 例えば雨の日に設定すると路面が滑りやすい状態になる、などはありますか?
山内 :はい、路面のμ(摩擦係数)などは、コンディションによって変化します。走るコースやその状態、車の組み合わせや車自体のセットアップの違いなどはそれぞれが膨大なパターンがあり、さらにその組み合わせも膨大になり得ます。これを実車ですべて体験しようとすると、それは不可能なことでしょう。シミュレーターの方がそうした環境を体験しやすいと言えます。
茶谷 :そういったリアル世界での障壁を越えていろいろ試すことができるのはシミュレーターのアドバンテージですね。
山内 :そう思います。言い方を変えると、シミュレーターは、ある特定のコースやクルマでの経験を深めるというより、クルマとは何か? それは、どういう物理的な振る舞いをする存在なのか? それは、どうコース=環境と相互作用するのか? といったことを、総合的に、抽象化したレベルで学んでいける気がします。
eスポーツで感じる、「心を揺さぶる」スポーツの価値
茶谷 :では、現在のグランツーリスモはどのくらいの割合でリアル(実際の環境)を再現できていると感じていますか?
山内 :GTアカデミーを始めた2008年以降、例えば、ル・マン24時間レースに参加するレーシングカーの設計をグランツーリスモのシミュレーションエンジンを使って開発してみたことはあります。また、2008年から2016年まで私も参加したニュルブルクリンク24時間レースでも、グランツーリスモ上でクルマを作り、セットアップし、実際にサーキットを走らせて、データを取りながら開発を進めていきました。
そのように、データロガーでログを取って、それらをもとにシミュレーションしたあと、それを実車に反映させて、サーキットを走らせ、クルマに設置した膨大なセンサーからの情報をグランツーリスモ上にフィードバックさせて、またシミュレーションを回す、という円環的な開発ををずっとやってきましたし、そうしたことが可能な精度で実践できている、ということです。つまり、クルマの開発ができるレベルにある、と考えています。
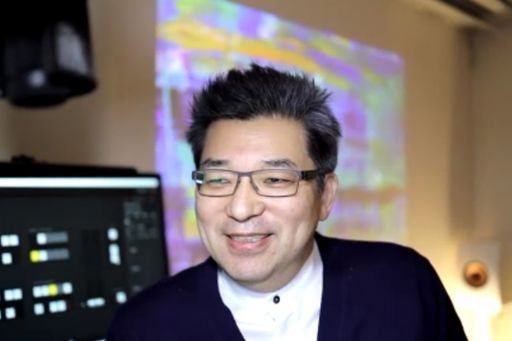
茶谷 :それは凄い! ゲームとリアルの垣根がほとんどなくなっている、まさにデジタルツインのようですね。
この流れで山内さんにぜひお聞きしたいのが、「eスポーツの未来」です。実はKPMGにもeスポーツ好きがたくさんいて、eスポーツにまつわる書籍を上梓したり、社内で大会を開催したりと盛り上がっています。山内さん自身はeスポーツが今後どう展開すると思いますか?
山内 :これは「全く分からない」という印象です。eスポーツといっても様々ですし、私たちがeスポーツの何かを代表しているという実感も正直なところありません。
そもそも私たちはeスポーツのムーブメントがあったからグランツーリスモSPORTを作ったわけではありませんし、FIAと組んでチャンピオンシップを開催したわけでもないですが、実際に自分たちで取り組んでみた感想を申し上げると、「スポーツというのは人間のエモーションを喚起する効率のよい“装置(メカニズム)”」なのだな、ということです。
開催前も「心を揺さぶられるだろう」ということは想像してはいましたが、自分たちが体験してみると想像以上です。スポーツは自分で行うにせよ、観客として見るにせよ、人の感情に訴えかけるところがあり、その感情の起こりにはリアルもバーチャルもまったく違いがない、と思いました。また、これまでスポーツインダストリーの人たちが何を体験していたのか、どんな価値を生み出していたのか、本当によくわかりました。
茶谷 :確かにレーシングゲームだけでなく多くのゲームがあり、それらが合わさって一つの産業でありブームになりつつあるのがeスポーツですね。プロも生まれてきて、近い将来にはYouTuberと同じく子どもが就きたい職業の上位になりそうです。
自動運転に「壁」があるとしたら?

茶谷 :さて、eスポーツと同様にグランツーリスモと関係が強い産業として挙げられるのが自動車産業です。昨今、自動運転が中心的な話題になっているのはご承知の通りです。KPMGの中にも「KPMGモビリティ研究所」を開設してこの分野のアドバイザリーなどを行なっているのですが、自動運転が可能になった時、レースの魅力や進化はどうなるのでしょうか?
山内 :素朴な答えになるのですが、自動車が出てきた時、当然ながら人より速く走れるけど人は走ること(陸上競技)をやめなかったですよね。そう考えると、AIが人間の技術を超えて自動運転が始まったとしても、運転することをやめたり、レースの価値が損なわれたりすることはないと思います。
茶谷 :レースのルールが変わる可能性はあっても、というイメージでしょうか?
山内 :おそらく、AIが最適化した結果として人間に勝てるようになったとしても、ゲームの直前にルールを変えれば人間は対応できたとしてもAIには難しい、という状況がまだ、しばらくは続く気もします。
茶谷 :直前にルールが変わると確かに現状ではAIは対応しきれないかもしれないですね。一方で、2020年末には棋譜を読まず人間に勝ったAI将棋プレイヤーが誕生した、という情報もあります。これがどう凄いかというと、「ゲームのゴールを自分で設定する」という人間の思考に近い発想がAIにもできるかもしれない、という点です。このことは産業界にも大きなインパクトを与えるかもしれません。
山内 :最近の研究によると、AIに無作為で1億枚くらいの画像を見せると、教師なしでも、創発的に世界の分節化(セグメンテーション)が起きるらしいですね。
人間の子どもの場合、親などの大人と一緒に世界を体験し続けた結果、自然と「世界とはこうなっている」という世界の分節化を行ない、後から覚えた言葉の体系と紐付けて「名付け」というプロセスを経ていきます。どうもそれと同じことがAIの世界でも起きるらしい、というのです。
この話はAI開発のスタートアップ企業である、プリファード・ネットワークスの岡野原大輔さんに聞いたのですが、大変興味深いと思いました。1億枚という数が多いのか少ないのかは、わかりませんが。人間の子供が体験を通じて世界を分節化するのに、だいたい1年かかるとすると、それよりは圧倒的に少ない時間で可能なのは間違いないです。
茶谷 :それだけ多く集められるものがそんなにありませんからね。企業内の呼称や勘定科目などはシンプルで数が少ない方が良いとされるので、少ないデータから答えを導く、というディープラーニングではやりにくいアプローチも考えないといけないかもしれません。
山内 :そのあたりが面白いところだと思います。人間は、シンプルさを美しい、と思う。Tシャツにプリントできるようなシンプルな方程式から、多くの生産的なアウトプットが得られるようなものが美しいとされている。一方、AIはそうではないんですよね。データドリブンで、人間なら量が多すぎて、手に負えないような膨大な量の方程式を、不可視なネットワーク層の中に生成するのがAIなのだと思います。数理的、という意味ではどちらもそうですが、AIは、これまで人間が取り扱ってこなかった数理の世界です。
茶谷 :自動運転が広がって、いろんな産業に波及しようとしている中で、カーオブザイヤーの選考委員もされている山内さん。今後の自動車産業の展望、自動運転が実装された後の世界をどう見ていらっしゃいますか?
山内 :私は過去から連綿と受け継がれた伝統的な自動車文化の中で日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員などで関わりを持っているので、自動運転の本当の最前線は分からない、というのが正直なところです。
しかし、素朴に「レベル5の自動運転は実現するのか?」という点は、自分の中で答えが定まらない状態です。もちろん、その手前まではあっという間に到達すると思うのですが……。
茶谷 :世界に先んじて超高齢社会となる日本において、自動運転が社会に実装されると、“移動難民”や“買い物難民”などから多くの支持を受けると思っています。特に、スーパーや病院のような生活便利施設と距離がある大都市圏以外の地域では切実なニーズがあるでしょう。
グランツーリスモのシミュレーターを使って自動運転が進化する、ということがあれば、日本として大変誇らしいことだと思うのですが、いかがでしょうか?
山内 :実は、米半導体大手のNVIDIA(エヌビディア)がゲームとしてのグランツーリスモのようなシミュレーターで自動車の運転を学ばせていたらしいのです。ただし、それはもう数年前のことで、現段階の自動運転の研究は、「自動車をどう運転するのか?」は、ひとまずクリアして「世界をどう認識するか?」というレベルでの開発競争のように見えます。
ともあれ、今どういうアプローチをしているのか、気になりますね。画像からの意味論的な認識はすでに実用化されていますから、「これは白線、ガードレール、道」ということは認知できます。しかし、「地面というものは必ず空の下になければならない」というレベルでの認知は意外と難しいのではないか、と思っています。
例えば、路上にトイレットペーパーが散乱しているところに出くわしたとして、人間なら「ああ、トラックから、何かの拍子に荷物のトイレットペーパーが落ちたのだろう」と瞬間的に推定できますが、AIにはそれが、路面の白線と区別がつかない。かなり難しいですよね。
茶谷 :メタ推定のようなものはそんなに得意ではないですからね。モノが何であるかを認知できても「どうしてここに?」といったことを推論するのはAIにとって容易ではありません。
山内 :そうですね。そのあたりが実装の障壁になっているのではないかと思います。もちろん、レースをする上で人間より高成績を出せるAIというのは可能だと思います。単独で1周のラップタイムを競う、タイムトライアルでは人間より優れたAIはもうすでに存在します。ただし、レースになると様々な要素が絡み合い問題が生じるので、対処は簡単ではないと言えます。
茶谷 :レースの事故を何万回も学習させる必要も出てきますね。
山内 :そうですね。あとは実際にAIにオンラインで人間と対戦させてみる、ということでしょうか。ある程度まで行ったら、AI同士の強化学習でどんどん強くなって行きそうです。
ヒトは「リアル or デジタル」を選択するか?
茶谷 :私たちKPMGには、実際にクライアント先に出向いてインサイトを吸い上げたり問題を明らかにする会計士やコンサルタントなどのプロフェッショナルたちと、KITのようにインサイトを分析したりテクノロジーで問題解決の方法を探るプロフェッショナルがいて、フロントとバックヤードに分かれてクライアントをサポートしています。この構図はフォーミュラーワン(F1)のチーム体制に似ていると思っています。
そこで山内さんにお聞きしたいのが、「F1のチーム体制、つまり、現場に向き合う存在とデータ分析を担う存在とがワンチームとして一つの物事に取り組むというスタイルがこれからも続くのか?」ということです。
山内 :私もレッドブルやフェラーリ、メルセデスやマクラーレンと、いくつかF1チームの現場に行ったことがあります。

レース中は、サーキットにあるピット内で整備等をして活動している人たちがいる一方で、レースに同行できるチームメンバーの数はレギュレーションで規定されていますから、現場にいる何倍もの数のストラテジストたちが、チームの拠点・本社のコントロール・ルームに詰めているのはご承知の通りです。その部屋は常時ネットワークで繋がれて、レース中の瞬間瞬間で送られてくるデータロガーのログや各車のGPS座標をもとに、常に分岐する可能性のある未来を推定して、その中で一番勝てるプロバビリティが高いシナリオを選んでいく、ということをやっています。
そこでおもしろいのは、そういったサーキットの現場からは遠く離れたコントロールルームにも、サーキットの映像がプロジェクターで見られるようになっていることです。素朴に考えれば、その映像は必要なくて、自分の手元にあるディスプレイの中で、ある程度抽象化された、あるいは解析しやすいデータが表示されていれば十分だと思えるんですが、それでも現場の様子は見られるようになっているんですよね。
茶谷 :現場感覚というか、意識付けが必要なのでしょうか?
山内 :そうなんです! ストラテジストといえども、人間には、現場感が大事だということです。ああいった様子は今後も変わらないのかもしれないですね。
茶谷 :そのニーズは理解できます。最近、ハリウッドでは、ミーティングルームの扉を開けると向こう側の壁に別拠点の様子が映し出されていて“バーチャルルーム”として繋がっている、という演出のもとで打ち合わせをするケースが出ている、と聞きました。そうして、あたかも共通空間にいるように感じさせる、ということのようです。
TeamsやZoomはすっかり普及しましたが、画面上で区切られているので「個」の印象が強く、一体感がないと思うようになった結果かもしれません。
<後編に続く>
対談者プロフィール

山内 一典
株式会社ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデント
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント シニアバイスプレジデント
日本のゲームクリエイター、山内一典は世界で8040万本を売り上げたグランツーリスモゲームシリーズで幅広く知られています。1992年にソニー・ミュージック・エンターテインメントに入社し、ソニー・プレイステーションの始まりに関わった後、1994年にはソニー・コンピューター・エンターテインメントに移籍し、自身初となるタイトル、モータートゥーン・グランプリをプロデュース。1997年にはグランツーリスモシリーズの最初のタイトルを作り、世界で1085万本の売り上げを記録しました。山内氏は1998年に株式会社ポリフォニー・デジタルを設立し、同社の社長を務めています。また2001年より日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員も務めてきました。
KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。