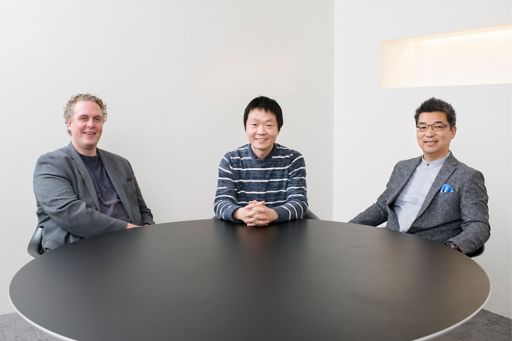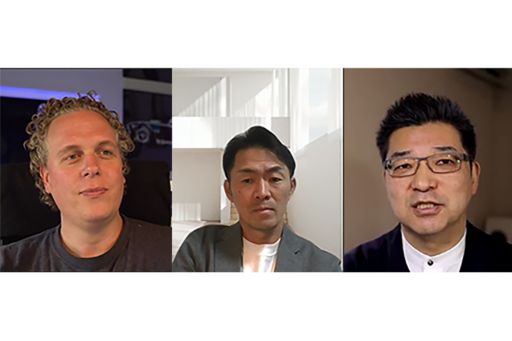企業経営や実務において、ESGやSDGs、サステナビリティといった言葉が活発に用いられるようになりました。そして今日、これらは「理想やお題目ではなく、企業価値向上のための重要な要素のひとつ」として透明性をもって示すよう求められています。
では、どのようにそれを実践していくのか? デジタル経営の“水先案内人”であるKPMG Ignition Tokyo(KIT)の茶谷公之とティム・デンリが、あずさ監査法人 常務執行理事 兼 KPMGあずさサステナビリティ株式会社 代表取締役 足立 純一と意見を交わしました。
サステナビリティへの関心が経済界でも高まってきたのはなぜか?

(株式会社KPMG Ignition Tokyo取締役 パートナー ティム・デンリ(左上)、同代表取締役兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(左下)、あずさ監査法人 常務執行理事 兼 KPMGあずさサステナビリティ株式会社 代表取締役 足立純一(右))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。
茶谷: 議論の前に、なぜサステナビリティへの関心が経済界で高まっているのかを俯瞰しておきましょう。KPMGあずさサステナビリティ株式会社の代表取締役である足立さんから、解説をお願いできますか?
足立: 多くの方がすでにご存知のように、企業の存在意義が「投資を受けて株主に還元する器」という考え方から「企業は社会全体の重要な構成要素のひとつである」という考え方にシフトしつつあるからだと言えます。企業は直接的な投資家だけでなく、顧客やその関係者、自社の取引先など様々なステークホルダーと関わる存在だと自認するようになってきたのです。
今日、企業にとっての「サステナビリティ」は、ビジネスの持続性だけでなく、社会そのものの持続性も包括するようになっています。それがよくわかってきたから、企業の行動も変わってきたということでしょう。第三者視点でどう評価されるか、配慮するようにアングルが変わってきています。5年ほど前は、「私たちはこうありたい」と表明するのがもっぱらでしたが、今は「社会全体で求められている姿」にいかにして近付いていくかを表明するというふうに発想が変わってきています。
潮目が変わったポイントはいくつかありましたが、直近の日本においては、特に菅義偉首相が2020年10月26日に国会で行なった所信表明演説の中で初めて「2050年までにカーボンニュートラル(二酸化炭素ネット排出量ゼロ)にする」との政策目標を掲げたことも大きなインパクトになっています。
一方、世界を見回すと、EUでは長く気候変動に対するアクションを訴え実践してきた経緯がありますし、米国でもバイデン政権になって早々に「パリ協定への復帰」が発表されました。このように、世界各国ですでに気候変動対策への“抵抗勢力”はなくなりつつあります。間違いなく、これまでよりはるかに、経済も政治も気候変動対策を“当然”とする動きが加速していくでしょう。
茶谷: そうなると企業はますますマインドセットを変える必要がありますね。
足立: そう思います。ただ、私たち監査法人の立場から見ると、「透明性と正当性を担保したい」というクライアントの希望自体が変わることはないように思います。
変わる点としては、ESG(環境、社会、ガバナンス)の要素です。つまり、気候変動や人権問題、労働搾取の有無やダイバーシティの実践などの情報を社外に伝えるにあたって、第三者からの保証と“太鼓判”を求められている、ということです。
もともとアカウンティングファームであるKPMGは、会計のように数値で評価できる財務のサポートに加え、いわゆる非財務と呼ばれる分野、つまり貨幣価値で測定してこなかったことについても数値化する仕組みとサービスを提供することになると考えます。
非財務分野の価値の数値化の意義
茶谷: 非財務分野の価値を数値化する、という話が出ましたが、その意義はどういったものでしょうか?
足立: 「CO2排出量取引」を例に挙げると、その議論の際に「そもそもCO2排出量報告の信頼性の担保も必要だ」との指摘が出ますよね。また、M&Aの際に、「CO2排出量が多い企業を買収してもいいのか?」といった論点が出てくるようにもなっています。アシュアランス(保証)業務においてはその「示されたCO2排出量の信頼性の担保」という部分が注目され始めています。
全体で見ると、これまで財務情報が評価の上で重視されてきましたが、財務・非財務のどちらも同程度の重要性をもって評価されることになる、というわけです。

この背景には、金融業界のスタンスが深く関わっており、その根本にはPRI(責任投資原則)等のサステナブル・ファイナンスと言われる領域のイニシアティブがあります。機関投資家など資金の出し手がグリーンな企業やグリーンであることを良しとし、地球環境への高負荷状態が続いたり、労働搾取や児童労働のような人権侵害が起こっているいわゆるブラウンなビジネスには投資しない、という考え方を根本に据えるようになりました。「グリーンでなければ融資が受けられないどころかダイベストメント(投資撤退)すら行なう」という動きも活発です。
デンリ: 今までは社会や企業のアジェンダといえば「環境保全、地球にやさしく」という方向性でしたが、金融業界が一歩踏み込んだ意識改革をしたことで、バリューそのものが変化しているわけですね。PRIの存在感の大きさがうかがえます。
足立: 投資を行っている金融機関はすでに「PRIに署名しているのが当たり前」というほどになっています。おっしゃる通り、お金の流れの部分に働きかける、というやり方は非常にインパクトが大きいです。
今日のような転換期で、グリーンファイナンスやサステナビリティファイナンスといった言葉も浸透し始めています。このような大きな動きと密接に関わっているのが、「クジラ」と呼ばれる超巨大な機関投資家である年金ファンドの存在です。
彼らが運用する資産を預けている人の中にはミレニアル世代やZ世代が少なくありません。投資する期間がより長く、かつ、グリーンに投資する意向が強い彼らの意見は無視できず、投資家も企業も、その期待に応なければ事業継続がままならない、というわけです。
非財務分野の透明性と標準化の今後について

茶谷: 先ほど、「CO2排出量報告等への関心も強くなっている」との話が出ましたが、これが求められる背景とは何でしょうか?
足立: コロナ禍によって、人の移動という観点では“ボーダー”の存在を改めて意識することとなりました。しかし一方で、物流や金融やサステナビリティの観点では“ボーダー”が希薄化していることへの意識も強く持たされることとなりました。例えば、気候変動の原因と言われるCO2のほか、水資源や水質汚濁の原因などは、国境の概念には当てはまらないものです。
茶谷: 確かに、そういった物質をはじめ、物理的に動くものは厄介ですね。KITでもそれを測定するにあたって「データはどのようなものがあるのか?」と調査し始めたところです。データの種類や評価の仕方、フォーミュラーが決まっていないので扱い方を検討する必要がありそうです。
これまで重要視されてきた財務分野には約100年の歴史があり、様式やルールが共通化されています。一方、先ほども触れた通り、非財務の部分はまだそれが定かではありません。測定方法の標準化は必須の事柄だと思うのですが、現状ではどう考えられているのでしょうか?
足立: 標準化が必要である、というのは共通認識としてあります。例えば、何をもってCO2排出量とするかという基準が異なると、「日本ではこれでCO2排出量の取引をしているが、他国とその取引を行なう場合はズレが生じるので補正しなければならない」ということになってしまい、正しい取引はかないません。
ただ、非財務報告に関するデファクト・スタンダードもまだ決まっていない状態です。しかし、会計の世界にルールがあるのと同様に、非財務に関する報告のあり方もだんだん決まっていくでしょう。いまはその大きな流れの中にいる、と言えそうです。
そのように報告の基準が定まってくると、データの重要性が高まるのは間違いありません。私たちも、TCFDレポートを公開するにあたって、物理リスク(洪水や風水害ほか自然災害)を評価するにあたり、気象データや地形データなどを駆使して「if」によるシミュレーションを行なう取り組みを外部のパートナーと始めました。これによって、ある特定のエリアにおけるリスク度合いが科学的に明らかになると考えています。
また、気象データによって気候変動リスクを今まで以上に科学的に測定するといった取り組みはすでに始まっています。これはまさにテクノロジーによって非財務分野の情報を補完するアクションだと考えています。
他方、CO2排出量の測定については、CCS(二酸化炭素の回収と貯留)のように、今まで想定しえなかったテクノロジーの登場がこれまでの考え方を変える、という出来事も起こっています。このように、測定方法が確立されたとしても、その考え方を根本から覆すような技術が出てくれば……追いかけっこになっていく部分はあるのかもしれません。
データドリブンはサステナビリティの実践を支える
茶谷: テクノロジーの発展が測定方法やルールを変えるきっかけになる、というのは、100年の間ほとんど変わらなかった会計の歴史との大きな違いですね。
足立: そうですね。非財務の分野でも基本の部分にはデータドリブンの発想があります。つまり、ファクトからスタートする、という点が仮説からスタートする伝統的な手法との違いだと言えそうです。だからこそ、これからは、過去から多く蓄積された自然に関するデータを組み合わせたファクトから、「それをどうやったら使えるか?」を考える必要があるでしょう。
ある特定のモデルから異変や不正などを推察する会計のメソッドは環境分野でも応用できるかもしれません。しかし、いずれの分野でもパラダイムシフトが起こると過去のモデルが必ずしも当てはまらなくなることが度々起こり得ます。ファクトから始められるというのはその課題を克服できるかもしれない、ということでもあります。

他方、ESG領域についてこれまで接してきた中で感じたのは、意外にも「やり方がトラディショナルな部分がある」ということです。だからこそ、「科学的であること、科学的根拠があること」が推奨されるようになってきたこの領域にデータドリブンの発想を持ち込みたい、と考えています。
茶谷: KITのラボでもその部分に強い関心を持っています。温暖化の影響ひとつとっても、これまでは気象などのデータを大量に分析しなければ科学的な見方はできませんでしたが、今は処理能力が上がり、それが広範囲のエリアに対してもできるようになっています。
足立: そうですね。ただ、先ほども触れた通り、そうした分析を我々がやろうとすると既存のやり方や考え方を踏襲してしまう可能性があります。しかし、本来ならデータファーストで新しい発想のもと取り組まなければならないものだと感じています。
茶谷: 近年、AIはアルゴリズムから答えを導き出すスタイルから、データからアルゴリズムを導くやり方に変わってきました。共通のインサイトや特性を見抜くようなセンスが求められるようにもなっています。
足立: データを分析してファクトからスタートする事でおもしろいのは、前提条件や事前の知識等がない、何も知らないイノセントな発想の方がうまい解決法を見つける場合が多いところです。
専門性の高い人たちを集めてアイディアを与え、高い知見を活用してもらえれば、まだ発想すらできなかったことにも問題提起と解決が起こりうるのではないか、と想像しています。
茶谷: 「unlearn」という言葉がありますが、すでに知っていることを忘れて何かに取り組むことは、発想を生み出すために大事なことなのだと思います。そういう意味では、KITにはテクノロジーやデータ分野の専門家ではあるものの、サステナビリティ分野についてはフレッシュな目線で見られる人材がいるので、共同で何かできるような気がします。
足立: これまで培ってきた知識や経験を無視することは想像以上に難しいことです。例えば私は会計の分野に長く身を置いてきたので、その分野から離れて考えることは難しいものです。しかし、最近はひとつの知恵や知識で対応するよりも、多くのそれを持ち合って共同で取り組んだ方がいい、という発想が一般的になってきています。批判的検証をしながら、よりいいものを育てていきたいですね。
KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。