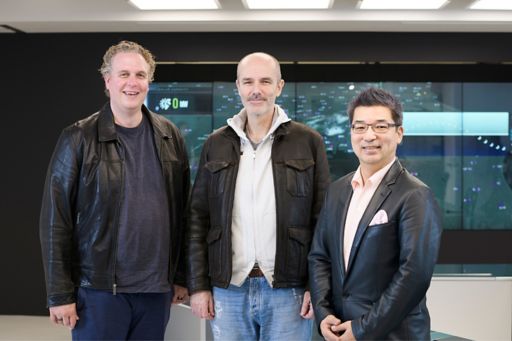大きな期待と不確実性への不安が入り混じるポストコロナの時代。企業経営においては、変動の予兆や暗黙知の変異を察知し、不連続な変化を乗り越えていくためにデータドリブンな「デジタル経営」へと舵を切ろうとする動きが出始めています。
では、本当の意味でデジタル経営がニューノーマルになった場合、会社経営はどのような姿になるのでしょうか? 本稿では、KPMG Ignition Tokyo(KIT)の茶谷公之とティム・デンリに加え、ストラテジーオフィスヘッド ディレクターである張 駿宇の3名の鼎談をご紹介します。
透明性を高めることと不確実さを受け止めることのバランス
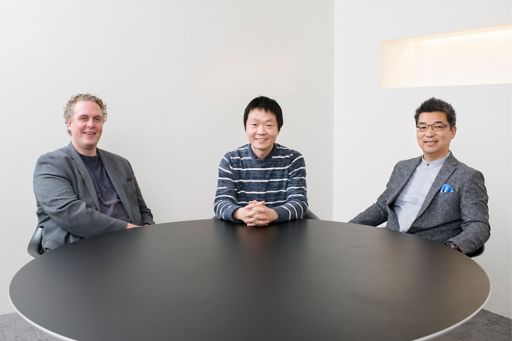
(株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(右)、同ストラテジーオフィスヘッド ディレクター 張駿宇(中央)、同取締役 パートナー ティム・デンリ(左))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。
茶谷: 今回、張 駿宇さんに「デジタル経営の最前線」を空想・妄想する議論に参加してもらったのは、KITの創立、設立の準備で主要な役割を担っていただいたからです。
デンリ: KITに限らず、新しい組織を立ち上げる際、一番重要なのは「組み合わせの妙」だと思います。割と何でも前のめりにやっていく感性の人と、「いやいやちょっと待って。これは状況を整理してジャッジする必要があるぞ」というふうに考えて対処する論理の人とが噛み合わなければならない。後者の存在は特に大事ですね。茶谷さんも私も、前者のいわゆる感性の部分が強いので、張さんのように、組織設立で「ちゃんとやらないといけないところ」を一手に引き受けてくれる存在はとても頼もしいものです。
さて、組織の立ち上げという話が出たので、今の日本企業が抱える「言葉の問題」について少し話せたらと思います。
私たちテクノロジー寄りの人間は、テクノロジーの力で組織内の「透明性を高める」といった言い方をしますが、同じことについて、経営側の人たちは、テクノロジーの力で「稼働を見る」といった言い方をすることがあります。立場によって意味するところや表現が微妙に異なるのはどこででも起こる事柄なのでしょうか?
茶谷: IT部門と事業部門、管理部門とあった場合、この3つの部署が違う言葉を使っていて、重要視していることや価値観が違ったり、何かあった時に最初に気になる場所が違うので、何となく歯車が噛み合わない、ということが起こるのではないでしょうか。
張: そうですね。伝統的な日本企業で新しいテクノロジーの導入の際は特に、「過去と未来の間の繋ぎ」が必要なのだと思います。いわゆるトラディショナルな経営をやってきた立場と、将来何をやっていくかというビジョナリーなことを妄想・空想する立場とでは、お互いを理解し合わないと結局のところ変わらないのではないでしょうか。
確かに「透明性」を高めることは技術で可能です。例えば、企業では決算処理をして年度で経営のフィナンシャル・レポートを出すわけですが、リアルタイムでデータを現場から全部吸い上げられるなら、年度ごとではなくもっと早く状況を正確に把握して内外に発信できるので、透明性は高まるでしょう。今はそのことをトラディショナルな経営をやってきた立場の人に見せて、説得することが重要になっているのだと思っています。
茶谷: 一方で、過去の成功したプロジェクトの多くは、実はトップの人たちがあまり透明性を高めず、あえて見えないところに切り出してそこで育成する、というやり方を採っているケースが多く知られています。「いろんな人がいろんなことを言ってきて潰されないようにこっそり進める」というイメージです。
デンリ: 今の茶谷さんの話で、最近東大のある先生からうかがったホンダジェットのエピソードを思い出しました。本田宗一郎氏が始めた飛行機製造に関するプロジェクトなんですが、やはりずっと守られてきて、だからこそ今になって凄く発展したというわけです。
張: きちんと将来像を見据えた上で「戦略的にあえて隠す」ようにしているかどうか、ですね。ただ、やはり人にとって不確実性や不透明であることはどうしてもある種の気持ち悪さを感じてしまうものです。特に、日本の確立された会社の経営陣からすると、「石橋を叩いて渡る」というカルチャーが強いので、そこをどうやって乗り越えるか、受け入れてもらうか、難しいところです。
茶谷: そうですね。ただ、やはり論理的に組み立てられるものは結局のところみんな同じ答えにたどり着いてしまうものです。だから、なかなか差別化ができなくなる、というジレンマに陥ってしまいがちです。みんなが分析して、ロジックを組めば組むほど同じような方向に進んでしまう…。
デンリ: 本当に優れた成功をする経営者は論理ではなく、「アート(芸術)」の領域なのだと思います。
もしかすると、テクノロジーの発展もそうした傾向があるのかもしれません。例えば、VRやARの技術を見て、「今ははっきりは論理付けできないけれど、これそのものはそんなに発展しないような気がする。だけど、AR・VRの裏にある技術は何らかの形で発展するかもしれないな」という感覚です。
GAFAはなぜ個性的な事業構造なのか?
茶谷: 経営者の「アート(芸術)」の話がでましたが、会社としての個性の話もしておきたいですね。張さんが社会人になるころの大企業と言えば、銀行や商社が名を連ねていたと思うのですが、今ではそのポジションはすっかりGAFAのような企業に替わってしまっています。そして、みんな個性的に見えます。
GAFAはよく「IT企業」と一括りにされますが、テクノロジーは使っているものの、同じプロダクトを作っているわけではなく、GoogleもAppleもFacebookもAmazonもそれぞれ実は全く違った業態です。技術ベースでありコンピューターを使っているなどの共通点はあるけれど、やっていること自体は異なります。GAFAに限らず、中国の百度(バイドゥ)やアリババもそうですね。
こうして見ると、人間が主体になっている企業はむしろ際立った個性を出しにくい、と言えるような気がしています。人間は一人ひとり違う存在だけれどもそれなりに似通っている部分もあります。一方で技術の方はいくらでも加工のしようがあるものです。それができるから、個性的な事業構造にしやすいのではないか、と想像しています。

デンリ: 所属する人間に紐づく文化の継承の有無も影響していると思います。これまでは、「この企業にはこういう系統の人が来て、同じような個性をもって、同じような基礎から成長していく」ということがありました。
茶谷: 確かに、日本企業の場合、就職に際して「大学の●●ゼミから紹介される」というルートがあったので、毛色が違う人が入ってくることは少なかったのかもしれません。
デンリ: 他方、例えばテスラ社のイーロン・マスク氏は、「今の産業は地球を破壊している。今後はサステナブルでなければならない」というコンセプトを掲げて電気自動車のビジネスをしつつ、その横で、「事業が地球を救うことにならないなら、スペースエックスで宇宙に出る」という凄く分かりやすいビジョンを示しています。
また、Googleは、「Don’t be Evil」という高尚な目線から事業をスタートさせています。AppleやFacebookにも社会的存在意義があって、それに基づいて会社のプロダクトやサービスが生まれ、共感した人が集まるという流れになっています。これらは今までの企業とは明らかに性質が違うと感じます。
張: 先ほど、組織立ち上げの際に感性の人と論理の人がいる、という話が出ましたが、論理の部分はいずれほとんどがAIや機械学習でカバーできるようになると思います。一方で、存在意義や感性の部分は、そうはならないのだと思います。
この議論をする時、私はいつも「植物を育てる」というイメージを思い浮かべるのですが、同じテクノロジーでも、違う国や違う文化、違う社会や違う組織でそれぞれ異なる“花”を咲かせるんですよね。それは経営のさじ加減の結果ではないでしょうか。
茶谷: 植物の例で言うと、ひとつの種だけを植えて成功する、ということはあまり考えられませんよね。いくつも植えてみて、伸び始めたものを残し、育てていく。これはいわゆる積極的二重投資に繋がるのですが、そうしたことを許容しなければいい結果は得られないと言えるでしょう。ひとつの種だけを植えて、「これを絶対に咲かせるぞ!」と言ってもそうなるとは限りません。
張: そうですね。そして、種が果物になるのか、野菜になるのか、どんな姿に成長するか分からないとしてもビジョンを持って育てていく必要があるのだと思います。
経営会議は「社長ひとりでAIが5人」になる時代が来るかもしれない

茶谷: 今、論理性はほとんどがAIや機械学習でカバーできるけれど感性の部分は人が担う、という話が出ましたが、そうなると「社長は人間ひとりで、5人くらいのAIが補佐に付く」といった経営会議が現実になるかもしれませんね。
張: 社長とAIが話し合いながら会社の今後を決めていく、という経営の姿でしょうか?
茶谷: そうです。AIのほうがデータアクセスのスピードが早く、アクセス可能なデータ量も多いので、社長が尋ねたことにすぐ答えを返せるでしょう。人間だと「ちょっと調べます」と持ち帰ることもありますが、AIにはそれがありません。そのため、ビジネスの展開がだいぶ早くなる可能性があります。
また、人間だと何となく記憶していたことや勘と経験で「こんな感じです」と言っていたことも、AIはファクトベースで判断できるので、社長の決断の精度は上がると想像できます。
そうなると、大企業の定義が変わるかもしれないですね。もっと大きな会社は小さな会社に分散していくかもしれません。小さな単位で事業を推進していて、社長ひとりとAIたちがやっているようなユニットを大企業として運営する、ということも起こるかもしれません。
デンリ: まさに私が考えているエコノミック・コミュニティはその姿です。今は企業というと「大企業」という先入観があり、いろんな部門部署、事業が一緒になってやっている、というイメージですが、それが分散されて、それぞれの深い専門性で一緒になって成り立つような姿が、たぶん今後の会社であり、社会のあり方なのではないでしょうか。
まるで中世のギルドの時代のようになる、と想像します。
茶谷: ギルドの時代を経て、産業革命以降は大企業化して、再び分割する、ということですね。
デンリ: 大企業として組織だっていた理由は、ある意味、品質の担保や効率化のためだったのだと思うのですが、分散しても同じくらい、あるいはそれ以上の効率や品質を提供できるようになると、自然と分散していくようになるのではないでしょうか。
そして、それが技術によって、今の世の中で実際に起こりつつあるのだと見ています。この先ますますAIが発展すると、分散している企業同士が人間同士の繋がりではなく、コンピューターの繋がりによってくっついていくようになると見通しています。だから分散されることで可能性が広がるし、逆に言うと分散されないと成り立たない、という世の中になっていくのではないかと私は考えています。
茶谷: 社内のことを詳細に知っているAI同士が相談して商談を決めるケースも増えていくかもしれませんね。
人間同士だと、企画発案者が10の事業部の10人に話を持っていかなければならない、となった時、だいたい「話しやすい人」から始めようとするものです。そうすると一番苦手な人は最後になってしまう…。その点、AIだと、一瞬のうちに相互にデータの照会をパパっとして調整などが早く終わる可能性が出てきます。
張: 会話や交渉の部分は全部機械に置き換わって、その先にある「人間がやるべきこと、人間にしかやれないこと」をやるようになる、という感じですね。
茶谷: コンピューターは良くも悪くも、ニュートラルですし、24時間働けますからね。
デンリ: ビジネス展開のスピードは格段に上がりそうです。しかし、それだけでなくリスク管理にも繋がると思います。大企業になる理由のひとつに「リスクを低減させる」というものがありますが、今までの社内のリスクのほとんどは人間に起因していると考えられるのではないでしょうか? 勘違いや相互の認識のズレなどがまさにそれです。
しかし、コンピューターになるとそのリスクは低減できるはずです。当然、AIが正しく動いているかどうかを別の形でモニタリングしたりコントロールしなくてはなりませんが、それがコントロールできる「AIインコントロール」が発展していくと、会社と会社の間、あるいは部門と部門の間のリスク管理がしやすくなるんですよね。だから分散もされやすいと考えます。
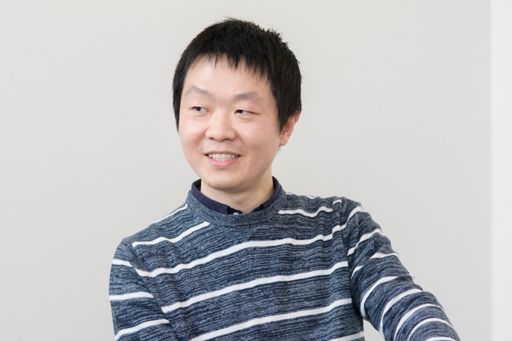
茶谷: 一方で、会社があまり小さくなるとリスク分散が難しくなるおそれも出てきます。フォーマビリティ(成形性)を高めるのはリスク分散という側面もあるでしょう。そこはどう解決できるでしょうか?
デンリ: それこそ、「透明性」の出番でしょう。透明性が上がることによって、見えなかったリスクが見えるようになります。そこはまさにAIが見つけ出す役割を担うのだと思っています。
つまり、もしAI同士で“商談”して協業や協力を進めるかどうかを決めるとなったら、「ここと一緒に事業にチャレンジしたら、このくらいのリスクが想定される。一方、こちらと取り組んだらこのくらいのリスクになる。リスクのタイプはこんな感じです。あとは判断してください、社長」というふうになるのではないでしょうか? そして、その社長の判断をもって事業が進んでいくのだとしたら、経営者の姿は今と随分違ったものになると思います。
茶谷: そんな時代には、事業のレイヤーとインフラのレイヤーに二極化するかもしれませんね。
デンリ: 事業のレイヤーはある意味で職人に近い存在になると思います。
張: そうした社会になるためには、社会全体の仕組みを変えなければいけませんね。AIの管理やデータセキュリティーのほか、個人が失敗した時にどんなセーフティネットを用意しておくのか、これは民間の範囲ではないかもしれません。
デンリ: そうですね。社会の方の変化はすでに今話したことが始まっています。例えば、シリコンバレーのスタートアップたちは、新しいサービスを考えた時、「決済機能が必要だから、その分野が得意なスタートアップと組もう」とします。そういった姿が増えていくのだと考えます。
張: ある意味で、提供するバリューが変わる、ということなのでしょう。機械ではなく、人間にしかできないことを提供する、という話です。
茶谷: 当然、人間同士のネットワークも作用しますけどね。だから、冗談みたいな話ですが、AIが“お酒を飲めるようになる”と強いかもしれません。
デンリ: そんなふうに気軽な存在になるのも遠い未来のことではないかもしれないですね。だから、私たちが変化していかなければなりません。注意しておきたいのは、「自分たちが思い描いている変化より、その変化の度合いが圧倒的に大きい」ということです。
一方で、それが現実になるまでには、10年、20年、30年、50年かけて、徐々にという距離感や速さだと思います。シンギュラリティーを信じるとするなら、物凄い変化ですからね! 人間とコンピューターが融合することすらあり得るのでしょう。
茶谷: AIの能力は、特定タスクについてはすでに人間の能力を超えています。だから、人間を超えない、ということはないのでしょう。ただ、人間からAIに置き換わるかというと、それもちょっと違うように感じます。
張: では、AIがAIを作り出すというのは?
茶谷& デンリ: それはあると思いますよ!
デンリ: 私の夢なのかもしれませんが、コンピューターの性能を、人間のできないところを越えるために使う、という発想はあってもいいのではないでしょうか?
張: 人間の拡張みたいですね。こんな話をしていると、いつも自分の子どもと話すときに困っちゃいます。将来何を目指すか、そして、今学校で勉強しているものはどれぐらい使えるか、という問題です。学校は一生懸命「論理」の世界を教えようとしていますが、これは10〜20年後には使えないと考えられるので、いずれ凄く困る世代が出てくるかもしれません。
デンリ: それはあると思います。特に、日本の文化でAIを見るのと、海外の文化でAIを見るのとでは随分違います。ロボットに対して、日本では友達だったりヒーローだったりと、助けてくれる存在としてイメージされることが多いですが、米国の場合は脅威になる存在とみなされがちです。その捉え方の違いは結構奥が深いでしょう。制御しなければならないものなのかどうか、という考えが根本にあるかないか、の違いに関わるからです。
茶谷: 今後、デジタル経営を本格的に推進していくなら、AIやロボットの進化の方向性と、それらが活躍する社会に必要な仕組みはおもしろいテーマになりそうです。
KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。