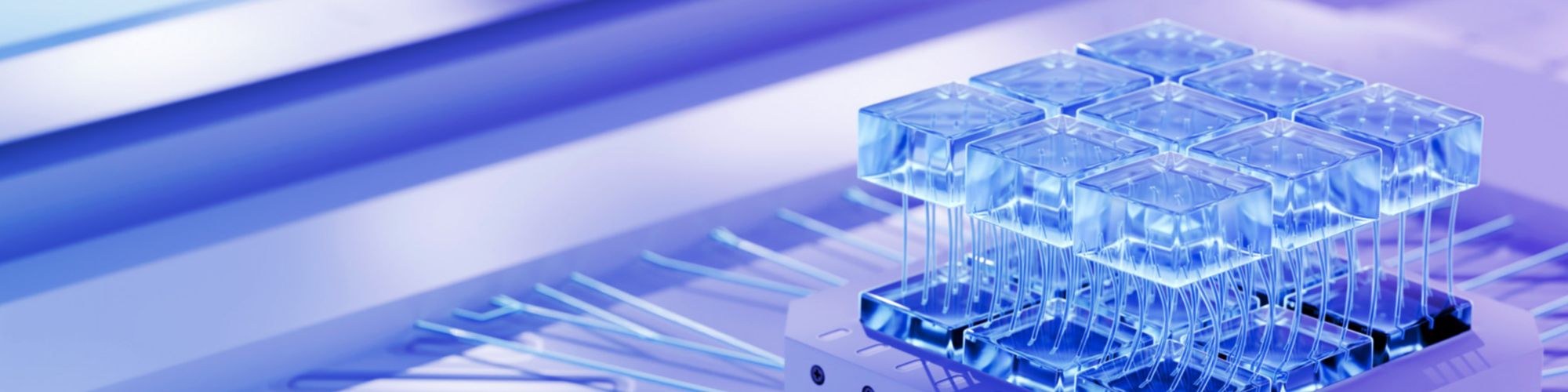1.量子コンピューティングの課題
量子コンピュータは、量子力学の原理を応用した次世代の計算機だ。従来のコンピュータ(古典コンピュータ)とは計算の仕組みが根本的に異なっており、大きな数の素因数分解を必要とする暗号解読や膨大な組合せの中から最適解を導く最適化問題などの複雑な計算を高速で実行する。そのアイデアそのものは1980 年代にノーベル物理学賞受賞者でもあるリチャード・ファインマン教授をはじめ、さまざまな研究者たちが提唱しはじめ、2000年代には多くの組織がハードウェア開発に挑戦してきた。
しかし、量子コンピュータというキーワードがビジネスの現場で聞かれるようになって久しいものの、永らくその商業的インパクトは限定的だった。量子コンピュータの特性上、計算誤りが古典コンピュータよりもはるかに高い確率で発生するという点が理由のひとつだ。完全な誤り耐性(フォールト・トレラント)量子コンピュータはまだ限定的な規模に対応するものが実現しているにとどまり、現状は限られた範囲内での実験的利用が中心だ。どの分野に、いかに導入すればROI(投資対効果)が確保できるか、ビジネスモデルが未確立かつ不透明だったことも否めない。量子の時代はまだ遠い未来だと感じているビジネスリーダーも少なくないだろう。
図表1:量子コンピューティングの3つのアプローチ

2.量子の時代はすでに始まっている──すでに使える量子的アプローチ
しかし、状況は確実に変わりつつある。鍵のひとつは、未成熟な量子コンピュータを補完する手段である量子インスパイアード最適化(Quantum Inspired Optimization、以下「QIO」)だ(図表1)。QIOは、量子力学の原理や量子計算の発想を古典コンピュータ上で実行する最適化手法を指す。量子コンピュータの商用化が進んでいない現状において、QIOは量子技術の恩恵を先行的に享受する限られた手段のひとつといえる。量子コンピュータの登場を待たずとも、既存の古典コンピュータで量子的なアプローチを実現できる橋渡し技術として、すでに金融や創薬をはじめとしたさまざまな分野で意思決定の高度化に貢献している。たとえば、日本の量子コンピュータ企業である株式会社エー・スター・クォンタムは、QIOを活用して配送の最適経路計算に取り組み、移動距離、稼働台数、CO2排出量などを最小化する配送ルートを高速で算出するなどの成果を上げている¹。
KPMGもグローバルで企業の課題解決に取り組んでおり、金融業界ではポートフォリオのヘッジ戦略を最適化し、10%のVaR(予想最大損失額)を改善。通信業界では、アンテナ配置最適化でコスト10~15%削減、計算処理を40倍高速化に成功するなど、すでに幅広い業界の課題解決を促進している(図表2)。
図表2:KPMGの量子コンピューティング事例

出所:KPMGインターナショナル「Quantum Dawn」を基にKPMGジャパン作成
3.世界と日本の現状
量子コンピューティング分野では、ドイツやオランダなどの欧州諸国が大学・研究所を軸とした学術クラスターで強みを発揮し、産業連携型の応用研究でも成果を挙げている。米国はスタートアップを含む民間投資が活発で、巨大IT企業群も主導的役割を果たしており、研究から産業化までのエコシステムが確立しつつある。また、中国は政府が量子情報科学国家研究所をはじめ、研究機関や企業に150億ドル超の資金投入を行っていると推定され、投資規模の面では米国をも凌ぐ。こうした動きは、量子技術をめぐる国際競争が急速に激化していることを示している。
日本は1990年代から量子アニーリングや超伝導量子ビットなどで先駆的な研究成果を挙げ、基礎理論と実証の両面で国際的に評価されてきたものの、激化する国際競争の中で存在感をさらに高めていくことが求められる。特に懸念されるのは社会実装・産業実装、人材育成での遅れだ。内閣府は、Society5.0の進展を加速するなかで、2030年までに「国内の量子技術の利用者を1,000万人に」「量子技術による生産額を50兆円規模に」といった目標を掲げている²。
4.今こそ「量子の準備」を始めるとき
かつてのスマートフォン、あるいは昨今の生成AIの登場時のような、産業構造やビジネスモデルを根本的に変える転換点が量子技術にも訪れるのか──社会への量子技術の浸透について、KPMGコンサルティングの馬場功一パートナーは、「誤り耐性が実装される2030年前後がポイント。社会実装は急速に進む」と見る。
また、量子コンピュータの性能向上は、現在広く利用されている公開鍵暗号(RSAやECCなど整数因数分解や離散対数問題に依存する方式)の安全性に将来的なリスクをもたらしている。この脅威に備えるため、米国政府は2022年の国家安全保障覚書第10号(NSM-10)において、連邦機関に対し量子耐性をもつ暗号システムへの移行準備を指示した。これを受け、NSAはポスト量子暗号アルゴリズムに関する方針を策定し、NISTは2024年に3種類の標準規格を公表している。米国のロードマップでは、2030年代を目途に公開鍵基盤を耐量子計算機暗号(PQC、Post-Quantum Cryptography)へ全面移行することを想定しているが、できる限り早期の導入が推奨されている。
自社ビジネスのどの分野で価値を生み出せるか、いかにROIを確保するか、そしていかに量子安全性を確保するか。短期的にはQIOや多大な追加投資の必要なくクラウド経由で量子技術を応用できるQaaS(Quantum as a Service)の活用(図表3)を検討したうえで、中・長期的(2〜5年)には投資対効果が明確な初期ユースケースに優先的に取り組むことが重要だ。
そのためには、「リテラシー教育」と「ユースケースの探索・評価」が不可欠である。量子技術に対する理解が社内で十分に醸成されていない場合、未知であること自体に過剰な忌避感が生まれ、導入リスクを過大に見積もる傾向が強まる。これは、合理的な意思決定を妨げる思考停止にほかならず、結果として技術革新の機会を逸し、競争力を損なうリスクを伴う。まずは量子技術に関する社員教育・社内理解を促進し、そのうえで、国内外の先進的なユースケースを幅広く探索・評価し、量子技術が真に価値を発揮する課題領域や潜在的リスクを見極めておくことが、社会実装の潮流に乗り遅れず、新たな競争優位を創出するための戦略的な布石となるだろう。
図表3:進化するQaaSエコシステム

出所:KPMGインターナショナル「KPMG 2025 Futures Report」を基にKPMGジャパン作成
参考資料:
1. KPMGジャパン「複雑な社会課題を解決する量子コンピュータの未来-『次世代ビジネスを牽引するテクノロジー最前線』」
2 内閣府 統合イノベーション推進戦略会議「量子未来社会ビジョン」
監修
KPMGコンサルティング
執行役員 パートナー
馬場 功一
執筆
KPMGアドバイザリーライトハウス
ストラテジー&ビジネスオペレーションズ
マーケティングリード 品田 洋介