2024年4月1日以降開始事業年度より法施行されたBEPS 2.0 Pillar2 グローバルミニマム課税制度。しかし、米国の第2次トランプ政権は早々に離脱を発表しており、国際協調から一転、各国独自の規制強化の時代へと変化しつつあります。「税制のグローバル化」が判然としない複雑な状況になっている今、日本のグローバル企業はこの変革にどのように対応し、どのような税務ガバナンスを構築すべきなのでしょうか。
本対談では、国際租税法研究の第一人者である政府税制調査会委員一橋大学大学院法学研究科教授吉村政穂先生とKPMG税理士法人代表の宮原雄一が、混沌とする国際税制の現状・課題と企業の対応策について掘り下げます。

吉村 政穂 氏
一橋大学大学院法学研究科教授 KPMG税理士法人顧問
一橋大学大学院法学研究科(ビジネスロー専攻)教授。東京大学法学部卒業、東京大学助手、横浜国立大学准教授等を経て、現職に至る。法人税、国際課税など、企業課税の分野を専門とする。研究の傍ら、政府税制調査会委員、総務省地方財政審議会特別委員などを務める。
税務ガバナンスの本質は税務ポリシーの「設定とモニタリング」
宮原
これまで私どもKPMG税理士法人は日本企業の皆さまに対して、税務ガバナンス体制の構築と強化が必要だと、セミナーやさまざまなコンテンツを通じて訴求してきました。しかし、日本企業はどちらかというと納税額の大きさ自体が会社のステータスである、あるいは社会貢献であるという考え方をお持ちの場合が多く、納税額の削減を企図すること自体に抵抗感があるケースが多いように思われます。
今後、海外で国内企業が欧米企業と戦っていくために必要不可欠なのは、一部の米国企業が行っているような法律が想定していない国際的な節税策ではなく、集中管理された税務ガバナンスを構築すること。そしてその仕組みや体制を「不必要な税金は支払わない」という姿勢で維持し続けることだと私たちは考えています。企業経営における税務ガバナンスとは何か、どう捉えるべきか、吉村先生のお考えをお聞かせください。
吉村氏
確かに税務ガバナンスの強化というと、「節税や過度なタックスプランニング」のイメージが先行することもあるかもしれません。しかし、本来は経営者として税務に対するポリシーを設定し、それが実行されているかをモニタリングすることが、企業における税務ガバナンスの本質と考えられます。
企業によって、節税策を追求することもあれば、コンプライアンス重視で保守的なアプローチを取ることもあります。いずれにしても、経営者が税務に対してどんなスタンスで臨むのかが重要であり、仮に税務ポリシーを明確に設定していない企業があれば、そのこと自体、大きな問題だと思います。
宮原
税務ポリシーの「設定とモニタリング」こそが、税務ガバナンスの本質ということですね。一方、企業経営において、税務ガバナンスは今後どのような役割を果たしていくとお考えですか。
吉村氏
前提として、適正な納税は企業と株主の関係において重要です。それはコンプライアンス重視を求める面もある一方、必要以上の税金を支払うことも株主の利益を損なうことにもなるからです。タックスプランニングについても、どの程度リスクを取るのか、会社としてどのようなリスク許容度で税務に取り組むのかを適切に設定し、株主に示すことが重要です。
加えて、近年は税務行政の文脈で税務ガバナンスの整備状況が注目され、EUやオーストラリアのように税務情報の開示を求める動きも出てきています。これは広範なステークホルダーである社会、政府からの税務ガバナンスに対する要請が高まっていることの現れです。
このように税務ガバナンスは単なるコンプライアンスの問題ではなく、企業の持続可能性や社会的責任にも関わる重要な経営課題となっています。その意味で、経営者層のコミットメントと理解が不可欠なのです。単に税務部門だけの問題として捉えるのではなく、全社的な取組みとして位置付ける必要があると考えています。
税務行政のDX化と国際化によりリアルタイム課税時代へ
宮原
昨今のEUやオーストラリアでの税務情報開示要求は、BEPSの流れと関連しているのでしょうか。また、こうした国際的な動向が日本企業に与える影響はどのようなものでしょうか。

宮原 雄一
KPMG税理士法人 代表
1990年KPMGピートマーウィック(現KPMG 税理士法人)に入所後、2002年より3年間、KPMGシリコンバレー事務所に駐在し、日系企業に対して米国税務アドバイザリー業務および駐在員に係る米国個人所得税の申告業務等を担当。2014年にパートナーに就任し、2022年1月KPMG税理士法人代表に就任。クロスボーダー取引に係る国際税務サービス、多国籍企業の人事部に対する税務アドバイザリー業務に豊富な経験を有する。
吉村氏
日本では表立った動きはあまりありませんが、税の公平性を議論する前提として、企業がきちんと税金を納めているかという問題意識が存在すると思われます。
実際、EUでは顕著に現れています。2013年頃、一部外資系企業がEU諸国でフェアな納税をしていないという報道がなされました。本件はのちに社会運動を引き起こすほど反響を呼び、「自国で利益を上げているのであれば、きちんと税金を納めるべきである」という市民の声はEUをはじめ、海外でますます大きくなっています。
BEPSはこうした社会的な要請と各国政府の財政的な必要性から生まれたもので、税務情報の開示要求はその延長線上にあると理解できます。日本企業にとって、これまであまり意識してこなかった税務の透明性や説明責任という観点が、一層重要になってくると考えます。特にグローバルに事業展開している企業にとっては、フェアという観点から、各国の税制に対応することが経営上の重要課題となることは間違いありません。
宮原
2013年当時と比較すると、今はテクノロジーの進歩により情報収集や共有が容易になっています。DX化は企業よりも行政側の方が進んでいるように感じますが、「税務行政のDX化、国際化が進む」ことについて、現状と吉村先生が見据えていらっしゃる未来像をお聞かせください。
吉村氏
企業も行政もグローバル化とDX化という2つの課題に取り組んでいます。日本企業が多国籍企業の世界展開に伍していくためにはグローバル化が必要であり、収集された情報を適切に活用するにはDX化が不可欠です。また、税務行政にとってもグローバル化とDX化が好循環を生み出す要因となっています。
将来的に、日本の税務当局は企業の取引段階の情報をリアルタイムに取得することを視野に入れていると考えられます。世界に目を向けてみると、付加価値税においては、E-invoiceが企業から取引先に発行される段階で、同時に税務当局にも情報が伝達される仕組みが、韓国やEUで推進されています。これは税務調査の在り方を根本から変える可能性を秘めています。
従来、税務当局は納税申告後に情報を入手して対応するというプロセスでしたが、今後は企業の取引段階で情報が蓄積され、課税期間終了時に税務当局の保有する情報と企業の情報を照合するという形になると予想されます。所得税や法人税については、お金の動きの性格付けや取引が行われた場所など、複雑な判断が必要になるため、事後的視点も引き続き重要です。しかし、付加価値税などにおいては、将来的には日本国内でもリアルタイムに付加価値税の納税・還付が実施される可能性があります。
このような変化は税務実務の根本的な転換を意味し、企業側も対応のための準備が必要です。特に情報システムの整備やデータの質の確保、税務専門家と情報技術専門家の連携などが重要な課題となるでしょう。
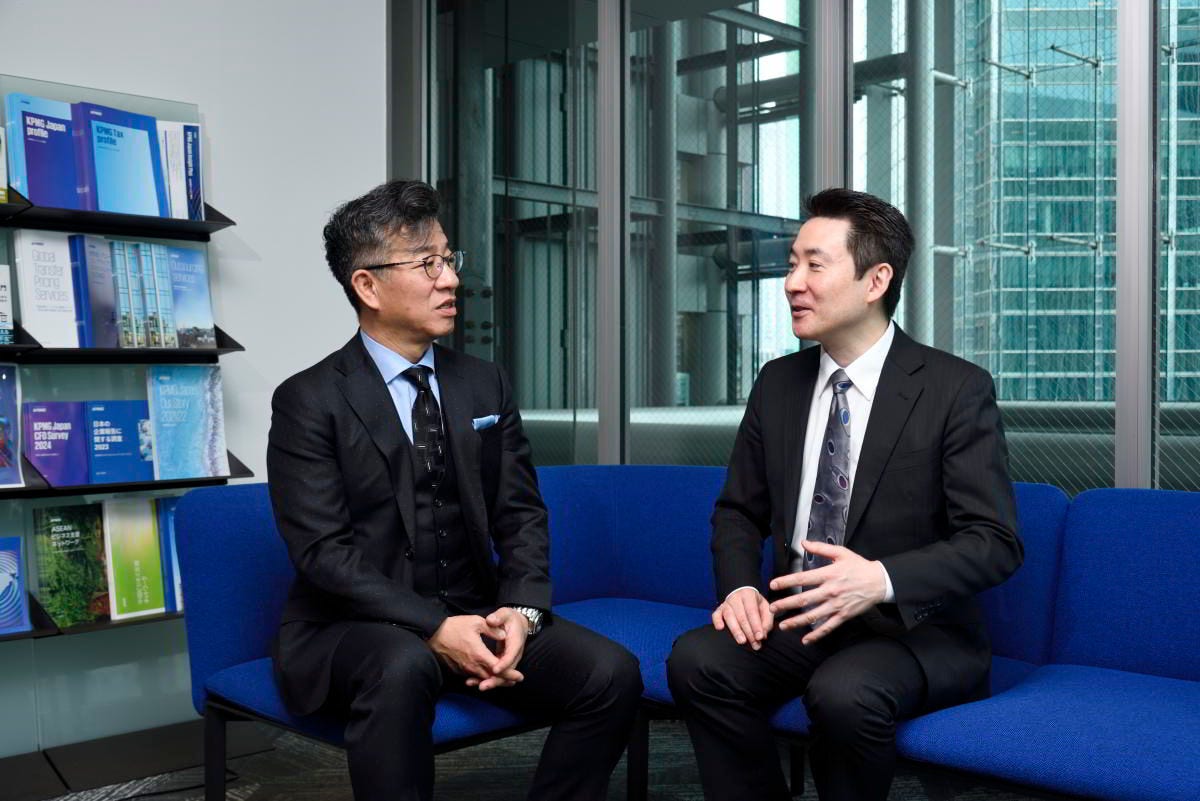
「後手の税務」が経営リスクの一因に。税務情報を先取りできる仕組みが不可欠
宮原
ありがとうございます。吉村先生がお感じになっている未来を想像しますと、「税務情報の先取りが重要になってくる」ことが色濃く見えてくるように感じました。
吉村氏
おっしゃるとおり、これまでは取引完了後の事後処理として税務部門が位置付けられ、適正な申告を行うための調整役としての役割が中心でした。しかし韓国やEUのような税務情報のリアルタイム連携を視野に入れた動きに対応する必要がありますし、企業内においても、取引段階から将来を見据えて税務部門が協働することが有益です。各国の規制動向への適時適切な対応という観点からも、先見的な姿勢の重要性が増しています。税務情報の先取りができれば、まず税務リスクの早期発見と対応が可能になります。潜在的な税務リスクを取引段階で特定できれば、事後的な修正や追徴課税のリスクを大幅に低減できます。また、企業価値のみならず、経営判断の質の向上にも寄与します。たとえば、M&Aや新規事業展開などの重要な意思決定において、税務面での影響を事前に分析しておくことで、より税効率的な判断が可能になります。さらに、税務当局との関係改善にもつながる可能性があります。適切な税務ガバナンスを持つ企業として信頼を得ることで、税務調査の頻度や深度が軽減されるケースもあります。こうした多面的なメリットを企業経営者が理解することから、税務ガバナンスの意識醸成は始まるのだと思います。
宮原
税務ガバナンスによって補強されるメリットとして、税務サプライズを未然に防ぐことが挙げられます。たとえば、海外企業を対象としたM&A。日本企業は事業主導で買収を進めることが多いので、税金の議論がどうしても後回しになりがちです。最終段階で高額な税がかかることが初めてわかって、それでも後に引けないケースは往々にしてあります。取引が始まるタイミングで税務のスクリーニングをかければ、こういったことは防げるはずですよね。

吉村氏
しかも、取引段階から丁寧に見ていかないと後で思わぬ課税になるリスクは、日本のほうが他国の多国籍企業よりも大きいかもしれません。タックスヘイブン対策税制のように、海外取引であったとしても日本で合算をして課税をする可能性を生じさせる仕組みが、他国に比べて日本はより厳格です。
たとえば買収によってEU内で本拠地を移そうとした場合、EU内は単一市場を目指しているため、課税上の繰り延べ措置が用意されています。しかし、このケースを日本の税務当局の視点から見ると、それは1度会社を清算して別の国に法人をつくるのと同じように見えます。そのため、課税対象になると判断され、結局M&Aを撤回したニュースも報道されています。日本の税制だから海外では関係ないだろうという意識でいると、思わぬ形でリスクを背負うことになるという実例です。
宮原
2024年に報道された、最近の事例ですね。まさにそのようなサプライズを防ぐためには、企業はどのような準備が必要でしょうか。
吉村氏
すでに社内体制として構築されているものを、また1から組み上げていくことは現実的ではないかもしれません。そのため、たとえば税率がきわめて低い国や地域に子会社を作って投資を行う場合や、国際的な展開を進めている企業を買収する場合など、税務リスクが高いものについては、少なくとも何らかの形で税務部門に情報が共有され、経営陣が早期に対応に関与できるような仕組みをつくっていくとよいと考えています。
崩れゆく国際協調。「米国第一主義」が及ぼす日本企業への影響
宮原
ここからは国際税制の現状について、話をさせてください。BEPSは日本企業に大きな影響を与えました。一方で、第2次トランプ政権の「米国第一主義」政策など、国際税務の環境も大きく変化しています。
吉村氏
BEPSの成果は、第2次世界大戦以降に米国が世界的なネットワークを構築してきた努力の成果の1つと言えます。米国はテロ対策や金融危機対応などの分野でリーダーシップを発揮し、グローバルガバナンスの意思決定に多大な労力を費やしてきました。その成果としてBEPSプロジェクトが実現し、今回のPillar2のような中央集権的なルール設定を基礎とする国際的な取組みが可能になったのです。
米国がこれまで構築してきたグローバルな枠組みを自ら弱める動きをしていることは非常に残念ですが、彼らの視点からすれば、ネットワーク構築のための投資に見合った見返りが得られていないという不満もあるのでしょう。これはある意味、われわれが平穏に過ごしてきた20年間の反動として受け止める必要があるかもしれません。
宮原
これらの動向は日本企業にどのような影響をもたらすのでしょうか。
吉村氏
今後4年間トランプ政権が継続し、共和党が議会において一定の勢力を維持することを考慮すると、米国が引き続き世界的なネットワーク構築を牽引することは期待できない状況です。グローバルルールが世界的な取組みとして維持されるかどうかは不透明ですが、いずれにせよ世界的な合意形成はより困難になると予想されます。先進国中心のルールと発展途上国・新興国中心のスタンダードが分化していく可能性も否定できません。この状況は、グローバルに事業を展開する日本企業にとって大きな課題となります。単一のグローバルスタンダードに準拠するだけでは不十分で、各地域や国ごとの異なる税制や要求に個別に対応する必要性が高まるでしょう。これは企業の負担増加につながりますが、適切に対応できれば競争優位性につながることもあります。
年々高まる税務の専門性と複雑性。対応の鍵はグローバル税務のプロフェッショナル活用
宮原
BEPSまでの国際協調の流れがある一方で、これからは各国独自の対応が主流になるとすると、日本企業はどのように対応すべきとお考えでしょうか。具体的な対応策や準備すべき体制についてご意見をお聞かせください。
吉村氏
グローバルスタンダードに適応していればさまざまなリスクから保護されるという時代は終わりつつあると思います。今後はグローバルな動向に応じた多角的な視点で注意を払う必要があります。具体的な対応策としては、まず各国の税制動向を継続的にモニタリングする体制の構築です。これには社内リソースの育成と外部税務専門家との連携も含まれます。次に、柔軟に対応できる税務ガバナンス体制の整備です。状況の変化に迅速に対応できるよう、意思決定プロセスや情報共有の仕組みを整えておく必要があります。
たとえば、中国やインドのように国際的なスタンダードから一定の距離を置いた税務行政や立法を行う国に対しては、海外からの進出企業同士が協力して意見表明をすることがこれまでも行われてきましたが、そうした対応はどの国においても、より一般的になると思われます。
また、税務リスク管理の強化も重要です。各国の税制変更がもたらす潜在的リスクを評価し、必要に応じて事業モデルや取引構造の見直しを検討する必要があるでしょう。さらに、透明性の確保と説明責任の履行も欠かせません。各国の税務当局や他のステークホルダーに対して、自社の税務ポリシーやアプローチを明確に説明できることが重要になってきます。
1企業でこれらを完全に実現することは難しいため、各国の動向を継続的に注視するKPMG税理士法人のような専門家の役割がますます重要になってくると予想されます。
宮原
各国の税制をしっかりウォッチするのは、なかなか大変です。KPMG 税理士法人は、企業グループと海外拠点のコンプライアンスを一括して管理するGCMS(Global Compliance Management Services)というサービスを提供しています。
このサービスは海外で多数の実績があり継続的に高い評価を得ていますが、日本では導入をご検討いただく企業は増えてきているものの、実際の導入としてはまだ複数社に留まっています。
日本では税務申告は内部で実施し、知識とノウハウを蓄積すべきという強い意識と海外子会社の税務についてまで本社が一括管理することには、本社側においても海外子会社側においても一定の抵抗感があるためと考えられます。
吉村氏
日本企業は、社内リソースに依存する傾向が強いためではないでしょうか。文化的な背景や組織の在り方が関係していると思われます。必要性を否定しているわけではなく、経営陣が社内で対応可能だと見立ててしまうことが多いのかもしれません。しかし、実際にはグローバルな税務環境の複雑化により、社内リソースだけでの対応は限界に近づいているとも言えるでしょう。
宮原
私たちも同じ認識です。今後は税務申告においても人材不足という課題が顕在化してくるでしょう。税務知識は世代間で継承し、適切なリソースを確保する必要がありますが、すべてを内部で完結させようとすると限界があります。また、世界各拠点の税制に精通することは日本本社の力だけでは困難です。しかも、各拠点で収集する情報の質にはどうしてもばらつきが生じるため、その不均質な情報に基づいて判断を下さざるを得ないことになります。外部の税務専門家に委託することには、一定水準の品質が保証された情報に基づく経営判断が可能になるという利点があります。
吉村氏
おっしゃるとおり、税務の専門性と複雑性は年々高まっています。特に国際税務においては各国の制度を熟知した税務専門家の知見が不可欠です。日本企業が伝統的に内製化を重視する傾向は理解できますが、すべてを社内で対応することは効率性の観点からも疑問があります。特に中小企業や海外展開の初期段階にある企業にとっては、専門的な知識やネットワークを持つ外部税務専門家の活用が合理的な選択肢となるケースも多いでしょう。その際に重要なのは、単に業務を外注するのではなく、外部税務専門家との協働を通じて社内の能力向上も図るという視点です。
宮原
各国が独自の対応を強化するなかでは、情報の正確性と精度がより重要な意味を持つようになりますね。「他社がそうしているから自社もそうする」という発想ではなく、自社の状況や拠点数の違いも含めて詳細に分析した上での判断が求められるようになるでしょう。このような環境変化に対して、日本企業はどのように対応すべきでしょうか。
吉村氏
トランプ大統領の動きからもわかるように、メキシコやカナダに拠点があった場合に突如として規制の標的にされる、そんなリスキーな時代に突入しています。サプライチェーンの構成によってリスクの内容や程度が大きく異なるなど、各社の状況はそれぞれに異なりますので、他社の動向を単に模倣するのではなく、自社の事業特性や戦略に合わせた税務ガバナンスを構築する必要があります。税務リスクの特定・評価・対応のプロセスを確立し、経営層が税務戦略の意思決定に積極的に関与する体制が望ましいでしょう。
また、グローバルな視点と各国の現地事情を両立させるバランスも重要です。グローバルな税務方針を維持しつつも、各国の特殊性に柔軟に対応できる仕組みが求められます。そのためには本社と海外子会社の間の効果的なコミュニケーション体制の構築や、情報共有プラットフォームの整備なども検討すべきでしょう。
さまざまなシナリオに対する備えを。予測不能な時代を生き抜く税務戦略
宮原
ここまで国際税制と第2次トランプ政権、それらに対応するための税務ガバナンスなどについて話してきました。トランプ政権の一方的で極端な対応が現実となり、企業にとっては予測困難な政策変更への対応が新たな課題となっています。
吉村氏
企業としては関税が課されればそれを支払わざるを得ず、部品が入手できなければ事業継続が困難になります。司法的な対応にも政治的な介入の可能性が高く、実質的には企業は無法な規制にも従わざるを得ない状況にあります。
このような不確実性の高い環境においては、想定されるさまざまなシナリオに対する備えが重要です。各国の政策変更に迅速に対応できるよう、情報収集と分析の体制を強化し、必要に応じて事業モデルを柔軟に調整できる、そんな準備が必須となります。先ほども申し上げたように、これまで米国が中心となって構築してきたグローバルな枠組みは弱体化しています。先の話ではありますが、現状では2026年の中間選挙も共和党有利の見通しのようです。インフレが許容範囲を大きく超えるような事態にならない限り、現状の政治的傾向は続くでしょう。各国の税制や規制の変化を継続的にモニタリングし、自社への影響を適切に評価できる体制の構築が不可欠です。
また、潜在的なリスクに対する対応策をあらかじめ検討しておくことも重要です。不確実性が高まるなかでは、予防的なアプローチと迅速な対応能力の両方が求められると考えます。その意味で、外部専門家によるグローバルな視点からのサポートがますます重要になってくるでしょう。
宮原
私たちの責任も一層重くなります。企業の皆さまが適切な税務ガバナンスを構築し、グローバルな環境変化に対応できるよう、より専門的かつ実践的なサポートを提供していく必要があると感じています。
吉村先生、本日はありがとうございました。
吉村氏
ありがとうございました。


企業の税務ガバナンス体制見直しをご検討されている方へ
KPMG税理士法人は、従来のコンプライアンスを主とした税務機能から企業戦略を支える税務機能への転換を目指すTax Reimagined(税務機能の再構築)を推進しています。以下のページにて詳細をご覧ください。




