慶應義塾大学寄附講座、「なぜ今この時代にイノベーションが求められるのか」
「なぜ今この時代にイノベーションが求められるのか」をテーマに、KPMGコンサルティング株式会社 佐渡 誠が慶應義塾大学経済学部向けに講義をしました。本稿では、講義内容のエッセンスをお届けします。
「なぜ今この時代にイノベーションが求められるのか」をテーマに、KPMGコンサルティング株式会社 佐渡 誠が慶應義塾大学経済学部向けに講義をしました。
KPMGジャパンでは、最新のテクノロジーの動向からアカウンティングやファイナンス、関連法規など、“起業”に必要な知識を体系的に学ぶ寄附講座「スタートアップとビジネスイノベーション」を慶應義塾大学経済学部に提供しています。そのなかの1つとして、「なぜ今この時代にイノベーションが求められるのか」をテーマに、KPMGコンサルティング株式会社 佐渡 誠が慶應義塾大学経済学部向けに講義をしました。本稿では、講義内容のエッセンスをお届けします。
Ⅰ.正解がない世界に飛び込んでほしい。そのために「目先だけを見ない」こと
私は現在、KPMGコンサルティング株式会社副代表を務めており、「ストラテジーグループ」と「イノベーショングループ」という2つの組織を統括しています。また、「ビジネスイノベーションユニット」という組織を、会社の中に4年前に立ち上げました。このユニットは、一言で言うと、「社会課題に対して本業を通じて向き合い、解決していこう」という目的で作られたものです。

KPMGコンサルティング 佐渡 誠
ここ数年、「CSV(Creating Shared Value)」という考え方が注目されています。CSR(Corporate Social Responsibility)は、企業が本業とは別に社会貢献活動を行うものでしたが、CSVは「本業そのものを通じて社会価値を創出する」という考え方です。つまり、ビジネス活動自体が社会課題の解決に直結するべきだ、ということです。私たちのビジネスイノベーションユニットも、このCSVの思想に基づき、ボランティア活動ではなく、プロフェッショナルなプロジェクト活動として社会課題に取り組んでいます。
たとえば、スマートシティ・街づくり、スポーツイノベーション、オープンイノベーションとスタートアップ支援、宇宙事業・テクノロジー推進などが挙げられます。宇宙産業への支援、先端テクノロジーを活用したイノベーションにも取り組んでいます。こういった業界をいかに産業化していくかということに注力しています。
共通点としては、コンサルティング業界としての正解がない・足が長いというものになります。
私が根本で感じているのは、たとえやる気があったとしても、目先の正解があるような仕事ばかりに人を当て続けていくと、会社としての成長にはつながらない、ということです。コンサルティング業界のビジネスモデルはシンプルです。人が動き回り、お客様先でお金をもらってくればいいのです。工場もないですし確かに目先の売上は立ちますが、骨太な成長にはなりません。ChatGPTや生成AIの登場により、IT領域のコンサルティング需要が爆発的に増えています。実際、テクノロジーに関するリテラシー格差を利用し、AI関連のコンサルティングを提供することで、短期的に大きな収益を上げることが可能です。
しかし、本当に重要なのは、単なる技術導入支援ではなく、「正解のない社会課題」に対して、いかに道筋を示していくかです。これが、本来のコンサルティングの使命であり、私たちの目指す方向です。
今日の講義を通じて、皆さんにも同じことをお願いしたいと思っています。正解がない世界に、ぜひ飛び込んでください。そして、皆さんの力で日本をもう一度動かしてほしいと願っています。
私が皆さんに伝えたいのは、以下の3つです。
1.日本の「潮目」が変わった
まず、日本社会の「潮目」が明らかに変わったということを伝えたいと思います。これは単なる気分の問題ではなく、時代が本当に変わってしまったという現実です。私が大学生だった1994年とは、もはや状況がまったく異なります。これから社会に出ていく皆さんには、最低限この変化をマインドセットとして理解しておいてほしいのです。
2. イノベーションは「起きたらいい」ではない
イノベーションについては、「誰かが起こしてくれればいい」という考えでは済まされない局面に、日本は立たされています。イノベーションがなければ、日本は沈みます。だからこそ、私たちはイノベーションを「待つ」のではなく、「自ら起こさなければならない」のです。KPMGコンサルティングも、こうした危機感から、大学と連携して皆さんとの対話の場を持っています。私たちだけではできないことを、若い皆さんに託したいと本気で思っています。
3. 正解のない世界でどう考えるか
最後にお伝えしたいのは、「正解がない世界でどう考えるか」ということです。これは公式や法則で解けるものではありません。私自身、さまざまな経験を通じて辿り着いた結論を単純化すると、「妄想」と「アート」を重視することに尽きます。
これらについて、本日お伝えしたいと思います。

KPMGコンサルティング 佐渡 誠
Ⅱ.現在の日本に何が起こっているのか
今日本で何が起きているのかについてお話しします。「失われた30年」という言葉を耳にしたことがあると思います。かつては「失われた20年」と言われていましたが、今は「30年」と言われています。ただ、数字が変わっただけで、実態はずっと停滞したままです。実際、国際競争力ランキング2024年で日本は38位です。私が学生だった頃、日本は第2位か第3位でした。世界中で「日本はすごい」と言われた時代でしたが、今はその面影はほとんどありません。
なぜここまで落ちたのでしょうか? 理由は多様ですが、よく指摘されるのは企業を率いている経営層の意思決定の遅さ・弱さ、そこに起因した迅速な投資判断の未熟さなどが挙げられます。
これは、日本がかつて「高度経済成長」を支えた時代の成功体験が、逆に足かせになっているからだと考えられます。私たち50代は、高度経済成長期を支えた世代に育てられました。規律を守り、スピーディに大量生産・大量消費を進めるスタイルが当時は正しかったのです。しかし、その価値観を無批判に受け継いだままでは、今の社会には通用しません。今、日本の産業界・企業界全体に、過去の成功体験と現在の現実との間に大きなギャップが存在しています。このギャップについて、どう解釈するかは皆さんにお任せしますが、私は事実として正しい認識だと思っています。大企業に就職することを否定しているわけではありません。ただ、皆さんには自分なりのアイデンティティと、大局観を持って世の中を見る力を持ったうえで、企業に進んでほしいと願っています。マクロ的に引いて見れば、今の日本はこういう状況にあります。
ある調査によりますと、国際競争力を構成する要素のなかで特に重要なのが「企業の新陳代謝」だとされています。つまり、新しいビジネスを起こし、若い世代や新しい発想をどんどん取り込んでいく力が強い国ほど、競争力が高いということです。これが日本では十分に回っていない。だから、日本の国際競争力は現在38位にまで低下しているのです。日本の大企業文化においては、過去の成功体験や旧来の価値観が根強く残っています。
この文化に固執している限り、新陳代謝は進まず、競争力も回復しません。皆さんは、そんな状況のなかで「どうキャリアを築いていくか」が問われています。
Ⅲ.自身のキャリアの選択とこれからの時代に求められること
私自身、慶應義塾大学を卒業した後、日本の大企業に就職しました。当時は就職氷河期でしたが、慶應義塾大学という看板や先輩たちの支援もあって、大企業のメーカーに入ることができました。しかし、2年目には「違うな」と感じ始め、4年目でコンサルティング業界に転職しました。当時、まだコンサルティングというキャリアは今ほど一般的ではありませんでしたが、結果として自分の意思で方向転換をしたことは、今振り返っても良かったと思っています。皆さんもこれからのキャリア選択において、マクロな視点を持ちながら、自分の軸で判断してほしいと願っています。
世界の企業の時価総額ランキングを見ると、1989年には上位50社のうち多くが日本企業でした。
しかし、現在、世界の上位に日本企業は一社も入っていません。これは単なる偶然ではなく、かつて成功したビジネスモデルが今は機能していないという事実を示しています。この現実に対して、私たちはただ悲観するだけではいけません。「だからこそ何かを変えなければならない」というのが、今、皆さんに突きつけられている課題です。
もう1つ大きな変化は、人口減少です。日本は2004年をピークに人口が減少し続けています。これは一時的なものではなく、構造的に戻ることがない減少です。人口が減るということは、国内市場が縮小することを意味します。かつては日本市場だけでビジネスが成立しましたが、これからは違います。日本国内だけに依存するビジネスモデルは、成功しにくくなるのです。また、これからのビジネスには、「海を越える」視点が不可欠です。国内市場の縮小に対抗するためには、グローバル市場を見据えてビジネスを展開する必要があります。
過去の産業革命の歴史を振り返ると、第1次から第3次産業革命までは「大量生産・大量消費」が基本でした。しかし、その結果として環境破壊や地球温暖化といった負の遺産を生んでしまいました。今求められているのは、単なる効率性ではありません。「創造性」を軸とした新しい行動様式です。大量生産・大量消費から脱却し、持続可能な社会を目指す——それが、これからの時代に求められる人間の行動原理なのです。
Ⅳ.現代の課題は3つに集約される
現代で求められることは大きく以下の3つに集約されると考えています。
・効率化(労働力減少への対応)
・持続可能性(環境・社会課題への対応)
・未来創造(新しい価値・ビジネスの創出)
これらの課題に真正面から取り組めるかどうかが、今後の社会、そして皆さん自身のキャリアにとって極めて重要な意味を持ちます。たとえ労働力が減ったとしても、社会を維持できるよう、引き続き効率化は求められています。あらゆる業界・現場で、効率化を進める努力は今後も不可欠です。一方で、ここ5〜10年で顕在化してきた新たな課題にも向き合わねばなりません。それが「負の生産」の問題です。CO₂排出、ゴミ問題、地域格差など、サステナビリティに関わる問題がますます重視されています。10年前はSDGsやサステナビリティという言葉もありましたが、今ほど本気で受け止められていませんでした。今は企業にとって、サステナビリティへの対応は「やったほうがいい」ではなく「やらねばならない」ものになっています。また、新規事業や新しいサービスも作ってビジネスを創出していかなくてはなりません。
どれを選ぶかに「正解」はありません。自身の興味や関心に応じて、どの領域で力を発揮したいかを考えることが重要です。効率化課題に関しては、日本人は非常に得意です。正解が比較的明確であり、A社で成功した手法をB社に転用するといったやり方は、教育や社会経験でよく訓練されてきました。
一方、負の生産や未来創造といった、「正解がない」イノベーション領域に対しては、日本人はやや苦手です。これは、そういった思考・行動様式がこれまであまり育まれてこなかったためです。これからは、皆さん一人ひとりが、こうした新しい課題にどう向き合うかが問われます。よく「イノベーションを起こしたい」と言いますが、重要なのは「何を解決したいのか」という問いです。イノベーションは手段であって目的ではありません。解決したい社会課題、あるいは目指したい未来像がまずあり、それに向けて試行錯誤する中で、結果としてイノベーションと呼ばれる変化が生まれるのです。
「新しいビジネスモデルを作りたい」
「CO₂問題を解決したい」
「地方経済を再生したい」
こうしたイシュー(課題)への熱意が、真のイノベーションを生み出します。たとえば、Uberの事例は有名です。彼らは最初から「ライドシェア革命を起こしたい」と考えていたわけではありません。「もっと便利な交通手段を作りたい」という課題感からスタートし、その結果として世界を変えるビジネスモデルが誕生しました。
一方、セグウェイの例では、「技術は素晴らしい」のに「どの課題を解決するのか」が定まらず、普及に至りませんでした。技術だけではイノベーションは生まれない。課題に向き合う熱意が必要なのです。
また、イノベーションを考える上で欠かせないのが、ビジネスモデルの理解と刷新です。単に表面的な仕組みをなぞるのではなく、どこで収益が生まれているのかどの構造が価値を生み出しているのかを深く理解する力が求められます。
- JTBとExpedia
- ユニクロとZOZOTOWN
同じ業界に見えても、ビジネスモデルの根本はまったく異なります。表面だけではなく、儲けの本質に目を向けることが大切です。表面的なプロダクトではなくデータや行動変容の構造にこそ注目すべきというのが、現代のビジネスモデル理解のポイントです。
Ⅴ.正解がない時代に求められる思考
今後求められるのは、「正解探し」ではなく「未来を自分で描く力」です。
- ロジカルシンキング
(課題を分析し、効率的に解決策を導き出す) - デザインシンキング
(観察を通じて隠れたニーズや問題を発見する) - アートシンキング
(自分自身の価値観や世界観から新しい問いを立てる)
このうち、特にアート思考が重要になります。「どこに課題があるか」ではなく、「自分は何を作りたいのか」という内発的な発想を持つこと。それこそが、未来を切り拓くために不可欠です。
『13歳からのアート思考』という本では、こんなエピソードが紹介されています。ある絵を見せられた時、大人は「水がきれい」「色彩が豊か」などと答える。一方、4〜5歳の子どもは「カエルがいる」と自由な発想をする。これは、大人になる過程で「正解を探す思考」に縛られていくことを示しています。本来、人間はもっと自由に世界を捉える力を持っている。これを取り戻すことが、これからの時代に必要だという提言です。皆さんはまだ自由な存在です。しかし、単なる就職予備軍ではありません。これからの日本を、社会を、未来を「作る側」に回ってほしい。イノベーションは「起きたらいいな」ではなく、「自ら起こさなければならない」時代に突入しています。
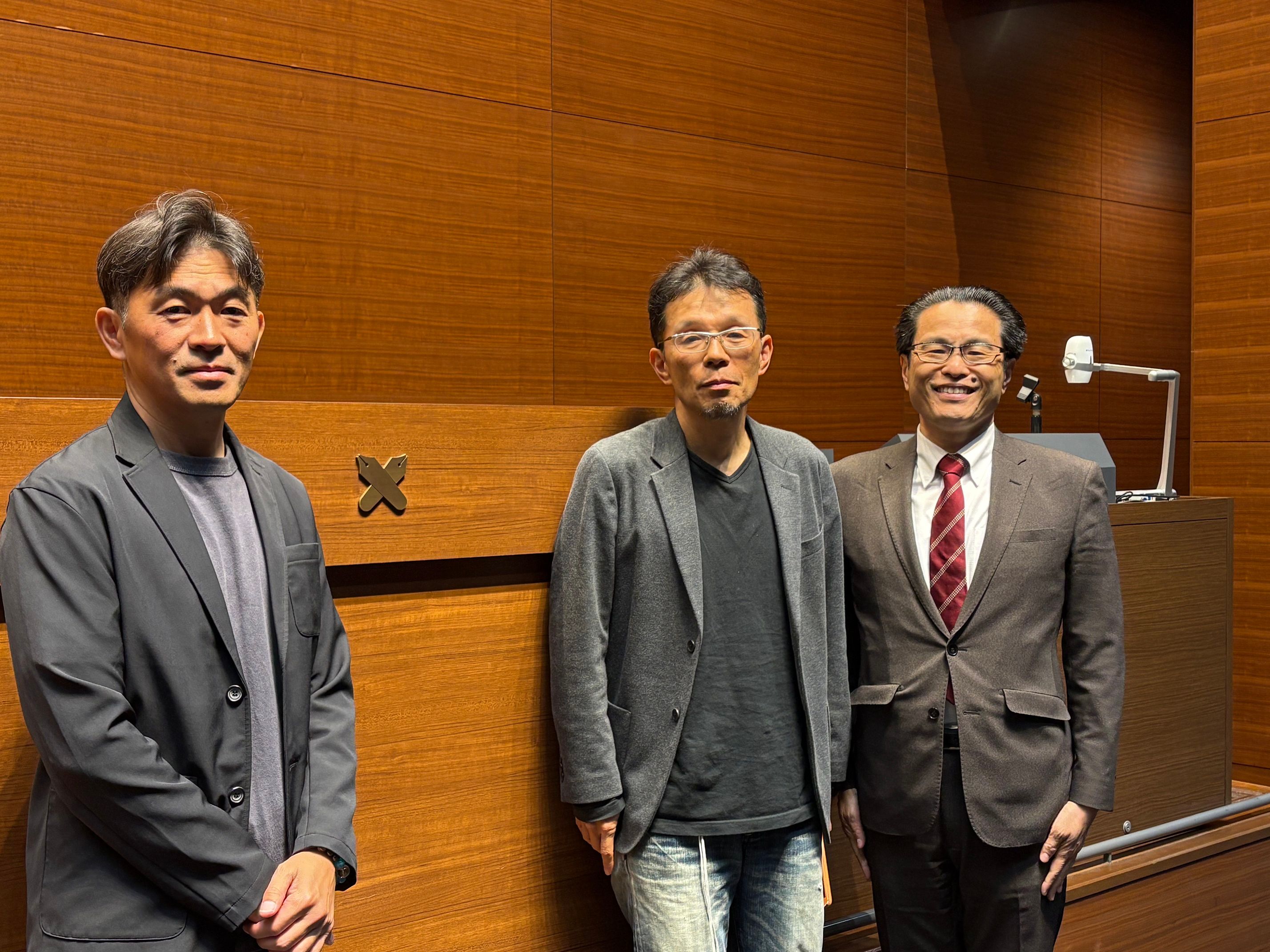
(左)佐渡 誠(中)倉田 剛 (右)慶應義塾大学 経済学部 教授 中妻 照雄氏



