慶應義塾大学寄附講座、起業で知っておくべきアカウンティングの知識
「スタートアップのための必携ビジネス知識 アカウンティング」をテーマに、KPMGコンサルティング株式会社 倉田 剛が慶應義塾大学経済学部向けに講義をしました。本稿では、講義内容のエッセンスをお届けします。
「スタートアップのための必携ビジネス知識 アカウンティング」をテーマに、KPMGコンサルティング株式会社 倉田 剛が慶應義塾大学経済学部向けに講義をしました。
KPMGジャパンでは、最新のテクノロジーの動向からアカウンティングやファイナンス、関連法規など、“起業”に必要な知識を体系的に学ぶ寄附講座「スタートアップとビジネスイノベーション」を慶應義塾大学経済学部に提供しています。そのなかの1つとして、「スタートアップのための必携ビジネス知識 アカウンティング」をテーマに、KPMGコンサルティング株式会社 倉田 剛が慶應義塾大学経済学部向けに講義をしました。本稿では、講義内容のエッセンスをお届けします。
Ⅰ.世界共通言語である会計と公認会計士の役割
財務諸表は会社が作成します。しかし、自分たちで作ったものを「正しい」と自己判断するのは、どうしてもバイアスがかかりますよね。だからこそ、独立した立場の監査人がチェックするという仕組みが必要なのです。
ここで、会社が財務諸表を作り、監査人が監査をするという構造に「ねじれ」が生まれます。公認会計士の多くがこの構造に葛藤を感じます。クライアントである会社から私たち公認会計士は報酬をいただく一方で、実際に向き合っているのは、その先にいる利害関係者つまり市場や投資家などです。こうした構造を理解したうえで、私たちは会計や監査に関わっているのです。公認会計士を目指して勉強している方も、そうでない方もいらっしゃると思いますが、仮に公認会計士試験に合格したとしても、すぐに財務諸表を作成したり監査をしたりすることはできません。監査の実務を2〜3年経験して、ようやく全体像が見えてくるというのが実際のところです。ただし、公認会計士や監査人になる必要は必ずしもありません。今日、皆さんにお勧めしたいのは、財務諸表を「正しく読む力」を身につけることです。そして、自分の言葉でそれを語れるようになること。これがとても重要です。
英語が世界の共通言語であるように、ビジネスの世界では会計がビジネスを数字で語るうえでの世界共通の「言語」です。英語ができれば、世界のほとんどの場所であまり困らない。みなさんも世界の共通言語として英語の勉強はされていると思いますが、同じように会計も「世界共通言語」として学ぶ意義があると思います。
これまで会計に触れたことがない、あるいは教養課程でつまらなくてやめてしまった、という方も多いかもしれませんが、今からでも全然遅くありません。私も英語が喋れなくて恥をかいてから英語学習に力を入れたのですが、経験してはじめて重要性に気づくこともあります。
Ⅱ.そもそも会計とは何か?
一言で言えば、会計とは「ビジネスの結果を金額で表す技法」です。どれくらい儲かったのか? いつ儲かったのか? どこで、どんな風に儲けたのか? そのすべてを数字と期間で表現するのが会計の技術であり、これは世界中で共通の言語として通用します。
「取引」という言葉も一般的に使われますが、会計の中では「会社の財産を変動させる行為」のことを指します。たとえば、地震で工場が壊れた、火事で設備が損傷したという出来事も、会計上では「取引」と見なされます。一方で、「A社とB社が提携交渉を始めた」というようなニュースは、会社の財産が動いていない限り、取引とはされません。このように、会計は世界共通の言語です。英語と同じく、今のうちに身につけておくと、将来のさまざまな場面で役に立つはずです。

KPMGコンサルティング 倉田 剛
「共通言語」というのは、みんなが使えるツールのことです。そして、それにあたるのが「財務諸表」です。財務諸表とは、企業がどんなビジネス活動をしてきたかを数字で示したもので、いわば“会社の成績表”です。
どれだけ資産が増えたか、利益がどのくらい出たかなど、企業の状況をルールに従って公表します。中期経営計画などもそうですね。今、就職活動をしている方や、気になる企業がある方もいると思いますが、上場企業であれば、その成績表(財務諸表)は誰でもインターネットで見ることができます。世界中どこにいてもアクセス可能です。企業は毎年、何十万、何百万件という取引を行い、その集積を帳簿に記録してまとめたものが財務諸表になります。
1.複式簿記と「貸方・借方」
帳簿は「左」と「右」に分かれていて、それぞれ「借方(デビット)」と「貸方(クレジット)」と呼ばれます。これが簿記の基本です。よく「貸方・借方」という言葉を聞いて挫折する人がいますが、これは単なる翻訳です。英語では"debit"と"credit"。意味を考えすぎず、単に「左」と「右」だと割り切ったほうが、理解が進みやすいと思います。
会計には「B/S(バランスシート=貸借対照表)」や「P/L(損益計算書)」といったフレームワークがあります。これらはルールであり、世界中で使われている共通言語です。内容が難しそうに見えても、実は慣れの問題です。会計は「複式簿記」という仕組みを基盤としています。すべての取引を「左」と「右」のセットで記録する——それがこの技術です。
複式簿記は、500年以上前にイタリアの数学者であり近代会計学の父と呼ばれるルカ・パチョーリによって体系化されました。彼は当時、宗教者に数学を教えていたそうです。その後、150年前に日本にこの簿記を導入したのが、慶應義塾の創始者でもある福沢 諭吉先生です。デビットやクレジットという概念を日本語に翻訳し、「貸方・借方」「貸借対照表」といった用語を作りました。150年経った今でも、その言葉が使われ続けているわけですから、すごいですよね。
2.起業で必要な会計の知識
ベンチャー企業の調査機関が発行している「ベンチャー白書」によると、起業の動機はここ20〜30年で大きく変化しました。以前は「金持ちになりたい」「自由になりたい」という動機が主流でしたが、現在では「自分のアイデアを実現したい」「社会課題を解決したい」という動機が増え、2018〜2019年には77%に達しています。社会をよくしたいという気持ちは素晴らしいと思います。ただ、一方で心配になるのが「お金のことをあまり考えない起業家」が増えている点です。どんなに良いことをしていても、資金が尽きれば継続できません。一生ボランティアを続けられる人なんて、そうはいないですよね。
米国のデータによれば、起業後1年以内に約4割、5年で8割の会社が消えるとされています。日本もほぼ同様か、あるいはもっと厳しいかもしれません。同じく米国の起業家調査で、失敗後に一番後悔するのは「フィナンシャル・マネジメントをしっかり学ばなかったこと」だそうです。つまり、やはりお金なんです。
3.道徳と経済の両立:二宮 尊徳と稲盛 和夫の言葉
江戸時代の二宮 尊徳はこう言っています。「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」
最近でいえば、詐欺や闇バイトなどはまさに「道徳なき経済」。逆に、いいことをしたいと願っていてもお金が続かなければそれは「寝言」になってしまう。稲盛 和夫さんも、同じようなことを言っています。技術者出身でありながら社長になった彼は、「数字がわからないと経営はできない」と痛感し、会計を学びました。
その彼の言葉は、「会計は経営のコックピットである」つまり、数字という計器を見ずに経営をしていると、飛行機でいえば燃料計を見ずに飛んでいるようなもの。危険極まりないのです。
Ⅲ.ビジネスパーソンの“たしなみ”としての会計
皆さんが将来、経営者にならなくても、ビジネスに関わる限り、会計は“たしなみ”として身につけておいた方が良いです。福沢 諭吉先生の言葉「学問のすすめ」にも、「実学」の重要性が語られています。実学とは、実生活に役立つ学問。まさに会計やお金の使い方がそれにあたります。会計を学ぶ目的は、会計を極めることではありません。会計という道具を使って、経営や社会を語れるようになること。それが、本質です。
企業経営や経済活動を、客観的かつ標準的に記述・分析できる唯一の共通言語。それが「会計」です。
財務諸表を理解することは、経営者にとっての“運転免許”のようなものだと言われます。でも、日本の上場企業を見ていると「無免許運転」がまだまだ多い。あるMBA取得経験もある著名な経営者も、こう言っていました。「MBAでいろんな科目を学んだけれど、最終的に一番役に立ったのは最初に学んだ“会計基礎”だった」と。私自身も同感です。私もMBAで同窓だった日本人で、B/SとP/Lの区別がつかないまま大企業で管理職をしている人もいて、「それで大丈夫かな」と思ったことがあります。
Ⅳ.30分で押さえるアカウンティング
会計のすべてを30分で語るのは難しいので、最低限知っておきたいことをお話します。
1.財務三表の超入門:B/S・P/L・キャッシュフロー
財務三表(B/S、P/L、キャッシュフロー計算書)は、それぞれ以下のように捉えると分かりやすいです。
- B/S(バランスシート):持ち物リスト
- P/L(損益計算書):お小遣い帳
- キャッシュフロー計算書:財布の中身
ある広報担当の方が、初心者にもわかりやすくこのように説明していました。とても良い比喩だと思います。

KPMGコンサルティング 倉田 剛
2.バランスシート(B/S)の見方
バランスシートは「左(資産)」と「右(負債・資本)」の2つに分かれています。これは複式簿記と呼ばれる構造です。たとえば、銀座のビルを持っている会社と、郊外のアパートを1軒持っている会社では同じ不動産業でも「持ち物」の価値が違いますよね。そしてその「持ち物(資産)」を、どのように手に入れたか。
- 銀行から借りた(負債)
- 自分で出資した(資本)
これがバランスシートの右側です。
自己資本比率というのは、「全体のうち、自前の資本でどれだけ賄っているか」を表す指標です。
半分以上が自己資本だと健全と言われていますが、日本の製造業では平均して40%程度。残りは借入による資金調達です。
3.P/L(損益計算書)の基本構造
P/Lは「ある期間にいくら儲かったか」を示す書類です。構造はシンプルで、
売上 - 費用 = 利益(または損失)
段階的に利益が表示されるのが特徴で、
- 売上総利益(粗利)
- 営業利益
- 経常利益(本業以外も含む)
- 税引前利益
- 当期純利益
など、段階を踏んで表示されます。
ちなみに、
- 一番上の「売上」は トップライン、
- 一番下の「当期純利益」は ボトムライン
とも呼ばれます。
4.キャッシュフローと財務三表の連動
P/Lで「利益」が出ていても、実際に「現金」が増えていないケースもあります。だからこそ、キャッシュフロー計算書が必要になります。
- お金は入っているか?
- 利益が現金として残っているか?
これが「財布の中身」であり、企業の持続性を測る重要な要素です。
5.ROA・ROEという視点
「どれだけの資本を使って、どれだけ利益を出したか」を示すのが、
- ROA(総資産利益率)
- ROE(自己資本利益率)
同じ利益でも、少ない資本で儲けたほうが効率的です。多くの日本企業は、これらの指標で10%前後を目指しています。
6.会計の美しさとシンプルな例
最後に、会計の構造を超シンプルにした例を1つ出します。
- 100万円借金して現金を得る(左:現金、右:借入金)
- それを使ってお店を開く(現金 → 建物などの固定資産に)
- 1年で売上120万円、費用70万円 → 利益は50万円
- 利益はキャッシュとして残り、最終的に資本に加わる
この「儲かった分」が純利益(リテインド・アーニングス)としてB/Sに加算される。これが複式簿記の“美しさ”です。左と右が常にバランスし、ビジネスの流れが1本の筋でつながっている。これこそが「数字で語る力」なのです。
利益が出たらどうするか? 借金を返すのも1つの手ですが、新商品の開発、店舗の拡大、他事業への参入、海外展開など、選択肢はいろいろあります。これがまさに「経営」の本質です。AIにはできない、人間ならではの意思決定が求められる領域です。複式簿記の構造は、こうした判断を支えるフレームワークでもあります。
7.キャッシュフローの重要性
キャッシュフロー計算書は、お金の出入りの全体像を示します。仕訳ではなく、B/SとP/Lの差額などから作成されるケースが多いです。
キャッシュフローは以下の3つに分類されます。
- 営業活動によるキャッシュフロー:本業で得たキャッシュ
- 投資活動によるキャッシュフロー:設備投資、新規事業、研究開発など
- 財務活動によるキャッシュフロー:借入、返済、株式発行など
この3つを見ると、「この会社は本業で儲かっているのか?」「新しいことに投資しているのか?」「財務的に無理してないか?」などが透けて見えるわけです。キャッシュフロー計算書が日本で法定の財務諸表となったのは、わずか30年ほど前。それまで重要視されていなかった背景には、「黒字でも倒産する会社」が多いという事実があります。
たとえば、
- 売上1000円を上げたが、回収は2か月後
- 給与は翌月支払い
このタイムラグによってキャッシュが足りず、従業員に給料が払えない。これが倒産理由となることは、決して珍しくないのです。つまり、儲かっていてもキャッシュがなければ会社は潰れる。これが経営の現実です。
「日本人全員が財務諸表を読めるようにする」これは、会計YouTuberとして知られる公認会計士 大手町のランダムウォーカーの福代 和也さんのコンセプトですが、私も大いに共感しています。彼の著書『世界一楽しい決算書の読み方』は、非常に親しみやすく、B/SやP/Lへの苦手意識を和らげてくれます。また、「どの会社に入りたいか」を考えるとき、給与や福利厚生ももちろん大事です。ですが、財務諸表を見て“どんな未来を描いている会社か”を知ることも、キャリア選択のヒントになります。
Ⅴ.会計と英語ができると自身のビジネス人生が変わる
最後に、会計とは直接関係ないように思われるかもしれませんが、「英語力」についても触れておきたいと思います。
私自身も、公認会計士を目指して会計の勉強はしていましたが、英語は30代になるまでまともに話せませんでした。大学受験で勉強はしましたが、実際の会話には苦労していました。私が本気で英語を勉強しようと思った「痛い経験」があります。あるとき、世界中から新任マネージャーが集まる国際研修プログラムに参加しました。約2000人が1週間のグループディスカッションと最終プレゼンを行う内容です。私は「せっかくの機会だからオールイングリッシュでやろう」と意気込んで、ネイティブスピーカーだけのグループに入りました。しかも私以外は全員女性で、ロンドン、ニューヨーク、テキサスなど、さまざまな出身地の人たちでした。
休憩時間には皆が盛り上がっていて、「ねえ聞いてよ!」とものすごいスピードで会話しているのに、私は全くついていけない。「わからなかったら止めてね」とは言ってくれるのですが、毎回止めていたら会話にならない。結果的に、1週間ずっと苦痛でした。最終プレゼンでは、私は「タイムキーパー」だけを任されました。英語力に不安があると思われて、発表の主役から外されたのです。そして終わったあと、あるメンバーから「タイムキーピングだけはうまかったね」と言われた時は、正直屈辱でした。その経験で「このままではまずい」と痛感し、本気で英語を学び直しました。英語が話せるようになると、世界が広がります。起業しなくても、どこかの会社に入っても、あるいは急に海外赴任を命じられても、慌てなくて済みます。
TOEICで800〜900点を取れると学生のうちから選択肢が一気に広がります。私は30代半ばまで英語ができませんでしたが、今ではある程度伝えたいことの7割くらいは英語で話せるようになりました。
私は英語が完璧ではありませんが、2000人以上の海外パートナーの前でプレゼンをしたり、グローバルのネットワークで日本代表を務めたりしています。大勢の前でのプレゼンの時には受け答えは緊張しましたが、やりきった経験があります。
母国が英語でない私たちがビジネスの世界で会計がわからないと、ミサイルに竹やりで挑むようなもの。ビジネスの共通言語である英語、そして数字の共通言語である会計、この2つができれば、グローバルな土俵で戦える武器になります。
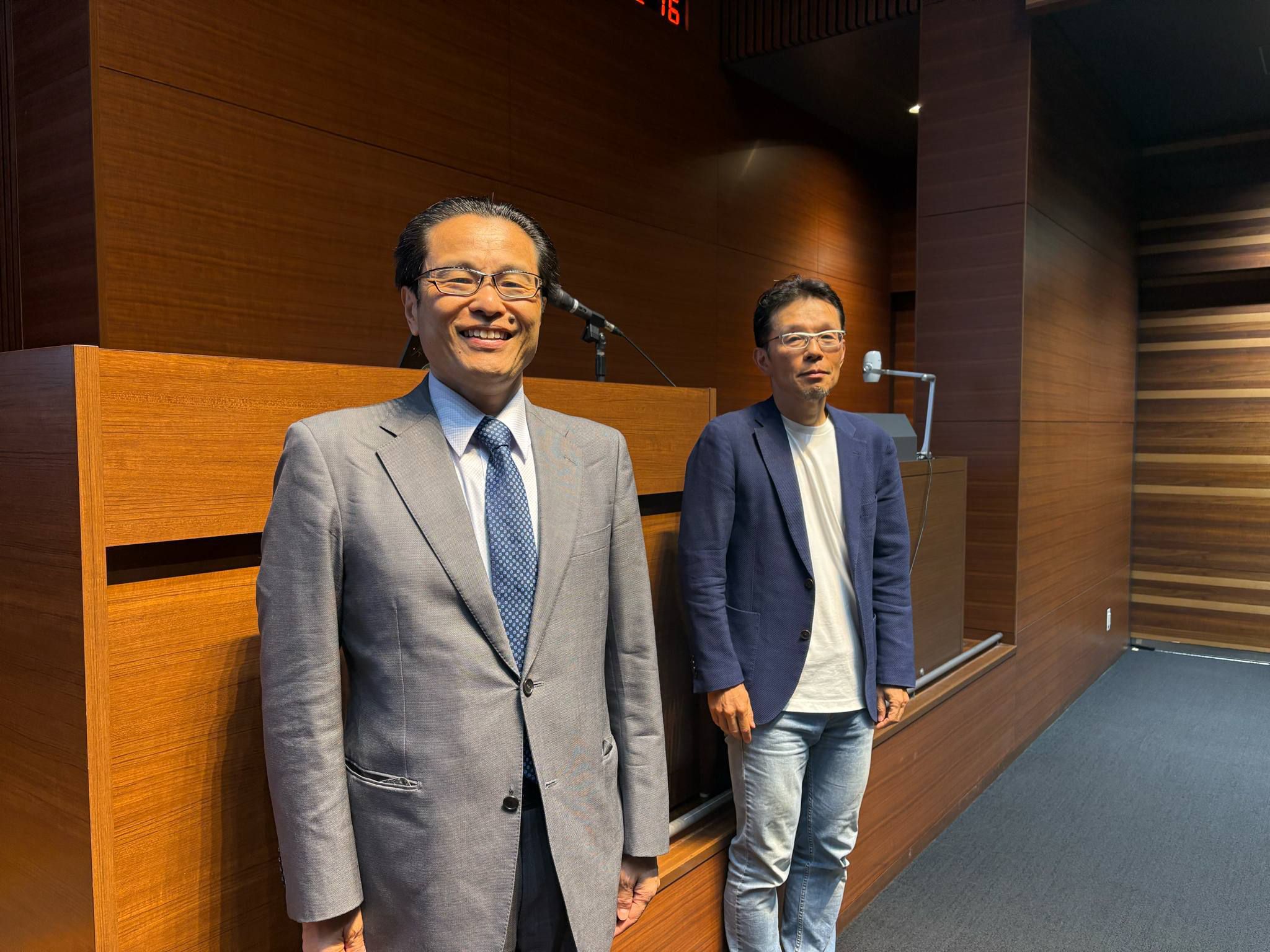
(左)慶應義塾大学 経済学部 教授 中妻 照雄氏 (右)倉田 剛
倉田 剛プロフィール
KPMGジャパン インフラストラクチャーセクター 運輸・物流・ホテル・観光セクター統轄リーダー/KPMGコンサルティング プリンシパル/KPMGモビリティ研究所コアメンバー
KPMGコンサルティング株式会社
大阪大学経済学部卒業。米国マサチューセッツ大学MBA修了。朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所後、大手鉄道会社グループ、テーマパーク運営会社、製造業、商社等の法定監査ならびに上場支援業務に従事。 その後、サービス業、飲食業、通信業などにおいてERPの導入及び経理業務改革、シェアドサービスセンターの導入、内部統制構築(米国企業改革法、内部統制報告制度)、IFRS®基準導入等を数多く担当。 現在、新産業領域でのイノベーション(Business Innovation)創出や経理業務高度化などのアドバイザリー業務を担当しながら、KPMGモビリティ研究所においてMaaS(Mobility as a Service)やスマートシティに関する調査・研究や、自治体等における実証事業に関与している。資格:日本公認会計士



