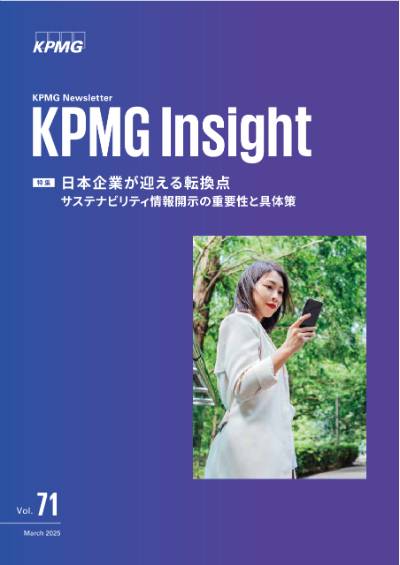間近に迫るサステナビリティ情報の開示 ~その背景と日本企業が目指すべき方向性とは~
今回は、元金融庁長官でKPMG税理士法人の特別顧問であり、KPMGジャパンのシニアアドバイザーの中島 淳一と、あずさ監査法人 会計・開示プラクティス部の関口 智和との対談により、サステナビリティ情報開示の背景と日本企業が目指すべき方向性が明らかになりました。
今回は、元金融庁長官でKPMG税理士法人の特別顧問であり、KPMGジャパンのシニアアドバイザーの中島 淳一と、あずさ監査法人 会計・開示プラクティス部の関口 智和との対談により、サ
2023年3月期から、有価証券報告書でのサステナビリティ情報開示が本格的に始まり、日本企業は新たな転換期を迎えています。気候変動への対応に加え、人的資本開示の重要性が高まるなか、企業の持続的な成長と環境・社会課題の解決の両立が求められています。
2024年には、生成AIの普及に伴う電力消費量の急増など新たな課題も浮上し、企業の開示姿勢や具体的な対応がよりいっそう問われています。また、金融審議会ではサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が開発するサステナビリティ開示基準に基づく開示や保証についての議論も本格化しています。
今回は、元金融庁長官でKPMG税理士法人の特別顧問であり、KPMGジャパンのシニアアドバイザーの中島 淳一と、あずさ監査法人 会計・開示プラクティス部長の関口智和との対談により、サステナビリティ情報開示の背景と日本企業が目指すべき方向性を明らかにしています。

| 中島 淳一 KPMG税理士法人 特別顧問、KPMGジャパン シニアアドバイザー 東京大学工学部卒業。1985年大蔵省入省、2013年金融庁総務企画局総務課長、2014年総務企画局参事官(信用担当)、2016年金融庁審議官、 2018年金融庁総合政策局総括審議官兼金融研究センター長代行、2019年金融庁企画市場局長、2020年 金融庁総合政策局長、2021年金融庁長官。現在に至る。 |
スチュワードシップ・コード改定から始まったサステナビリティ戦略
関口
中島顧問は、これまで金融庁で企画市場局長、総合政策局長、さらには長官として、金融業界の中心として活躍されてきました。まずは、サステナビリティ情報の開示や保証というテーマについて、これまでどのように取り組んでこられたかをお話いただけますでしょうか。

| 関口 智和 あずさ監査法人 会計・開示プラクティス部長 1995年に朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)に入所後、2000年から2年間アーサーアンダーセンニューヨーク事務所に赴任。2024年より会計・開示プラクティス部長として会計・開示に関する品質管理の責任を担うとともに、サステナブルバリュー本部 副本部長としてサステナビリティ関連業務を担当している。加えて、2023年より、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のTransition Implementation Group のメンバーに加入し、KPMGネットワークの代表を務めている。 |
中島
企画市場局長時代のスチュワードシップ・コード改定が、サステナビリティとの本格的な関わりの始まりでした。改定にはサステナビリティの要素を考慮するという内容を盛り込みましたが、これは大きな決断でした。当時は投資における経済的リターンを重視すべきという立場から、サステナビリティ要素の考慮に反対する意見も強くありました。これは今でも米国で議論のある問題ですが、そのなかで実現できたことは、私にとって印象深い出来事です。
2020~2021年には総合政策局長として、菅政権による2050年カーボンニュートラル宣言を受けてサステナブルファイナンス有識者会議の立ち上げを担当しました。金融庁全体として取り組むという方針から総合政策局に設置し、人選からアジェンダ設定、取りまとめまで一貫して携わりました。数ある総合政策局長の仕事のなかでも、思い出深い取組みとなりました。
さらに金融庁長官の時に岸田政権下で「新しい資本主義」が提唱され、気候変動対策は継続しつつ、成長と分配の好循環という観点から人への投資が政策課題として掲げられました。サステナビリティの文脈でも、人権や人的資本も検討項目でしたので、政権の掲げる方針をサステナビリティの枠組みのなかで正面から取り組むことができました。
また、当時はIFRS 財団のISSB(国際サステナビリティ基準審議会)による基準開発の議論が活発化していましたが、日本は当初からこれを積極的に推進する方針を掲げていました。現在、まさに有価証券報告書への具体的な組み込み方について議論が進められており、非常に高い関心を持って見守っているところです。
有識者会議で新時代の資本市場像についての議論が本格化
関口
今お話にありましたように、サステナビリティ情報の開示は、2020年9月に発足した菅政権下でのカーボンニュートラル宣言が大きく影響したと思います。宣言のなかで2021年4月に2030年温室効果ガス削減目標を引き上げることも表明され、それを受けてサステナブルファイナンス有識者会議が立ち上がりました。その狙いをお聞かせください。
中島
2015年のパリ協定以降、金融分野でもTCFDによる開示フレームワークの議論が進み、気候変動問題については国際的な議論が活発化していました。このため、当初は金融庁でも国際部門を中心に対応していました。2019年に、チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサーを設置しましたが、まだ国内部門では「海外の話」という認識が強かったですね。
しかし、菅政権が2050年カーボンニュートラルを宣言したことで、金融庁全体、そして政府全体で取り組むべき課題だということが明確になりました。特に2021年はCOP26のグラスゴー開催を控え、2030年に向けたカーボンニュートラルへの道筋を示す重要な年でした。そのため、2020年末から日本としての取組みと発信を意識した議論を開始しました。
金融庁による有識者会議の立ち上げは、大きな注目を集めました。金融機関は「金融庁は具体的に何を始めるのか」と関心を持ち、企業関係者も「実際に何か動き出すかもしれない」と受け止めました。学者や有識者の方々も、行政、特に金融分野での実行力を持つ金融庁が本格的に動き出したことで、議論が本格化しました。
有識者会議では、まず日本としてのサステナブルファイナンスへの取組み方という基本的な考え方を整理し、そのうえで開示を中心とした具体的な施策を議論しました。金融庁が主導する以上、一方的な議論ではなく関係者のコンセンサスづくりを重視しました。現在も、この時の議論が基礎となっていると考えています。
関口
金融庁の動きは金融機関への影響はもちろん、開示を通じて企業全般にも大きな影響を及ぼします。その意味で、有識者会議の設立は非常に大きなアナウンスメント効果があったと感じています。
二元論を超えた日本型アプローチ「トランジション・ファイナンス」の模索
関口
サステナビリティ情報開示の議論において、EUタクソノミーへの対応が大きな論点だったと記憶しています。タクソノミー情報の開示を日本の制度に導入すべきかについてはどんな議論が交わされたのでしょうか。
中島
EUタクソノミーに対する日本の取組み方や考え方は、有識者会議でも議論の重要な対象となりました。当時、特に経済界からは反発の声もありました。私自身も技術や取組みを「グリーン」か「非グリーン」かに二分し、グリーンなものには投資を促進し、そうでないものからは資金を引き上げるという考え方は、あまりに単純で乱暴だと違和感がありました。
たとえば、日本の主要産業である自動車産業で言えば、EVはグリーンで他は非グリーンだと分類になります。しかし、ガソリン車からハイブリッド車への移行でも、二酸化炭素の排出量は大幅に削減できます。このように、分類の仕方によってさまざまな影響が出てくる。EUタクソノミーのような制度を導入し、分類方法の議論に終始してしまうのは、生産的ではないと考えました。
そこで日本は、経済産業省を中心に「トランジション・ファイナンス」というアプローチを提唱しました。炭素を排出する産業が脱炭素への移行するための支援を目的とした金融の流れを作るという考え方です。単純な二分法ではなく、脱炭素技術の開発や設備投資への資金提供を促進する方針を打ち出したわけです。このトランジション・ファイナンスは有識者会議でも議論され、現在では日本から海外に向けても発信しています。今や世界的な主流の考え方になりつつあると感じています。
関口
二元論を好まない日本の国民性かもしれませんが、EUタクソノミーのような白黒つける方式は日本では馴染みにくいと感じていました。日本政府が推進するトランジション・ファイナンスは、欧米とは異なるアプローチでサステナブルファイナンスを進めようとする日本の意思を示したものだと理解しています。

投資家にとって有用な開示「シングルマテリアリティー」にフォーカス
関口
企業開示においては、環境への影響を示すインパクト・マテリアリティーと、環境リスク・機会が企業に与える影響を示すファイナンシャル・マテリアリティ―という2つの要素への対応が重要ですが、それはどのように議論されたのでしょうか。
中島
そうですね。金融庁は気候変動そのものへの対応よりも、金融監督当局として、有価証券報告書における開示を念頭に、ファイナンシャル・マテアリティ―に焦点を当てて議論を進めました。サステナブルファイナンスを通じて資金の流れを作ることがわれわれの役割だと考えていたからです。
環境関連の立場からは、企業活動が経済・社会・自然に与える影響も含めて、より多くの開示を求める声が強かったのですが、金融庁やIFRS財団のISSBは、まずは投資家にとって有用な開示、つまりファイナンシャル・マテリアリティ―に焦点を当てる方針を採りました。
私は、開示は多ければ良いというものではないと考えています。また、開示制度の設計にあたっては、企業の負担という面だけでなく、投資家が他社との比較や過去との比較を通じてどのように投資判断を行うかという観点に立ち返って考える必要があります。そのため、開示資料には比較可能性や再現性が求められます。特に気候変動に関する開示は始まったばかりということもあり、まずは財務への影響に関する開示を優先して進めてきました。これは国内での議論だけでなく、海外に向けても日本の立場として発信してきました。
関口
1ヵ月ほど前、アジアコーポレートガバナンスアソシエーション(ACGA)主催の円卓会議に参加した際、投資家から興味深い意見がありました。すなわち、これまでのGRIに基づく開示にはさまざまな指標があったが、投資判断とは関係が薄いものが多く含まれており、正直見ていなかったが、ISSBの基準に基づく情報は、投資家が意思決定するためという目的に絞り込んだ開示として大いに活用したいということでした。まさに中島顧問と同じ認識を投資家の方々も持っているという印象を受けました。
日本のサステナビリティ開示の二本柱は、気候変動開示と人的資本開示
関口
その後、岸田政権下で「新しい資本主義」が提唱され、資産運用立国構想や人的資本が大きく掲げられました。それらの背景や狙いをお聞かせください。
中島
2021年10月に発足した岸田政権は、「成長と分配の好循環」を掲げ、特に働く人々の所得増加を重視しました。金融分野では、資産所得の増加が重要なテーマとなったのはご存じの通りです。
日本の家計金融資産は2,000~3,000兆円規模ですが、その約半分が現金預金で、十分なリターンを生んでいません。一方、米国やイギリスでは、より多くが投資商品に向けられ、そのリターンが家計の資産形成につながっています。この状況を改善するため、日本でも資本市場を活用することを政権として議論したわけです。
ただし、この課題は金融庁が20年以上前から、さらにアベノミクス以降も取り組んできた課題です。資本市場に関する政策の難しさは、多くの関係者の行動変容が必要な点です。個人の投資行動の変化、金融機関による適切な商品提供、運用会社による高度な運用、そして企業自体の収益力向上が求められます。特に、家計の金融資産リターンの源泉となる企業の中長期的な価値向上が重要であるため、機関投資家と企業間のコーポレートガバナンスにも注力してきました。
人的資本に関する開示の背景には、企業の収益源が設備から知的財産などの無形資産へシフトしていることや、人口減少下で人材の重要性が高まっていること、さらに女性活躍の課題、コロナ禍で見えてきた新しい働き方、デジタル時代のリスキリングの必要性などがあります。岸田政権の政策は、これらの既存の議論を生かす形で展開されたものだといえるでしょう。
関口
そうすると、菅政権下での気候変動開示への対応と、岸田政権下での人的資本開示の推進が、日本のサステナビリティ開示の二本柱としてそろったということでしょうか。
中島
その通りです。サステナビリティは単なる「いいこと」ではなく、経営戦略の中核として位置づけられるべきものです。最近は特に、サステナビリティへの取組みを通じた中長期的な企業成長という観点で議論されるようになってきました。
関口
確かに金融庁も最近、人的資本戦略と経営戦略の結びつきが不十分な点を指摘していますね。今のお話を聞いて、その背景がよく理解できました。
非財務情報の開示から見えてくる、企業価値の向上への道筋
関口
中島顧問が金融庁長官だった2023年3月期から、いよいよサステナビリティ情報の開示が義務化されました。同年7月にはコーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクションプログラムが公表されましたが、その狙いやポイントはどこにあったのでしょうか。
中島
2023年7月のアクションプログラムは非常に画期的な取組みでした。これは、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードの3年ごとの見直しと、2022年4月の東証市場区分再編という制度整備の成果の上に立っています。
このプログラムの特徴は、新たなルール追加ではなく、既存制度内での実質的な価値向上を目指す点です。金融庁や東証も、企業への一方的な指示ではなく、対話的なアプローチを採用しました。また、日本企業の課題であるPBR(株価純資産倍率)の低さにも正面から向き合い、成長性・収益性の向上と、人的資本を含めたサステナビリティへの取組みを重点項目としました。
サステナビリティ情報の開示は、2017年頃からの任意開示から、より信頼性の高い有価証券報告書における開示へと発展しました。これは企業の開示実務全体に大きな変化をもたらすものでした。
義務化の効果は大きかったと感じています。各上場企業で経営レベル、取締役会レベルでの議論が必要になり、特に先進的な企業では、現状評価、将来目標、戦略、KPIを経営戦略の中に位置づける動きが見られます。一方で、まだ戸惑いを見せる企業も存在しています。そういった企業に対しては、好事例の共有や分析結果の提供を通じて、段階的な改善を期待しています。
関口
開示義務化は、先進企業の取組みを可視化するだけでなく、これまで取組みが進んでいなかった企業に気づきを与え、約4000社の上場企業全体に意識づけを促す効果があったように見えます。
中島
そうですね。開示の義務化により、投資家や監査法人による分析も可能になりました。たとえば、KPMGの分析では、女性管理職比率とPBRの相関関係が示されました。これは、女性活躍に取り組む企業の将来性を市場が評価している可能性を示唆しています。
ESG情報の開示は、必ずしもすぐに利益に結びつくものではないため、企業側にも戸惑いがあるかもしれません。しかし、投資家による評価や分析が蓄積されていけば、企業価値向上への道筋が見えてくるはずです。EDINETのXBRL化など、分析環境の整備も進んでおり、今後の展開が期待されます。
関口
KPMGは分析結果を報告書で公表しましたが、多くの問い合わせがあり、メディアからも注目されました。このような気づきの共有が、開示の質の向上につながっていくと実感しています。今後もデータに基づく分析を通じて、議論を深めていきたいと考えています。
中島
企業のサステナビリティへの取組みは、開示を通じて可視化され、それが投資家の評価を経て、最終的には資金調達の円滑化や企業価値の向上につながっていく。そういった好循環が生まれることを期待しています。まだ始まったばかりですが、この動きが日本のコーポレートガバナンスの新しいページを開くことになるのではないでしょうか。

開示制度の本質は、実効性ある取組みとの好循環の創出
関口
2023年3月期からの有価証券報告書におけるサステナビリティ情報開示の開始に加えて、欧州ではCSRDに基づく報告が開始されています。こうした動きを踏まえ、日本の今後の対応に関するお考えについてお聞かせください。金融審議会では、SSBJ基準に基づく開示や保証について議論が進んでいますね。
中島
気候変動対策は、ますます重要性を増していると感じています。2024年の世界的な猛暑に加え、生成AIの普及による電力消費量の急増も大きな懸念材料です。特にGPUの製造・使用による電力消費量の増加は深刻な予測となっています。
こうした状況下で、企業は生成AIやデータセンターの利用も含めた電力使用量を、正確に把握する必要があります。金融審議会でのSSBJ基準に基づく開示の議論も重要ですが、単なる開示の拡大ではなく、気候変動対策としての実効性という観点も重要です。経営者の意識改革、使用量削減、代替エネルギーへの投資、省電力半導体の開発など、具体的な行動につながる開示であるべきです。
直近の金融審議会では、2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業に対して、開示を開始し、1年後から保証を導入する方針が示されました。グローバルな資本市場において、日本だけが突出した開示を求めることは企業の競争力を損なう可能性があります。一方で、他国が開示するなかで日本企業だけが開示しないことは、資金調達の面で不利になります。米国の気候関連開示の行方が不透明ななか、国際的な動向を見極めつつ、バランスの取れた開示制度を構築する必要があります。特に、GHG排出量の開示は、企業の中長期的な成長性や価値を計る重要な指標となっています。気候変動が重要課題となる中で、企業のトランジション(脱炭素への移行)をどのように進めていくのか、その過程でスコープ1・2の情報が特に重要になってきています。
金融審議会での議論を踏まえると、保証はスコープ1・2の情報や、ガバナンス・リスク管理に関する開示から段階的に始められる予定です。投資家にとって情報の正確性は重要ですが、非財務情報には将来予測やストーリー性が含まれ、物理的リスクや移行リスクの評価も前提条件によって大きく変わります。そのため、保証のあり方についても、各国の状況や関係者のニーズを踏まえた議論が必要です。
また、企業の自主的な開示意欲を引き出すことも重要です。開示が資金調達に有利に働くと認識できれば、企業は積極的に情報を開示するでしょう。しかし、単なる負担増として捉えられては、形式的な対応に終わってしまう恐れがあります。関係者の納得感を得られる開示内容や議論の進め方を丁寧に考えていく必要があります。
関口
気候変動への対応がグローバルに大きな課題となっていくなかで、企業がカーボンバジェットという制約を踏まえてどのようなイノベーションを実現し、それを通じて成長していくのかが一層重要になっているように思います。ただし、過度な開示要求は競争力を損なう可能性もあり、資本市場での活用を前提とした適切な情報開示と信頼性の確保が求められますね。
中島
そのとおりです。完璧な制度を一度に作るのは難しいかもしれませんが、その時々の状況に応じたベストな選択を積み重ね、改善を重ねていくことが重要だと考えています。拙速な制度導入は逆効果になる可能性もありますので、脱炭素に向けて着実に一歩ずつ進めていくことが大切です。
サステナビリティ情報の開示は、単なる規制対応ではなく、企業の持続的な成長と地球環境の保全を両立させるための重要なツールとなるべきです。そのためには、開示基準の整備だけでなく、開示された情報が実際の投資判断や企業行動の改善につながる仕組みづくりも必要です。
金融庁の立場からすれば、市場機能を通じて企業の持続可能な成長を促進することが重要です。開示制度がその触媒となり、企業の積極的な気候変動対策や持続可能な事業モデルの構築を後押しする。そういった好循環を生み出すことが、今回の制度設計の本質的な目的だと考えています。
関口
サステナビリティ情報の開示は手段であって目的ではなく、最終的には開示を通じて企業の持続的な成長と環境問題の解決の両立を図っていくことが重要ですね。その意味で、今後の制度設計においては、実効性と実務上の負担のバランスを慎重に検討していく必要があると感じています。
次世代の共感も呼ぶサステナビリティ経営に期待
関口
最後に、サステナビリティ課題への取組みや情報開示の対応について、メッセージをお願いします。
中島
日本の最大の課題は、少子高齢化と人口減少だと考えています。企業にとって、若手人材の確保は生き残りのための重要な課題です。今の若い世代は、「気候変動は大丈夫なのか」「自分の会社は真剣に取り組んでいるのか」「人材育成はどうなのか」「働く環境は整っているのか」など、自分たちの10年後、20年後の将来に強い関心を持っているように思います。今回は、開示について資本市場を前提に議論してきましたが、実は情報に関心を持っているのは投資家だけではありません。企業で実際に働く従業員や就職を考える学生たちも、企業間の比較をしながら、自分のキャリアを考えているのです。そういう意味で、開示担当者だけでなく経営に携わる方々にも、サステナビリティ開示の議論に注目していただきたい。それは自社の経営戦略であり、特に若い世代へのメッセージとしても重要です。各企業の積極的な取組みを期待しています。
関口
大変貴重なお話をお伺いでき、私自身とても勉強になり、また刺激を受けました。ありがとうございました。

(左)KPMG税理士法人 中島 淳一(右)あずさ監査法人 関口 智和