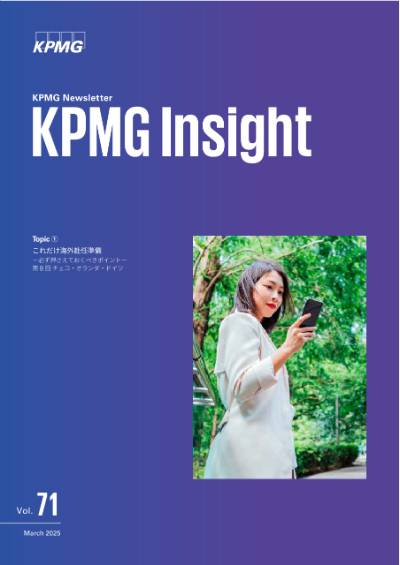これだけ海外赴任準備-必ず押さえておくべきポイント-第8回 チェコ・オランダ・ドイツ
本稿では、欧州における主要な規制動向を詳しくご紹介します。
本稿では、欧州における主要な規制動向を詳しくご紹介します。
近年、欧州連合(EU)では環境保護やデジタルセキュリティに関する新たな規制が次々と導入されています。これらの規制は、持続可能な社会の実現と企業の競争力維持を目的に、環境保護やサイバーセキュリティの強化を図ろうとするものです。これらの規制は国際的に大きな影響力を持つことから、日本企業にとっても重要なトピックスといえるでしょう。
そこで、本稿では、EUが2026 年から本格導入を予定している炭素国境調整メカニズム(CBAM)をはじめ、森林破壊防止規則(EUDR)、サイバーレジリエンス法(CRA)、改正ネットワークおよび情報セキュリティ指令( NIS2 指令)、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)、企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)など、欧州における主要な規制動向を詳しくご紹介します。
さらに、EU各国のアップデート情報として、チェコ、オランダ、ドイツに関する法律・会計・税務関連情報についても、特筆すべき内容をご紹介します。
本号を通じて、欧州の最新動向を理解し、今後のビジネス戦略に役立てていただければ幸いです。なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。
※当該情報は2月21日時点の情報に基づいております。発行日時点の最新の状況を表していない可能性もある点ご了承ください。
Point
欧州連合(EU)では、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)や森林破壊防止規則(EUDR) 、サイバーレジリエンス法(CRA)など、環境保護とデジタルセキュリティを強化するための新たな規制が導入されており、その動向を注視する必要がある。 チェコ オランダ ドイツ |
Ⅰ.EUにおける全体的な規制動向
本稿では、近年EUにおいて相次いで導入されているESGやデジタル関連の新規制のなかから、特に影響の大きい規制について説明します。今回ご紹介する規制以外にも、EUでは多くの新たな規制が導入されていますので、ご留意ください。
1. 企業サステナビリティ報告指令 (CSRD)
欧州委員会(EC )がCSRDを発効したことに伴い、EU域内の50,000社以上の企業がサステナビリティ関連の開示を義務付けられました。それに伴い、アニュアルレポートの焦点も、株主からより幅広いステークホルダーを意図したものへと移行することとなりました。
2024年度に最初に報告する企業グループは、大規模な社会的影響度の高い事業体( 通称Large PIEs )です。2025年度からはLarge PIEs以外の大企業、具体的には売上高5,000万ユーロ、総資産2,500万ユーロ、従業員数250名超の3つの条件のうち2つ以上の条件を満たす企業が対象となります。また、EU域内で1億5,000万ユーロ以上の売上高がある場合、EUの大企業/グループとその子会社だけでなく、EU域外の親会社にも影響を及ぼします。
さらに、サステナビリティ報告書はアニュアルレポートの一部として提供され、報告の初年度から限定的な保証( レビュー)の対象となります。
2. 企業サステナビリティ・デュー・ ディリジェンス指令(CSDDD)
CSDDDは、企業のバリューチェーンにおける実際のまたは潜在的な人権および環境に関連する負の影響を評価し、防止し、緩和するため、リスクに基づいた
デュー・ディリジェンスを実施することを求める指令です。CSDDDにおけるデュー・ディリジェンスは「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス(OECDガイダンス)」を基にしており、CSDDDに基づくデュー・ディリジェンスはCSRDに基づくサステナビリティ報告の開示事項の一部を構成しています。そのため、EUバッテリー規則等のバリューチェーンにおける人権・環境リスクを評価・対応を求める規則とも親和性が高くなります。
また、一部加盟国で先行していたデュー・ディリジェンス規則をEU加盟国全体にわ
たり標準化することにより、欧州各国・地域で事業活動を行う企業にとって、より要求事項が明確化されることとなります。デュー・ディリジェンスに含まれるステップは以下のとおりです。
- 責任ある企業行動を企業方針および経営システムに組み込む
- 人権や環境に対する実際のまたは潜在的な負の影響を特定、評価し、優先順位を付ける
- 負の影響を防止、軽減、または阻止し、必要に応じて是正措置を講じる
- 通知メカニズムと苦情処理手順を確立し、維持する
- 講じられた対策の有効性を監視し、デュー・ディリジェンスについて開示する
- パリ協定に沿った移行計画を採択し、実施する
- CSDDDは以下の企業が対象となります。
- 従業員数1,0 0 0名以上かつ売上高4 億5,000万ユーロ以上のEU域内企業
- EU域内売上高が4億5,000万ユーロ以上のEU域外企業
- 欧州においてフランチャイズまたはロイヤルティ契約( 共通のアイデンティティ、ビジネスコンセプト、統一されたビジネス手法の導入を担保するもの)をグループ外企業と締結しており、当該ロイヤルティ収入が2,2 5 0万ユーロ以上かつ売上高(EU域外企業はEU域内売上高)が8,000万ユーロ以上の企業
CSDDDは2024年7月に発効され、その後2 年以内にEU加盟国で国内法制化されることになっています。2027~2029年は移行期間として、企業規模に応じて適用対象開始時期が定められています。
3. 炭素国境調整メカニズム(CBAM)
CBAMはEU域外からの輸入品に対して炭素価格を課すことを目的とする制度です。EU域内での炭素排出量削減努力を補完し、EU域外からの安価な炭素集約型製品の流入を防ぐための措置で、2026年1月から本格適用となりました。対象は鉄鋼、セメント、肥料、アルミニウム、電力などの産業で、これらの製品の輸入業者に対して、炭素排出量に応じた証明書の購入を義務付けます。2023年10月から移行期間が始まり、2026年1月からの本格適用に向けて、輸入業者は四半期ごとに排出量を報告する必要があります。
この制度は、EUの「Fit for 55」政策パッケージの一環として、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で少なくとも55%削減する目標を支えるものです。
導入の狙いは、EUの産業競争力を維持しつつ、グローバルな気候変動対策を促進することです。これにより、EU域内の企業が不利な競争条件にさらされることを防ぎ、同時に他国・地域にも炭素排出削減の取組みを促す効果が期待されています。また、CBAMは国際貿易における公平性を確保するための手段としても位置づけられており、各国・地域の政策決定者や企業にとっても重要な関心事となっています。
4. 森林破壊防止規則(EUDR)
EUDRは森林破壊防止を目的とした規制で、大豆、パーム油、牛、コーヒー、カカオ、ゴム、木材(これらの由来製品含む) に適用されます。EUDR発効後に対象製品をEU市場に投入、もしくはEUから輸出するためには、同製品が森林破壊の起きた土地で生産されていないこと、生産国の法令に従って生産されていることの確認、デュー・ディリジェンス報告書の提出が求められます。
当初は2024年12月30日から適用開始の予定でしたが、2024年10月に1年延期が公表され、2025年12月30日から適用開始される予定です。
5. サイバーレジリエンス法(CRA)
CRAはデジタル要素を備えた製品のサイバーセキュリティを高めることを目的とした規制で、デジタル要素を備えた製品( 自動車部品等一部例外あり)の製造業者、輸入業者、販売業者に適用されます。特に製造業者に対しては、対象製品のライフサイクル全体( 開発段階から製品寿命まで)のサイバーセキュリティの確保を求めるなど、さまざまな要求事項が含まれています。
CRAは2024年12月に発効しており、段階的な施行を経て、2027年12月11日に全面施行します。
詳細はKPMGのウェブサイト「EUサイバーレジリエンス法がもたらす日本企業への影響とは」1をご参照ください。
6. 改正ネットワークおよび情報セキュリティ指令(NIS2指令)
NIS2 指令はEU域内のサイバーレジリエンスを向上させるためのEU指令で、対象となる18のセクターで製品・サービスを提供する一定規模以上の企業に適用されます。対象企業の経営者はサイバーセキュリティを高いレベルにするための要求事項を遵守する責任を負い、セキュリティインシデントの報告義務が課されます。
NIS2指令は2023年1月に発効、現在各EU加盟国で国内法制化が進められています。詳細はKPMGのウェブサイト「改正ネットワークおよび情報セキュリティ指令(NIS2指令)」2をご参照ください。
Ⅱ.各国アップデート
1. チェコ
チェコに関するアップデート情報は次のとおりです。
(1) 就労許可取得要件の緩和
2025年1月時点で、日本を含む10ヵ国の国民は、チェコでの就労にあたり労働当局からの労働許可が不要となります。これにより、長期就労にあたり、労働許可を待つ必要がないため、人材派遣の行政手続きが大幅に簡素化されます。ただし、長期就労の場合は引続き滞在許可( ブルーカード、就労カード等)の取得が必要である点に注意が必要です。
就労に付随する論点として、運転免許証の交換に関する注意点が挙げられます。日本とチェコは運転免許証の交換制度が適用されることから、チェコで再度運転免許証を取得する必要はありません。ただし、2024年1月以降は、暦年で185日以上チェコに滞在していることが交換の条件となります。あくまで「暦年」のため、翌年になるとカウントがリセットされ、再度185日経過するまで交換ができない点にご留意ください。
(2) リース会計の変更
日本基準やIFRS会計基準と異なり、チェコではリースの借り手はリースに係る費用をすべて期間損益として処理します。現在、チェコの会計法の改正が議論されており、IFRS会計基準への整合が検討されています。改正された場合には、すべてのリースについて使用権資産とリース負債が求められ、減価償却および支払利息の計上が行われることとなります。これらの変更は2026年1月以降開始する事業年度からの適用が予定されているものの、現時点では草案段階であり、国会での成立が待たれる状況です。
日本企業の場合、連結パッケージへの組替えが行われていると考えられるため、連結仕訳や開示への影響について確認することを推奨します。
(3) 移転価格税制と税務調査
最後に、移転価格税制上の注意点についてお伝えします。移転価格の分野における税務調査の件数は、2013年の282件から2023年には570件と過去10年で倍増しており、税務当局が最も重視する分野となっています。最近の傾向としては、リスクと機能の分析に焦点を当て、本格的製造会社から受託製造会社への分類変更による過年度の欠損の否認が散見されている状況です。特に、昨今のインフレ影響を受けて、2~3年にわたり損失を計上してきた製造子会社に関しては、税務調査および追徴課税のリスクが高まっています。そのため、自社の移転価格税制上のリスクと機能について、本社とのすり合わせを行うことを推奨します。
2. オランダ
オランダの税務コンプライアンスおよびオランダ会計基準の特徴は次のとおりです。
(1) オランダの税務コンプライアンス
法人税所得税申告期限は、原則決算日後5ヵ月以内ですが、11ヵ月の延長が可能です。予定納税額は、過去の納付実績に応じて、事業年度開始後1~2ヵ月以内に税務当局より通知されます。また、ハイブリッドミスマッチ対策税制( ATAD2 )に基づく文書も備えておく必要があります。
移転価格関連では移転価格ポリシー、マスターファイル、ローカルファイルの文書を申告日までに備えておく必要があります。さらに、連結売上高7億5,000万ユーロ以上のグループ子会社の場合、Country byCountry Reporting(CbCR:国別報告書) が最終親会社で提出される旨の通知を、オランダ税務当局に対して行う必要があり ます。
配当にかかる源泉税は、源泉税申告を配当宣言後1ヵ月以内に、オランダ税務当局に提出する必要があります。ただし、源泉税が免除される場合は、同期限内に配当にかかる通知をオランダ税務当局に対して行います。なお、利息およびロイヤルティにかかる源泉税は暦年単位であり、翌年1月末までに申告が必要です。
付加価値税(VAT)の申告は、月次または四半期単位です。各々の申告期限は対象期間の翌月末までです。
(2) オランダ会計基準
IFRS会計基準が導入された当初、オランダ会計基準はIFRS会計基準とのコンバージョンを急速に進めました。しかし、上場企業は、連結財務諸表にはIFRS会計基準の適用を採用し、オランダ会計基準適用していません。そこで、オランダ会計基準委員会(DASB )は、オランダ会計基準を非上場会社向けの基準として位置づけました。そのため、IFRS会計基準とのコンバージョンは鈍化しています。
一方で、グローバルでIFRS会計基準を適用しているグループの子会社の財務報告の効率性を鑑み、オランダ会計基準を適用しつつ、IFRS9の期待信用損失モデルの適用、IFRS15および16 の適用を可能とするオプションがあります。
3. ドイツ
ドイツ赴任にあたり知っておくべき項目について、ドイツ企業法を中心にご紹介します。
(1)取締役の責任
ドイツの法令には、ドイツ有限会社の取締役が負うべき注意義務として、資本金の半額を喪失したことが判明した時に遅滞なく総会を招集する義務等が規定されています。注意義務に違反した取締役はドイツ在住か否かにかかわらず、個人財産で無制限に連帯責任を負うことになります。したがって、取締役に就任する場合は、自らの義務について正確な理解が必要となります。
(2)会社区分と会計監査
ドイツの企業は、売上高、総資産、従業員数の3つの基準値により小会社、中会社、大会社に区分されます(図表1参照)。これらの基準値のうち、2基準以上の条件を2事業年度連続で満たした年度より、その区分に変更されます。
会社区分が小さくなるにつれて、財務諸表の作成・開示義務も簡略になります。また、中会社と大会社は会計監査を受ける必要があります。決算書を決算日以後12ヵ月以内に開示しない場合には、ペナルティが科されます。
(3)ドイツ会計基準
ドイツ企業の資金調達は銀行融資が中心だったこともあり、ドイツ会計基準は債権者保護を目的として発達してきました。
そのため、「理性的な商人の判断」に従い、日本基準やIFRS会計基準等他の主要な会計基準に比べてやや保守的な会計処理が求められます。
(4) 就労目的の滞在許可
日本国籍を有する人は、ビザなしで90日間ドイツに滞在することが可能です。また、90日を超えてドイツに滞在する場合は、ビザなしでドイツに入国した後に滞在許可を申請することができます。ただし、ドイツに入国しても、就労目的の滞在許可取得までは就労できないこと、最近90 日以内に滞在許可を取得できないケースが出てきていることから、状況に応じて日本でビザを取得しておいたほうがよい場合も考えられます。
また、付随論点として、ドイツで車を運転する際の注意点を挙げます。ドイツでは、日本の運転免許証に加えて、そのドイツ語訳もしくは国際運転免許証を携帯することで、ドイツ入国から6ヵ月間はドイツ国内での運転が可能となります。それ以降の期間に運転する場合は、ドイツの運転免許証への書換えが必要ですが、日本の運転免許証とそのドイツ語訳があれば、ドイツでの住民登録後、無試験での書換申請が可能です。
図表1 ドイツ会社区分の基準値
| 小会社 | 中会社 | 大会社 | |
|---|---|---|---|
| 総資産(千€) | 7,500以下 | 25,000以下 | 25,000超 |
| 売上高(千€) | 15,000以下 | 50,000以下 | 50,000超 |
| 従業員数 | 50人以下 | 250人以下 | 250人超 |
出所:KPMG作成
1 EUサイバーレジリエンス法がもたらす日本企業への影響とは:
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/07/cyber-resilience-act.html
2 改正ネットワークおよび情報セキュリティ指令(NIS2指令):
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2024/02/cyber-nis2-security.html
執筆者
KPMGチェコ
末正 響/マネジャー
KPMGオランダ
藤末 亮太/シニアマネジャー
KPMGドイツ
田岡 有/シニアマネジャー