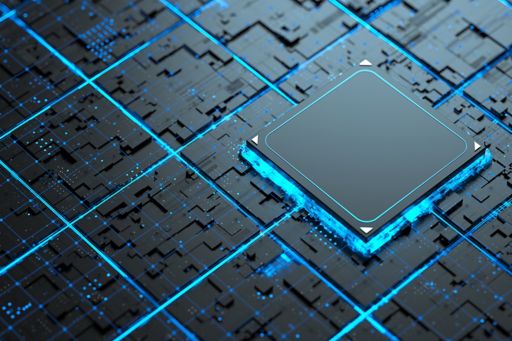サステナブルなオペレーション変革のポイントー製造業のSX実現に向けてー
企業経営におけるサステナビリティ対応が、必ずしも事業・機能部門のオペレーションの実態に反映されていない状況があります。製造業における真の持続性、企業価値の向上に、エンジニアリングチェーンマネジメント(ECM)とサプライチェーンマネジメント(SCM)へのサステナビリティの実装について解説します。
エンジニアリングチェーンマネジメント(ECM)とサプライチェーンマネジメント(SCM)におけるサステナビリティ対応のポイントと直面する課題、目指すべき方向性を考察します。
昨今では、企業経営におけるサステナビリティ対応の重要性が「当たり前」なものになりつつあります。全社的な掛け声や対外的な開示強化が図られる一方で、事業部門や機能部門といったオペレーションを支える実務部門、すなわち現場層においては依然として「コスト増をどう正当化するのか「結局は建て前やポーズだけではないか」といった冷めた声も根強く聞かれます。こうした意識差を乗り越え、製造業において、サステナビリティ経営を真の持続性、真の企業価値につなげるためには、製造業にとってのコアなオペレーションである「エンジニアリングチェーンマネジメント(以下、「ECM」という)」と「サプライチェーンマネジメント(以下、「SCM」という)」におけるサステナビリティの実装が欠かせません。本稿では、わが国の製造業にとっての、これらのオペレーションにおけるサステナビリティ対応のポイントと直面する課題、そして今後目指すべき方向性について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。
目次
POINT1 サステナブル経営に向けた実務オペレーションの作り込み
サステナブル経営の実現には、方針づくりや開示の取組みだけでなく、サステナビリティを機会として捉えた現場部門によるECMやSCM等のオペレーションの作り込みが重要となる。
POINT2 ECMのサステナビリティ対応:サーキュラー型製品への移行
サーキュラー型製品への移行には、顧客のサステナビリティ課題の定量的な可視化と、提供する付加価値の明確化を行ったうえでサーキュラー化施策を選定することが求められる。また、製品の企画・開発現場でサーキュラー化施策が確実に実行される仕掛けづくりも必要となる。
POINT3 SCMのサステナビリティ対応:サステナブル調達の加速
サステナブル調達を実現するには、一部のサステナビリティ担当者のリソースだけでは足りない。購買担当者やサプライヤー自身に対する知識・スキルレベルの把握を行ったうえで、教育・研修、サポートによる底上げが必要となる。また、QCD観点だけでなく、ESGの観点でサプライヤーを評価できるスキルを高め、サプライヤーに対しても受け入れの体制(文化)を構築していくことも求められる。
POINT4 CMとSCMのサステナビリティ対応を支えるコーポレート機能
ECMとSCMのサステナビリティ化を進めるには、共通機能としてのコーポレート部門の支えが不可欠となる。サステナビリティのオペレーション実装を技術的にサポートする機能や、対外的な発信や説明を担う機能との連動が重要である。
I.サステナブル経営実現には実務オペレーションの作り込みが不可欠
企業のサステナビリティ対応に向けた社会的な、また資本市場等からの要請が強まっている昨今、製造業の経営者にとって「サステナビリティが事業継続上の最低条件である」という意識が広く浸透してきているようです。実際、サステナビリティ経営に係る方針策定や、工場やオフィスの再エネ利用推進などの施策を進めている企業が増えてきています。
一方、事業部門や機能部門といったオペレーションを支える実務部門、すなわち現場層においては依然として「サステナビリティ対応はコストがかかる」「法規制で求めていることをやればよい」といった意識が勝り、受け身的な対応で留まっている企業が多いように見受けられます。
脱炭素や資源循環、また人権への対応といったテーマをテコに企業価値を上げ、サステナブル経営を意味ある形で実現するためには、実務部門のオペレーションにおけるサステナビリティの「作り込み」が重要であると、筆者は考えます。
本稿では、製造業のコアなオペレーションであるECMとSCMに注目します。ECMでは製品企画・開発のサイクルを通じた付加価値の創出を目指し、SCMでは調達から物流、販売までのオペレーションを通じて開発された製品の安定的な市場投入をカバーします。これらのオペレーションにおけるサステナビリティ対応のポイントと、企業が一般的に直面するであろう課題を例示しながら、今後の企業が目指すべき方向性について解説します。
II.ECMのESG対応:サーキュラー型製品への移行
1.主要企業の取組み状況
これまで製造業はモノをつくる過程で、「採る」「作る」「捨てる」の直線的経済システム(リニアエコノミー)なものづくりを進めてきました。その結果、資源の過剰採取による生態系への悪影響、採取した資源の製錬時や加工時の炭素排出、製品使用後の廃棄による環境汚染などを引き起こしてきました。しかし、ESG対応が求められる現在においては、リニアエコノミー型なものづくりからサーキュラー・エコノミー(資源循環)型なものづくりへの転換が求められています。
サーキュラー・エコノミー型なものづくりとは、廃棄物を発生させず、新しい原材料の投入を極力抑え、資源循環のループが閉じている状態を目指すものです。日本では従来から3R(Reduce、Reuse、Recycle)政策が進められてきた経緯もあり、多くの製造業でサーキュラー・エコノミー型製品の開発が進められています。先進的な事例としては、複写機メーカーの取組みが挙げられます。プラスチック使用量削減のために筐体の薄肉化を行うReduce設計、製品寿命延命のために機種間における交換部品の互換性を高めた標準化設計の推進などが進められています。
2.企業が抱える課題
上記の例のように、一部の先進的な企業ではサーキュラー・エコノミー型製品を提供するため、製品の企画・開発段階からサーキュラー化施策の適用が進められてきていますが、資源循環のループが完全に閉じるような理想形の状態にするには、まだ多くの課題を解決する必要があります。
一方、技術進化のスピードが速い製品やコスト競争が激しい製品などでは、サーキュラー・エコノミー型製品への移行が進んでおらず、これから本格的な検討に着手すべきか悩まれている企業も多いと思われます。
上記のようにサーキュラー・エコノミーの導入状況は違えど、サーキュラー・エコノミー型製品の実現を目指す企業が直面する課題については共通した課題があります。以下では、その課題について述べたいと思います。
課題1:サーキュラー化施策の適切な選定
サーキュラー型製品の施策は、図表1のサーキュラー移行モデルに示すように、Reduce設計などのサーキュラー製品設計等の施策から、製品利用時のシェアリング、また利用後の再生、リサイクルなど多岐にわたります。
しかしながら、どの施策を採用することが自社や顧客にとっての重要なサステナビリティ課題を解決することになるのかを把握できず、本来必要な施策についても十分な検討がなされないまま、取組みやすいところから進めてしまうケースが散見されます。まずは、本来解決したいサステナビリティ課題の明確化が必要です。
図表1 サーキュラー移行モデル

PRE-USE(インプット)
- サーキュラーな製品設計プロセスへの変革
- オーダーメード型プロセスへの移行
- 需給コントロールのアジャイル化
- 環境負荷を踏まえたサプライチェーン構造の最適化
- 調達トレーサビリティ強化など
POST-USE(アウトプット)
- 回収・再利用プロセスの整備
- 製品の修理・再生や再販売プロセスの整備
- 効率的にサイクルを回すためのサプライチェーン機能再配置、など
出典:“Circular Revenue Models” (2019), KPMG
課題2:サステナビリティ対応と収益の両立
サーキュラー化施策を実施することで、廃棄物削減等のサステナビリティ価値を顧客に提供することはできますが、顧客がその価値に対価を払ってくれるとは限らないという問題があります。一部のサステナビリティ意識の高い顧客に対する販売は伸びるかもしれませんが、ターゲットとする顧客にそのサステナビリティ価値が本当に訴求できるのか、サステナビリティ対応により増加したコストを売価に反映しても目標の販売台数を達成できるか等についての推定が必要となります。
たとえば、販売した製品の回収率を高めようと製品売切りのビジネスモデルから、製品の所有権を企業においたままで製品で創出される成果のみをサービスとして提供するビジネスモデル(製品のサービス化)もサーキュラー化施策の1つとして挙げられますが、顧客サービスデスクの拡充や製品回収時の物流機能の構築による投資が必要となります。それらの投資を考慮しても、収益が成立するように売価を決定したとき、顧客が自社の製品・サービスを選択するかについての検討が必要となります。
課題3:サーキュラー化施策の確実な実行
優先的に実施すべき施策を決定しても、実際の製品開発時のプロジェクトにおいては、QCDが優先され、サーキュラー化施策の実施は結局見送られてしまうことがあります。ある産業機器メーカーでは、再生材の積極利用やリサイクルしやすいような設計を行うようにトップダウンで号令をかけていますが、コストの目標値の達成に目途が立たず、最終的には納期が優先され、従来どおりのバージン材の使用が決定されてしまうという事象が起きていました。結果的に機種ごと、はたまた同じ機種であってもプロジェクトによってサーキュラー化対応の差異が発生してしまいました。製品戦略立案や製品企画において決定されたサーキュラー化施策が、確実に製品に反映されるような仕組みをいかに構築するかがポイントなります。
3.課題解決の方向性
対応1:サステナビリティ課題の定量化
複数ある製品のサーキュラー化施策を選定するには、サステナビリティ課題の明確化から取り組む必要があります。まず自社製品で使用している資源のうち「何を循環させるのか(What)」と「なぜ、その資源を循環させる必要があるのか(Why)」を検討します(図表2参照)。
図表2 サーキュラー化のWhy/What

出典:KPMG作成
WhatとWhyの検討には、自社製品で使用されている資源のインフロー(製品製造時のバージン材、再生材の使用量)とアウトフロー(製品使用後の再生、廃棄の量)の量がどの程度なのかを定量化し、現状の資源循環による社会的、環境的インパクトの大きさを評価することが求められます。
たとえば、プラスチック精製段階で排出される炭素排出量やプラスチック廃棄時の燃焼による炭素排出量を上記のインフロー、アウトフローの数値から算出して、インパクトの大きさを定量的に見積ります。仮に、プラスチックの炭素排出量のインパクトが相対的に大きな割合を占めるとなれば、プラスチック(What)を脱炭素(Why)実現という目的から資源循環させるべきであると結論付けることができます。
B to Bの製造業では、さらに複雑な分析が必要となる場合があります。自社製品で循環させるべきと考えている資源と、顧客企業のそれが異なるケースがあるためです。その場合には、自社の分析に加え、顧客企業で扱っている資源や顧客業界のサステナビリティに対する動向調査も必要となります。
以上のように、サステナビリティ課題の大きさを定量的に可視化することで、解決すべき課題が把握でき、その課題解決に必要なサーキュラー化施策の候補を適切に検討することが可能となります。
対応2:サーキュラー化施策の顧客提供価値の明確化
次に、抽出したサーキュラー化施策の優先度付けを検討するために、その施策が顧客等に提供する価値が何かを明らかにすることが求められます。提供価値には、客観的に価値を評価でき、顧客の経済性に直結する提供価値(以下、「財務的な提供価値」という)と、サステナビリティ価値のような顧客が主観的に価値を評価し、経済性に直結しにくい非財務的な提供価値があります(図表3参照)。ハイブリッド自動車の例で示すと、低燃費という提供価値はコストという客観的な価値で評価でき、顧客の燃料費削減という経済性に直結するため、財務的な提供価値と言えます。一方、炭素排出削減というサステナビリティ価値は顧客の経済性に直結しないため、非財務な提供価値となります。
図表3 顧客提供価値の種類
| 財務的な提供価値 | 顧客が客観的に価値を評価でき、経済的な価値に変換が可能な価値(機能、性能、品質など) |
| 非財務的な提供価値 | 顧客が主観的に価値を評価するため、価値の大小が変わったり、経済的な価値への変換が容易でない価値 (デザイン、ブランド、環境価値など) |
出典:KPMG作成
施策の中には前述の製品のサービス化のように、その2つの提供価値が背反してしまうケースがあり、サーキュラー化施策の優先度付けや実施可否の選択を難しくしている原因となっています。
では、どのように施策の優先度付けを行えばよいのでしょうか。1つは、財務的な提供価値と非財務的な提供価値であるサステナビリティ価値の両立ができる施策を優先的に適用することです。シンプルな例として、耐久性や信頼性のニーズが強い製品は、従来どおりその耐久性や信頼性を他社より高めることが、サステナビリティな非財務的な価値と財務的な価値の両方の価値を提供する施策となります。特に、サーキュラー化施策の適用に社内のコンセンサスが取りにくい企業の場合は、両立するような施策から適用していくことがサーキュラー型製品への移行のファーストステップであると考えます。
2つ目は、現在はサステナビリティ価値である非財務的な提供価値しかないが、将来的には財務的な提供価値につながるような施策がどれかを推察して、優先度付けを検討することです。税制の動向がそのヒントの1つになります。炭素税やプラスチック税等すでにグローバルで適用の動きがありますが、自社のマーケットでそれらの税制が適用されるタイミングや影響の大きさを推測して、必要な施策を先行的に企画・開発しておくことが対応の方向性となります。
対応3:製品開発段階におけるサーキュラー化施策実行の仕組みの構築
施策を選定し、優先度付けを行った後は、複数の製品開発プロジェクトで確実にその施策が実行されるような仕組みの構築が求められます。財務的な提供価値と非財務的な提供価値が両立している施策であれば問題はありませんが、将来的に財務的な提供価値につながると予測しているサーキュラー化施策や、非財務なサステナビリティ価値の側面が強い施策を実行するには、製品の企画・開発現場でサステナビリティ対応のインセンティブが働くようにすることが対応案となります。
1つは、インターナルカーボンプライシング(以下、「ICP」という)の導入が取組み例となります。現在、ICPの導入は、再生可能エネルギーを事業所や工場へ導入するために設備投資の計算で用いられるケースが多く見られますが、この考え方を製品開発プロジェクトに適用するという試みです。すなわち、サーキュラー化のようなサステナビリティ対応に対して、仮想的な財務価値を与え、製品開発の現場においてサーキュラー化施策の優先度が上がるような仕掛けを施します。
具体的には、再生材の選定で原価を見積もるときに、バージン材料と再生材を使用したときの炭素排出量をそれぞれ算出し、ICPで設定した社内の炭素価格を乗じて炭素排出量をコストに転換します。そのコストを本来のコストに加え、原価見積を行うことで、実際はコストが高い再生材が、ICPの計算においてはバージン材料より仮想的に安くなり、サーキュラー化施策である再生材を選定するようなインセンティブを働かせます。
実際には、ICPを実務適用することで設計開発担当や原価企画担当の作業負荷が増えることが想定されるため、ICPの自動計算ツール等のIT施策導入や運用面の工夫もセットで考えることが必須となります。
また、ICPは製品開発のシーンだけでなく、さらに上流の研究開発や新規事業でも適用の余地があります。サステナビリティ課題への対応の要請が日に日に強くなる現在において、短期的な収益のみという判断基準で、研究開発テーマや新規事業テーマを判断することは時代にそぐわないと筆者は考えます。ICPを例としたサステナビリティ価値を財務価値に置き換えられるような社内の仕組みを構築して、研究開発や新規事業の取組みが中長期的な目線で判断されるようなオペレーションの変革がポイントであると考えます。
III.SCMのESG対応:サステナブル調達の加速化
1.主要企業の取組み状況
調達に関するサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)については、「サステナブル調達」(=サプライチェーン全体で社会的責任を果たす調達)が重要なキーワードとなります。これまでもグリーン調達やCSR調達というキーワードで、環境問題や人権問題に配慮した調達を行う企業は存在しましたが、2017年に発行された「ISO20400(Sustainable procurement)」や、2018年に採択された「OECD責任ある企業行動に関するデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を契機に、グリーン調達やCSR調達の概念をも含めた「サステナブル調達」の取組みが加速してきた印象があります。
「サステナブル調達」とは、サプライヤーを選定・評価する際にQCDの観点だけでなく、調達先の人権リスク(強制労働、児童労働等)や環境リスク(環境汚染、生態系の破壊等)を評価し、問題点があった場合には是正する取組みのことです。ISO20400では、関連規格であるISO26000に記載されているESG関連のイシューだけでなく、図表4のような調達に特化した要素も定められています。組織統治や人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行に対する社会的責任を果たすことだけでなく、持続可能な調達の実践に向けた実務的なガイドラインとなっています。
図表4 持続的な調達に向けたガイドライン(ISO20400)
| 項目名 | 詳細 |
| 革新的な解決策(ソリューション) | 革新的な解決策(ソリューション) |
| ニーズへの焦点 | ニーズへの焦点 |
| 統合 | 日常的な調達行為とサステナビリティ調達が乖離した取組みになっているのではなく、既存のすべての調達慣行にサステナビリティが統合されていること |
| 全費用(コスト)の分析 | 調達価格だけでなく、調達する製品のライフサイクルを通じた金銭的コストや、社会・環境コストも考慮すべきという概念。ライフサイクルコスティング(LCC)と呼び、エネルギーコスト・メンテナンスコスト・廃棄コストなどを含む総所有コストに加えて、社会・環境にまつわる外部への影響やコストを加味する考え方。具体的には、排出するCO2を金額換算(カーボンプライシング)したものを加えることなどが想定される。将来的にはこのような点も考慮したコストを考慮することが推奨されている |
出典:ISO20400よりKPMG作成
また、欧米を中心に、RBAやSEDEXなどのデータプラットフォームや、EcoVadisのようなCSRパフォーマンスを評価する仕組みの活用が広がってきており、日本においても一部先進企業では登録・活用が進んでいます。
先進企業の取組みとしては、自社独自のサプライヤー評価プログラムを策定し、事前の審査や取引後のサプライヤー監査を徹底、取引継続の判断に生かすような事例もあります。
日本企業においては、SAQ(セルフアセスメント質問票)を活用したサプライヤーへの調査をするに留まり、実地監査まで実施できていないケースは多いと思われます。しかし、昨今の動向を踏まえると、サプライチェーン上のサステナビリティ課題を自社の重要課題であると捉え、通常業務に統合し、経営課題として徹底的に取り組まなければ、時代から取り残されるような時代に差し掛かってきているのではないかと思料します。
2.企業が抱える主な課題
サステナブル調達を徹底的に進めていくには、以下の課題が想定されます。
課題1:サプライヤー管理工数の肥大化
一般的にtier1だけでも多数のサプライヤーがあり、さらにtier2以降も含めると膨大な数のサプライヤーが存在します。また、直接材だけでなく間接材も含めると、その数はさらに大きくなるため、サプライヤーのリスクを踏まえた優先順位付けが必要となります。
課題2:調査の限界(どこまでやればいいのか?)
多くの企業は、teir2以降どこまでどのように調査すべきかを悩んでいます。Teir2以降にはtier1から働きかけてもらう必要がありますが、強制力を働かせることも難しいため、業界全体での取組みや、前述のようなプラットフォーム活用が必要となります。
また、調査手法に関しても、書面調査(SAQ)は有効な手段ではありますが、本質的な問題を的確に捉えるには至らず、虚偽報告の懸念もあります。そのため現場実査が必要となりますが、リソースの課題もあるため、第三者を活用するなどの検討も必要となります。
課題3:調達(購買)担当者・サプライヤーの知見・スキル不足
サステナブル調達を実現するためには一部のサステナビリティ担当者のリソースだけでは足りません。購買担当者やサプライヤー自身に対する知識・スキルレベルの把握を行ったうえで、教育・研修、サポートによる底上げが必要となります。QCD観点だけでなく、ESGの観点でサプライヤーを評価できるスキルを高め、サプライヤーに対しても受入れの体制(文化)を構築していくことが重要となります。
3.課題解決の方向性
これらの課題に対して、以下のような解決策が想定されます。
対応1:包括的なサードパーティーリスク管理体制の構築
サプライヤー管理をバラバラに行うのではなく、統括部門が一括してデータを集約するとともに、リスクが高いサプライヤーを中心に、一括してリスク評価・モニタリングを行うことで管理上の重複が回避できます。
一方で、集約には集約部門のリソースや社内における発言力が必要となるため、経営層による本件の重要性の全社発信や、ESGおよび調達の経験・スキルが一定以上あるメンバーを選定することが重要となります。
対応2:サプライヤー管理プラットフォームの整備
サプライヤーの選定・評価、購買活動、サプライヤーとのコミュニケーション(SAQ含む)、改善活動などを一気通貫で管理できるようなプラットフォームを準備し、サプライヤーに対するリスク管理を包括的・効率的に行うことが有効です(図表5参照)。これにより、サプライヤーとの取引の一連のプロセスをカバーし、また関連データを含めたデータ分析基盤を整備することで、サプライヤーのリスク検知やサプライヤーとの一層のコラボレーションを促進することが可能となります。
図表5 サプライヤー管理プラットフォームのイメージ

出典:KPMG作成
自社でそのようなシステムを開発する以外にも、coupaなどの購買プラットフォームとEcovadisの連携や、SEDEX・RBAなどの活用による効率化や連携も有効です。
このように、調達機能を1つのハブとして、変化を続けるサステナビリティ課題に対する効率的なオペレーションを作り込むことが、サステナブルSCMにおける変革のポイントであると考えます。
IV.コーポレートを活用したサステナブルなオペレーション変革の促進
ECMやSCMといったオペレーションへのサステナビリティの作り込みを成功させるには、コーポレート機能の活用も重要です。
1つのカギはサステナビリティに精通している専門チームの構築です。ある通信機器メーカーでは、外部からサステナビリティの知見を持つ有識者を積極登用し、具体的なオペレーションに深く訴求する形で、ECMやSCM全体でサステナビリティの取組みを最適化できるようなサステナビリティ推進チームを構築しています。設計開発段階における審査会や調達方針を決める会議などサステナビリティ視点の織込みが必要な会議の参加やレビュー、また、ICPのようなオペレーション変革の仕組み構築の企画構想も担っています。
2つ目のカギは、効果的な対外的開示やステークホルダーエンゲージメントに向けた取組みです。ECMやSCMにおける取組みの効果をステークホルダーに対して説明とメッセージングを行い、かつフィードバックを適切に得ることが求められます。
ある産業機械メーカーでは、サステナビリティ対応のための製品ラインナップを充実させていますが、プロモーション施策とともに、環境性能に係る情報開示を充実させて、従来の製品ラインナップに比しての売価増への理解を得ています。
また、調達部門においても、取引先へサステナビリティに取り組む意義、また目標やロードマップを積極的にサプライヤーに発信することで、共感と共創の関係づくりを進めている事例もあります。
V.さいごに
日本は古来より三方良しの考え方があり、現場層におけるサステナビリティ経営そのものへの理解獲得は比較的容易と考えます。本日紹介したように、ECMとSCMといったオペレーションにサステナビリティを真の意味で実装し、日本企業の強みである現場での創意工夫につなげることで、日本の製造業の復権の機会となることを切に願います。
執筆者
KPMGジャパン
製造セクター
パートナー 土谷 豪
シニアマネジャー 大木 俊和