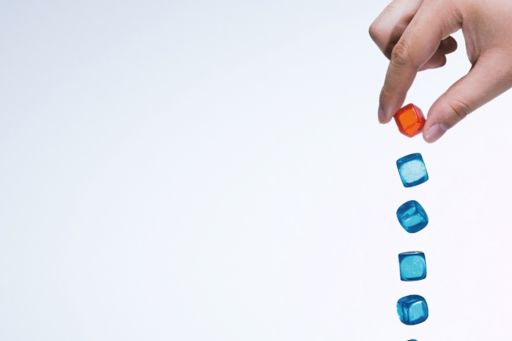企業におけるIT業務機能のあるべき姿~変化に素早く対応するIT実現のために
不確実な環境を機会と捉え、ビジネスとITシステムの連携を深めて対応スピードを高めるために必要な戦略とアプローチについて考察します。
不確実な環境を機会と捉え、ビジネスとITシステムの連携を深めて対応スピードを高めるために必要な戦略とアプローチについて考察します。
ビジネス環境の不確実性と市場の変化速度は加速してきており、先進的な企業は、これを危機ではなく、機会と捉えることができる俊敏性(アジリティ)を獲得して競争力を強化しようとしています。ビジネスとITシステムが一体化した現代において、ITシステムやそれを支えるIT業務にもこの俊敏性が求められています。
しかし、その実現は容易ではありません。先行事例などから有効であると想定できるアプローチを以下に挙げます。
(1)あるべき「全社ITアーキテクチャ」を描くこと
(2)企業におけるIT業務機能の最適な配置をゼロベースで検討して、よりビジネスに連携できる姿を定義すること
(3)人材育成やプロセス・手法・ツール・プラットフォームなどの技術基盤の導入を全社レベルで持続的に実施すること
また、このアプローチを支える要素として、外部依存から脱却し、ビジネスとITの連携を深めて対応スピードを高めることの前提となる内製化推進も要諦であると考えています。
本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りします。
ポイント
- ビジネス環境の不確実性と市場の変化速度は加速している。
- これからのITシステム、IT業務に求められるのは、変化に素早く対応できる能力である。
- 上記を実現するには、あるべきITシステムの定義、最適なIT業務機能の配置、内製化の推進とソーシング戦略の見直し、人材育成、技術基盤(プロセス・手法・ツール・プラットフォーム)の構築を、戦略的かつ持続的に実施する必要がある。
生き残るのは、変化に柔軟に対応できる者である
1. ビジネス環境の不確実性
人やモノ、そして、情報の交流が進んだグローバルフラットの時代においては、有事の際の影響が世界規模で急速に拡大することが明らかになりました。新型コロナウイルス感染症によるパンデミックのなか、多くの企業は生き残るために、カスタマーリレーションやグローバルサプライチェーンなど、ビジネスモデルの抜本的な見直しに迫られています。また、AIに代表される破壊的なテクノロジーが確実に社会に浸透しはじめており、今後どのようなテクノロジーが生まれ、それがどのようにビジネスを変えるのかも完全に予測することはできません。
このように、ビジネス環境の不確実性が高まる社会では、困難な状況や想定外の変化が発生しても企業活動を維持し、むしろビジネスの好機とする俊敏性や柔軟性が企業の競争力となると言えます。
2. 市場の変化速度
ビジネス市場の変化も急激に加速しています。10年永続できるビジネスモデルはなく、常に市場の変化に対応する必要があり、オペレーションも変化をし続けることが常態(ニューノーマル)であると覚悟すべきです。
また、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、もはや目指すべきものではなく、企業が生き残るために必要な前提条件になりつつあると言えるかもしれません。フロント、ミドル、バックエンドを連動してデータをスムーズに連携させることで、オペレーションとIT機能の一体化を促進し、柔軟でスピードのあるシステムと組織を構築することが重要です。
あるべきITシステムの方向
1. 徹底的なシンプル化と最新テクノロジーによる継続進化
あるべきITシステムの全体像を考える際は、業務領域の特性にビジネス戦略を加味して検討することが重要です(図表1参照)。
安定性や保守性が求められるSoR領域は、SaaS(Software as a Service)やクラウドなどの最新技術を活用しつつも、パッケージの標準機能に業務を合わせるアプローチを選択して、ITシステムとオペレーションを徹底的にシンプルにすることを検討すべきです。一方、企業の競争力の源泉となるSoE、SoI領域は、ビジネス環境の変化を前提として、最新のテクノロジーで持続的に進化させることが求められます。どのようにすればエンドユーザーにより深くタッチできるのか、どのようにすれば自社しか持ち得ないデータを収集できるのか、どのようにすれば独自の分析技術を実装できるのか、などの視点であるべき姿を追求し続けるべきです。
もう1つの重要な視点はデータです。データの利活用が競争力の源泉であるだけでなく、過去データの蓄積はお金では買えないという特質から、既存企業が新興企業に対して有利なポジションを確保できる差別化領域でもあります。しかし、データを有効に利活用している企業は非常に少ないのが実情です。
【図表1】ITシステムの特徴による分類

2. ITシステムを支えるIT 業務機能のあり方の検討
変革を目指すには、あるべきITシステムの全体像を描いたうえで、現状のビジネスを維持しながら同時に理想を実現して、ビジネスの変化に素早く対応しながらシステムを変化させ続ける能力をも持たなければなりません。リーダーは不確実性と変化を前提として、IT業務機能の最適化をゼロベースで再検討すべきです。ソーシング戦略立案、内製化の推進などを考慮しながら、あるべきIT業務を構築することが求められています。
次章ではそれを実現するためのアプローチを提示します。
IT業務機能の最適化アプローチ
1. 目指すべき全社ITアーキテクチャの定義
(1) あるべき全社ITアーキテクチャの定義
IT業務機能の検討には、その前提となるあるべきITシステムの俯瞰図を描かなくてはなりません。そして、社会の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、要件追加や変更が容易な目指すべきシステムアーキテクチャの定義が重要です。KPMGは、業務とITが一体となったリファレンス・アーキテクチャとしてコネクティッドエンタープライズ(図表2参照)を提示しており、このモデルをベースとして、業務、システムの現状、中長期のビジネス戦略、システム化方針などの情報を加味し、企業独自の全社ITアーキテクチャを構築していきます。参照モデルを活用した仮説アプローチは、効率性だけでなく、標準モデルというグローバルの知見を自社に取り込む機会となるでしょう。
【図表2】KPMGのコネクティッドエンタープライズ(サマリー)

(2) テクノロジーとのマッピング
あるべき全社ITアーキテクチャに対して、柔軟性の視点や長期のシステム化方針に基づき、「あるべきテクノロジー」をマッピングしていきます。その際には、どの領域についても、クラウド化、SaaS化を第一選択肢とすべきでしょう。これらのテクノロジーは実務に耐え得る有効な選択肢となっており、システムを資産ではなくサービスとして調達することで、変化に対する柔軟性を確保することに繋がります。
(3) あるべき全社ITアーキテクチャの共有
あるべき全社ITアーキテクチャは、ビジネス部門、システム部門の双方で共有すべきものです。そして、新規開発時だけでなく、保守においても常に参照し続けることで、目指すべき方向に向けて日常の活動を整合させるイネーブラーになります。
2. 企業のあるべきIT 業務機能の配置を検討
(1) ビジネス部門を含めた企業におけるIT業務の再定義
企業におけるIT部門の役割およびIT業務機能の最適化をゼロベースで検討することが重要です。事業部門とIT部門を一体化して、ビジネスとテクノロジーの融合を主導した方が効果的なアイデアが生まれ、企画、開発、導入の統合(アジャイル、DevOps)が進み、効率性と迅速性が確保できるでしょう。これはビジネスマネージドITというモデル(図表3参照)であり、よりビジネスに近い組織にIT業務機能を実装します。このモデルの組織としての実現方法には検討の余地がありますが、いずれにせよ、デジタルリーダー組織※1の多くはテクノロジーを社内に広めて業務部門とIT部門の橋渡しを担う機能と、全社ITアーキテクチャを最適化して継続的に改善する機能を最適な組織設計により実装することが重要だと考えています。
※1 デジタルリーダー組織:デジタル技術を活用して顧客へ新しい価値を提供している企業。参考資料:「HARVEY NASH/KPMG 2019年度CIO調査」
【図表3】ビジネスマネージドITのイメージ

(2) 内製化の必要性とソーシング戦略の立案
社会の変化に柔軟に対応してビジネスのスピードを加速させるためには、IT要員の内製化の検討が必要です。経済産業省のレポートである「IT人材白書2017(情報処理推進機構)」によると、日本では、IT人材の約70%がベンダー企業に在籍しており、ユーザー企業にいる人材は30%に過ぎません。一方、米国ではこの比率が逆転し、65%の人材がユーザー企業に在籍しています。これは、日本の企業は、ITテクノロジーの外部依存度が非常に高いことを示しており、ビジネスとITが融合するデジタルトランスフォーメーションの阻害要因だと考えられます。また、ビジネスに対してダイレクトに貢献するITシステムを主体的に検討して実行することができなければ、ビジネスの変化スピードに対応できないケースもあり得るでしょう。
上流は内製、下流は外製という業務機能による従来の内外製の判断に加えて、内製化すべきシステム領域と外製のままで問題が少ないシステム領域の切り分けが重要です。安定性や保守性が求められるSoR領域は、コストメリットがあれば外製化推進の検討も有効ですが、常に進化が必要なSoE、SoI領域は、各ビジネスの実務メンバーとITメンバーの混成チームによるアジャイルでスピードを重視したシステム開発・保守が求められるため、その前提として内製化を進めるべきです。また、危機対応という視点でも内製化比率を高めておくことが有効と考えます。
3. 持続的な人材育成と技術基盤
(1)求められるデジタル人材の定義と育成プログラムの策定
あるべきITシステムとその開発・保守のためには、必要となるデジタル人材の定義が重要です。従来のITスキルに加え、事業部と一体となり最適なソリューションを検討して推進する能力が求められます。また、ビジネス部門からの依頼対応といった守りの意識ではなく、周囲を巻き込み、主体的に推進する攻めの意識も必要です。そのような人材は希少であるため、現状を把握したうえで段階的に、人材育成や配置転換、中途採用や専門人材の外部調達などを組み合わせ、企業としてのIT業務機能を強化していくべきです。
(2)アジャイル、DevOps等の手法・プロセスの導入
事業部門とIT部門がより密接にかかわり、迅速かつ柔軟に行動するためには、適切な手法やプロセスの導入が重要です。アジャイルやDevOpsなどの概念は新しいものではありませんが、デジタルリーダー企業1はSAFe®(Scailed Agile Framework®)※2 などの新しいフレームワークを活用するなど企業での実装に向けて継続的に改善を実施しています。新しい手法、プロセスの導入のためには、上述したようなスキルやプロセスの視点だけでなく、ビジネス担当者が使いやすいローコーディングツールや開発プラットフォームなどの技術基盤、組織・体制、全社の評価基準、さらには新しい企業文化の構築などを網羅的かつ段階的に実施することが重要です。
※2 SAFe(Scailed Agile Framework)®:エンタープライズ向けのアジャイル手法およびフレームワーク、ナレッジベース。
モデル事例
段階的な組織的アプローチにより、工程単位の縦割り組織からプラットフォーム単位の多能工のIT要員からなるIT組織への変革、内製化の推進、ビジネス部門との連携に成功したモデル事例を紹介します(図表4参照)。
この変革により、ビジネスに対応した迅速性、柔軟性を獲得し、デジタルトランスフォーメーションを推進する組織基盤が構築されました。
【図表4】モデル事例

Step1: プラットフォームの整備と全社アーキテクチャの定義
クラウドシフト、SaaS化を推進する組織を新設し、これを実現するとともに、あるべきITシステム全体図(全社アーキテクチャ)を定義。プラットフォーム単位に企画、開発、保守を実施する基盤を順次整備していきました。
Step2:ビジネス部門とIT部門を繋ぐ組織の設立
ビジネス部門からのIT化の要求を一元管理し、機能重複の廃除やあるべき全社ITアーキテクチャとの整合性をチェックする部門として「CoE(Center of Excellence)」を新設しました。この組織は、あるべきITアーキテクチャの視点で、システム化のGo/No Goの判断をする権限を有しています。これにより、新規開発、拡張開発などのIT業務実施のなかで、目指す姿にITシステムを近づけていきます。
Step3:プラットフォーム単位の多能工からなる組織へ
また、CoEは、ビジネス部門とIT部門の連携を推進し、よりビジネスに近い場所でシステム開発を実施することを支援しました。IT要員を細分化されたスキル人材から、1人で複数工程を担う多能工(コンカレント)となる意識付けをしながら、組織もシステム領域、工程単位から、プラットフォーム単位に再編し、1人のITメンバーが事業部と協力しながら、企画、開発、ローンチまでを実施する体制として、リードタイムを削減しました。これにより、外部要員への依存も大幅に低下しています。
Step4:ツールとプラットフォームのさらなる整備
ITオペレーションを変革するための基盤として、最新の手法やツールを検証しDevOpsのさらなる高速/高度化を目指す「R&D」を新設しました。専門部署を設置することで継続的な成果を上げることに成功しました。ローコーディング環境や、開発・保守プラットフォームが整備されることで、ビジネス部門が主体となる開発・運用が可能となっています。IT部門の主たる役割は、環境を整備して、目指すITアーキテクチャを維持するための統制にシフトしていくことになります。
おわりに
目指すべき全社ITアーキテクチャを定義し、企業のあるべきIT業務機能の配置を検討し、それらを実現する人材の育成と技術基盤を構築することは、一朝一夕にできることではありません。トップの意思、持続可能な明確な方針、具体的な計画、現場を含め意識改革が必要であり、長期的で困難なチャレンジとなることでしょう。
しかし、不確実性と変化速度が急激に加速しているビジネス環境を考えると、今こそ立ち向かうべきテーマであると考えます。
執筆者
KPMGコンサルティング
パートナー 浜田 浩之
ディレクター 竹下 智
シニアマネジャー 鈴木 徳之